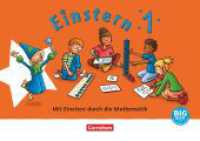内容説明
“書物に耽溺した者に亡霊がとりつく。「現実」という名の亡霊が。(…)構造主義以降の批評は、二十世紀末葉、不可避の帰結として、「現実」に復讐される。テクストの外部が、ハイカルチャーの外部、あるいはヨーロッパの外部というかたちで回帰”するのだ。十九世紀ロシア・リアリズム文学の成立をその植民地表象、とりわけカフカス地方のそれをとおして分析しつつ、“テクスト”と“現実”との相関の現在に介入を試み、ポストコロニアル批評の彼方をめざす気鋭の野心作。
目次
内部と外部
第1部 植民地表象の諸主体(見る主体の変容;知の主体の変容)
第2部 植民地と社交界(表象の約束事性とアイロニー;衣装と真実)
第3部 植民地表象と「現実」(個別性と一般性;表象の「現実性」)
リアリズムとアイロニー
著者等紹介
乗松亨平[ノリマツキョウヘイ]
1975年、大阪府に生まれる。東京大学文学部を卒業後、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学、文学博士。日本学術振興会特別研究員などを経て、現在、オックスフォード大学客員研究員。専攻、ロシア文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nranjen
6
「19世紀のロシア、リアリズム文学の成立を植民地表象をとおして分析したもの」。ここで中心に扱われている「カフカス」というものが、序文で述べられてようにオリエンタリズム、内部の二項対立にあてはまらない特殊性を著者が「その手前の」という言い方をしているのが非常に興味深い。(そもそも植民地なのか?)このカフカス」という表象が社交界という「演劇的文化」によって成立していることも説明されている。プーシキン以外にもエレーナ・ガンなど面白そうな作家も紹介されている。視覚像についての論も面白い。2020/03/27
劇場版 機動戦士ΖガンダムⅡ 恋人たち
1
リアリズムの行為性への転回がサイードであったとして、植民地の代理表象が可能となった言語的条件、即ち記号システムの変遷を、テクストと行為の関係から論じている。親密な読者公共圏において有機的な行為の一部であったテクスト、その崩壊による有機的行為とテクストの切断とペルソナ=無機的行為による統合、後期プーシキンにおいて氾濫するテクストと外部の提出、レールモントフにおけるテクストの行為性の解釈の不可能性、べリンスキーの民族による公共圏の高次の回復、トルストイによる切断されたテクストの現実性における宙吊りという結実。2022/07/09
トム
1
やっと読んだ。レールモントフをはじめとした同時代ロシア作家が「内面化したカフカス」という主題は興味深い。どの文もとても真似できない、当たり前だけど。自分のロマン主義作家への無理解に恥じ入ってしまった、卒論がヤバい。2021/04/29
宵子
0
18世紀~のロシア文学と植民地…と言いつつも、その多くはカフカス(コーカサス)とロシア・ロシア文学との関わりについて記したもの。 しかし、カフカスがロシア文学に及ぼした影響は「ロマンティズム」なのか「リアリズム」なのは白黒付けたい人には、もやもやするかもしれない。 最も、ロマンティズムがあってこそ、リアリズムがあるのだけど。2012/12/02