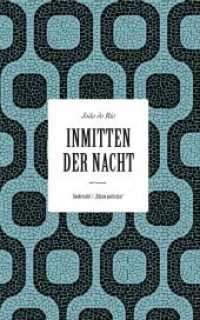- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 芸術・美術一般
- > 芸術・美術一般その他
内容説明
写真や古着、電球やビスケット缶を用いたインスタレーションで、つねに“名もなき者たち”の記憶の可能性を問いつづけてきたフランスの美術家をめぐる初の本格的モノグラフィー。21世紀の“私たち”の“記憶”は、“モニュメント”に託せるだろうか。
目次
第1章 忘却の風景
第2章 遺品のコレクション
第3章 喪うこと、共にあること
第4章 懐かしさと可愛らしさ
第5章 死者のモニュメント
第6章 死を盗まれた人びとのために
第7章 亡霊のまなざし
第8章 記憶の住み処
著者等紹介
湯沢英彦[ユザワヒデヒコ]
1956年東京都生まれ。東京大学文学部仏文学科卒業、同大学大学院人文科学研究科博士課程中退。85年から89年まで、パリ第四大学博士課程に留学、文学博士号取得。現在、明治学院大学文学部フランス文学科教授。専攻、二十世紀フランス文学文化
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
eirianda
4
この人は記憶の墓のようなものを、後に残らせない形で、作品にしているのだな。それにしても03年の日本でのインスタレーションは、以前の作品に比べるとぐんと優しいのはどういう変化なのか?作家の年齢のせいか、それとも日本の里山のせいか?2014/10/27
Rinopy
4
作品を見て興味を持ったので…ボルタンスキーが「死」によって人の記憶が失われてしまう事をとても恐れている…という筆者の考えに同感。瀬戸内で体験した「心臓音のアーカイブ」も絶対的に消えない圧倒的な「生の証明」を表したかったんじゃないのかな…と思いました。2010/11/14
がっちゃん
1
東京庭園美術館にて「アニミタス さざめく亡霊たち」を鑑賞し、作品に立ち会う。芸術は発見。という思いが確信に変わった。作品に、ボルタンスキーに感謝。彼は「神話」を作ろうとしている。見たことはないけど、あることは知っている。そんな作品。「死」「記憶」「伝達」2016/10/26
ケイエム
1
陰鬱な雰囲気の漂う作品だなぁ、時間の重みに潰されちゃいそう。というイメージが強かった彼の作品。初期の作品は滑稽な要素も含んでいて、今の作品にも要素として残っているようだ。いい意味で作品の軽さが見えてきたのが収穫。それは同時に生の軽さにも繫がるんだけど。作品について、ボルタンスキー自身の見解ももっと知りたくなった。2016/01/31
すな
0
秋より長崎に巡回するボルタンスキー展に向け、どのような作品を作る人であるかを知りたく本著を読んだ。普段はそういうことはしないが、彼の場合はなんとなく事前に知りたいという気分になった。 作品そのものは一見するとふざけているような軽さがありながら、通底する喪失に対する意識、けっこう個人的にも感じ入る社会における死が不在になり忘却が代理しているという問題への意識が似ており、ユーモアもあり俄然興味がわいた。この次は作品を観てから、だろう。2019/09/10