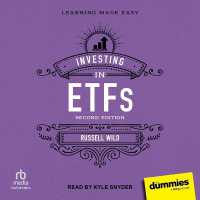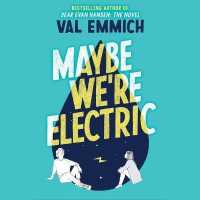内容説明
富の生産を超える危険の生産。人類自らが生み出した危険社会とは―。社会学・科学哲学・政治学にまたがる壮大な視座から展開されるいま最も新しい社会文明論。
目次
第1部 文明という火山―危険社会の輪郭(富の分配と危険の分配の理論について;危険社会における政治的知識論)
第2部 自己内省的な近代化―科学と政治の普遍化(科学は真理と啓蒙から遠く離れてしまったか;政治の枠がとり払われる)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びす男
36
図書館本。30年以上昔の本とは思えないほど、現代の状況を言い当てている■知識と技術が自然を凌駕し、社会は、自ら生んだ危険(リスク)と直面する。誰もが気候変動や核の脅威と無縁ではない。「貧困は階級的で、スモッグは民主的である」■社会や政治は専門家に依存し、人々は身の安全をその議論に委ねる。コロナ禍で見た光景とも重なった■「危険をどこまで受容するか」という社会的合意の段では、価値観や文化がものを言う。この間、SDGsなどの言葉に支持が集まり、世の中を動かし始めている。状況は少しずつ改善されていると、信じたい。2021/11/28
エジー@中小企業診断士
0
1988年9月刊行。ベルリンの壁崩壊前に西ドイツの大学教授がチェルノブイリ原発事故後に書いた本である。現代社会論として産業社会から危険社会と至る要因を分析。とにかく論の運びが難解で抽象度が高い言葉でさらに抽象度が高い概念を説明しているため、要するに何?となる。経済、技術革新が政治のパワーを喪失させ企業が利益追求で外部経済的に国境を越える巨大リスクを生産している危険社会。サブポリティカルの台頭や企業の倫理化など今のサステナビリティの文脈に繋がる。リスク論の「読むべき本」ということではあるが消化不良気味。2021/12/17
-
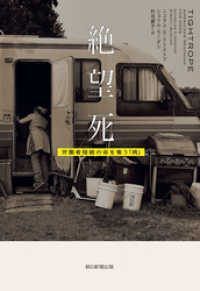
- 電子書籍
- 絶望死 労働者階級の命を奪う「病」
-

- 和書
- 吟詠教本 参考資料篇