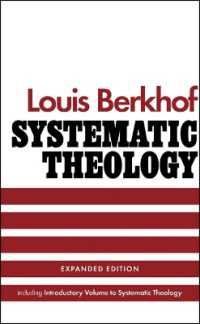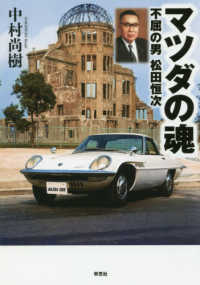内容説明
大切な人が植物状態から一生目が覚めないとわかった時―あなたが望むのは延命治療?それとも尊厳死?アメリカで「死ぬ権利」裁判を担当した弁護士が綴る衝撃のドキュメンタリー。
目次
第1部(テリー・シャイボの人生―一九六三年十二月から二〇〇〇年一月まで;公になったテリー・シャイボの人生―二〇〇〇年一月から二〇〇五年三月三十一日まで;テリー・シャイボの死体解剖)
第2部(医療技術の進歩;死に関する法律と権利;ナンシー・クルーザン訴訟;今日のアメリカで、私たちはどう死ねばよいのだろうか?;「施設のグライドパス」に従って死ぬ;テリー・シャイボの立場;私の「リビング・ウィル」;栄養チューブ―最大の難問;それでも私は生きる権利を信ずる;身障者の社会が抱く特別な懸念;オレゴン州対アシュクロフト(ゴンザレス)、そして医師の自殺幇助
ホスピス:隠れた宝石
私たちはここからどこへ行くのか?)
著者等紹介
コルビー,ウィリアム・H.[コルビー,ウィリアムH.][Colby,William H.]
1955年生まれ。1977年ノックス・カレッジ卒業後、1982年カンザス大学で法務博士を取得する。アメリカ最高裁で初めて審理された「死ぬ権利」訴訟において、ナンシー・クルーザン一家の代理人を務めた弁護士である。「フロントライン」、「トゥデイ」、「CBSディス・モーニング」、「グッド・モーニング・アメリカ」など、数多くの全米ネットワークのテレビ番組に出演。「Patient Self‐Determination Act(患者自己決定法)」として最終的に成立した連邦法の法制化に大きく貢献した
大野善三[オオノヨシゾウ]
医療ジャーナリスト、前NPO日本医学ジャーナリスト協会会長。早稲田大学第一法学部卒業。NHK科学教育部にて主に科学・医療番組の制作を担当。退職後も、NHKエデュケーショナルの依頼により、NHKの医療番組の制作に携わる。2001年医学ジャーナリスト協会会長(現NPO日本医学ジャーナリスト協会)に就任。現在は、フリーで医療番組制作、医療ジャーナリストとして医学・医療記事の解説執筆に携わる
卓ZITO真佐子[ハヤノジトーマサコ]
医療福祉ジャーナリスト、翻訳家。東京医療保健大学国際交流アドバイザー。青山学院大学文学部英米文学科卒業。コネティカット大学等留学。国際医療福祉大学医療福祉ジャーナリズム修士課程修了。東京大学医療政策人材養成講座五期生。1993~2006年までアメリカに居住。アメリカの医療に関する取材執筆、翻訳、編集、研修企画などに携わる。帰国後は、医療、看護、介護を中心に看護/医療系専門誌に多数執筆している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
海星梨
うぃっくす
takao
de sang-froid
-

- 和書
- すばらしいアジアの遺跡