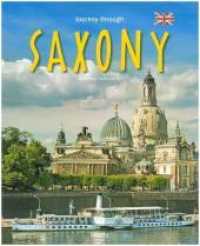内容説明
住みなれたワルシャワの町が、この二年半の間にすっかり変わり始めました。ミーシャは腹の底からわきあがる恐怖、飢え、突き刺すような悲しみを経験しました。ミーシャはゲットーの「弧児の家」に妹二人とともにひきとられています。病気の母さんはゲットーの壁の向こうで暮らしています。ミーシャは壁を越えてお母さんに食べ物を運んだり、病気の看病に出かけていきます。ナチに捕まれば、射殺されるかもしれません。ある日、ミーシャの前で、パンやの親子が、ユダヤ人だというだけで、ナチの親衛隊に射殺されてしまいました。いつかきっと、このかたきはとってやるぞと、ミーシャはかたく心に誓いました。このミーシャたちを守ってくれたのは「弧児の家」の院長コルチャック先生でした。しかし、アンネ・フランクと同じ運命がポーランド人の上にも訪れる日がきました。その日、コルチャック先生を先頭に、二百人の弧児は整然と隊列を組み、「絶滅収容所」に向かっていきました。耐えられない苦痛と絶望の中にあってなお失わない人間の魂の美しさを描き、わたしたちに人間への信頼と希望をよみがえらせてくれる恐怖と愛情の物語です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんちゃん
23
「なぜ、おきたのか?ーホロコーストの はなし」の中で紹介されていた本。ワルシャワゲットーの中で暮らすミーシャは、病身の母と離れ、妹達とともに「孤児の家」にいます。命の危機に常にさらされつつ、ゲットーの壁の向こうとの行き来を繰り返す中で、やがてレジスタンス活動のメンバーとして孤児の家を離れます。日々締めつけが厳しくなるゲットーの暮らしの様子とともに、ミーシャ少年の迷い、決断、家族への思い、ドクターさんとの関わり…大人でも抱えきれないようなものを背負って生きた子どもたちに胸が締めつけられました。2012/12/13
アキ
10
家族のため命を懸けて壁の向こう側目指し『勇気をもって、お腹を空かせて、思いつめて 這う、進む、走る♪』のは「闇取り引き」に向かうゲットーの子どもたち。子どもたちに『死の天使は、威厳と平静さをもって迎えるものと覚えておいてほしい』と願うコルチャック先生…。小学校の上映会で『コルチャック先生』(アンジェイ・ワイダ監督)を見て悲しい想いに暮れた遠い記憶が甦りましたが、著者があとがきで自ら言う「恐怖と愛情の物語」(原題:SHADOW OF THE WALL)を読んだ記憶も、いつまでも忘れられないものとなりました。2013/01/24
lisatread
2
中学以来の再読。アヴェマリアのヴァイオリン後、ホロコースト繋がりで。ゲットーの中の孤児院に暮らすミーシャの視点から見た世界。コルチャック先生の事、この時代のこと、読んでて辛いけど、もっと知りたくなってしまう。。2016/05/25
エル
1
あの時代のユダヤ人が経験したであろう、恐怖、悲しみ、憎しみ…が伝わってくる。ゲットーの外は常に死が隣り合う。子どもだからと容赦しない。子どもだって家族のために、生き延びるために危険を犯してゲットーの外へ出ていく。あの時代、誰もが自分が生きるために必死だった。コルチャック先生のように子どものために生きれた大人がどのくらいいただろうか…ミーシャのその後が非常に気になる終わり方でした。2025/05/27
けむりの猿c((•ω•))ɔ
1
原題は「SHADOW OF THE WALL」だが、この「ゲットーの壁は高くて」というタイトルは秀逸だと思った。ユダヤ人迫害について漠然とした知識のまま読んだ。実在したコルチャック先生の、回想録や、伝記を元に、主にミーシャ少年の目線で語られる物語。すぐ側にある死への恐怖と隣り合わせにある民族の誇り。父の残した僅かな財産を、危険を冒してまで壁の外側で食べ物と交換し、病気の母へ届ける健気なミーシャに感動する。読後にユダヤ人迫害の記事等を読んだが、いわれの無い理由が多く、民族主義の政治的利用だったことがわかる。2020/05/30
-

- 和書
- 自習ノルウェー語文法