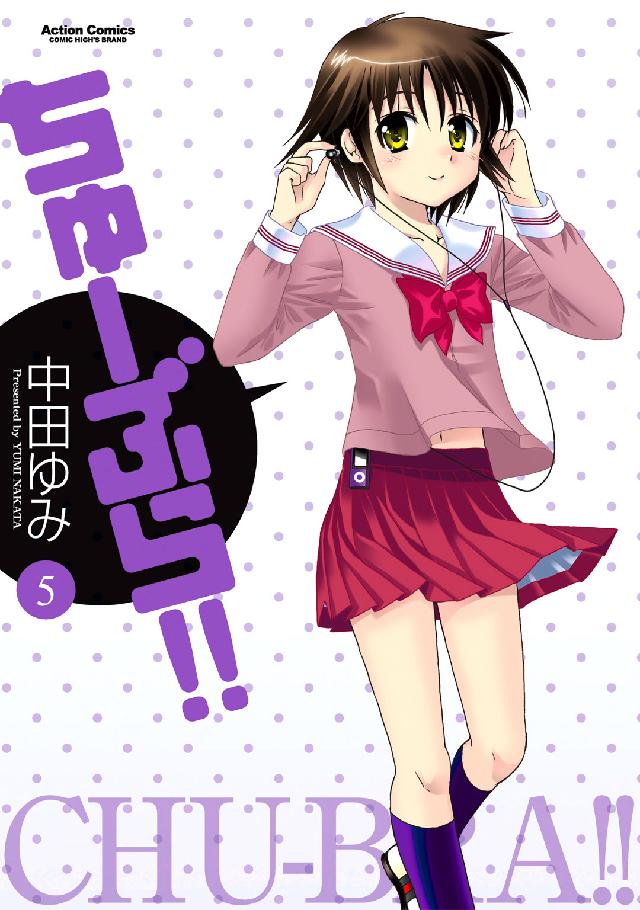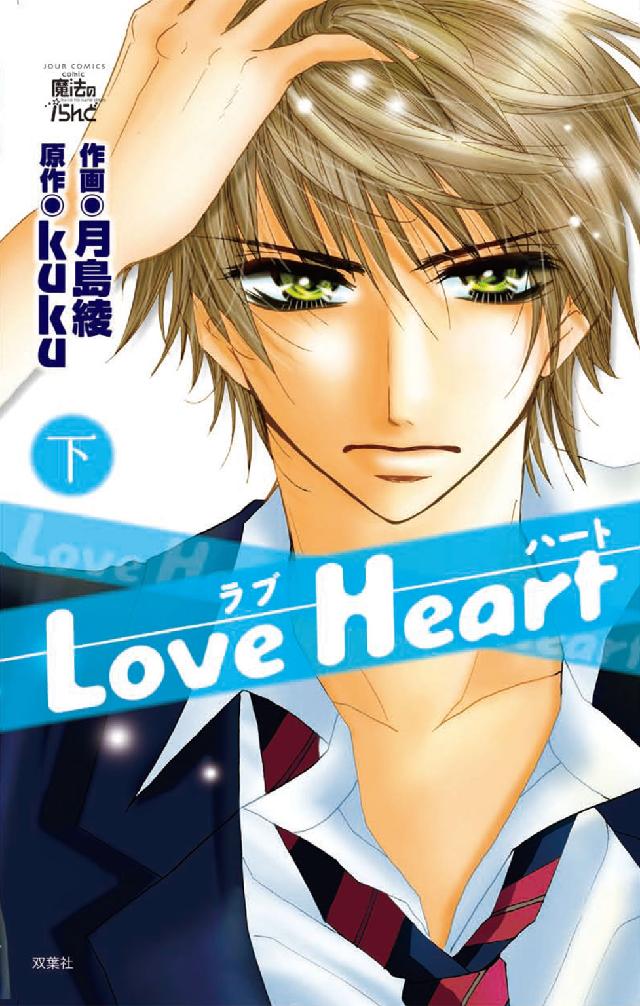出版社内容情報
京都議定書の発効を受けて、好評の前版を全面改訂。第2約束期間(ポスト京都)に向けた展望を加えました。
"1 基礎編 11
1-1 地球温暖化は本当に進んでいるのか? 13
(コラム)地球温暖化のメカニズム 13
(コラム)日本は猛暑・豪雨の国になると予測 15
1-2 気候変動枠組条約とは? 16
(コラム)「地球環境問題」と「国際環境条約」の課題 19
1-3 京都議定書とは? 21
(コラム)日本の基準年排出量は12億3,690万トン(CO2換算) 22
1-4 IPCCが評価した森林・木材の温暖化防止機能とは? 24
(コラム)二酸化炭素トンと炭素トン 26
1-5 温室効果ガスの削減目標と森林との関係は? 27
(コラム)日本の森林は自家用車4,500万台分のCO2を吸収している 29
(コラム)世界の森林は重要な炭素貯蔵庫 30
1-6 日本の森林に見込まれているCO2吸収量は? 31
1-7 京都議定書上の「森林経営」活動とは? 33
(コラム)「森林」の定義 35
1-8 伐採木材(HWP)の取り扱いは? 37
(コラム)木材住宅1軒で国民2人分のCO2排出を相殺 38
(コラム)木材中の炭素量を求める算式 41
1-9 京都メカニズムとは? 42
1ー10 排出量取引には? 76
(コラム)CDMの関連組織 77
2-3 CERはどのように発行・分配されるのか? 78
2-4 指定運営機関(DOE)になるには? 80
(コラム)DOEの役割と責任 82
2-5 バリデーター、ベリファイヤーになるには? 84
(コラム)ISOにおける温室効果ガス関連の新規格 84
2-6 どの指定運営機関(DOE)を選べばいいのか? 87
(コラム)プロジェクトの「スコープ」 88
2-7 CDM植林とは? ①アカウンティング 90
(コラム)再植林の基準年 92
2-8 CDM植林とは? ②非永続性 94
(コラム)COP9におけるCDM植林に関する議論の経緯 97
(コラム)CDMの基本分類(排出源・吸収源・通常規模・小規模) 96
2-9 CDM植林とは? ③クレジット発生期間 99
(コラム)追加性 100
2-10 CDM植林とは? ④ベースライン、リーケージ 101
(コラム)バウンダリー 102
2-11 CDM植林とは? ⑤社会経済的・環境的影響 103
(コラム)侵入性外来樹種とGMO 104
2-12 CDM植林とは? ⑥小規模CDM植林プロジェクト 105
2-13
2 ノン京都マーケット 139
3 リテール・マーケット 140
4 英国の排出量取引制度(UKスキーム) 140
5 EU域内排出量取引制度(EU ETS) 144
(コラム)米国のシカゴ気候取引(CCX) 139
(コラム)グリーン・インベストメント・スキーム(GIS) 145
3-2 森林炭素取引を仲介するコンサルタント 147
1 ヤコ・ペリ社 147
2 トレクスラー・アンド・アソシエーツ社 149
3 三菱証券 150
3-3 世界銀行の炭素基金 152
1 プロトタイプ炭素基金(PCF) 152
2 バイオ炭素基金(BCF) 153
(コラム)カトゥーンバ会議 154
(コラム)世界銀行が指摘する期限付きクレジットの長所と短所 157
3-4 オーストラリアの植林政策 158
(コラム)ニューサウスウェールズ州のポートフォリオ方式 159
3-5 ビクトリア州の炭素権取引 165
1 ビクトリア州の森林政策 165
2 グリーン・トライアングル地域の植林事情 168
3 プロスペクタス――ハンコック社の取り組み 170
(コラム)炭素権を巡る日本国内での者にとってのメリット 189
3-9 日本国内の排出量取引(ET) 191
1 環境省の自主参加型排出量取引制度 191
2 地方分権研究会、東京都、埼玉県の検討状況 193
3 企業内での排出量取引 194
(コラム)三重県のCO2排出量取引制度提案事業 192
3-10 森林吸収量取引試行事業 196
3-11 日本政府の京都メカニズム支援施策 201
1 京都メカニズム活用連絡会 201
2 CDM/JIに関する検討調査委員会 204
3 京都メカニズムに関する検討会 205
4 吸収源対策の第三者認証制度の試行事業 205
5 インドネシアにおける植林の評価方法に関する調査 206
6 CDM、JI植林推進検討ワーキンググループ 207
7 林野庁によるCDM植林関連事業 207
(コラム)日本政府が設置している相談窓口 206
3-12 第2約束期間に向けて① 途上国と米国の参加 208
1 途上国段階的参加方式 209
2 ブッシュイニシアティブ方式 210
3 ブラジル提案 210
4 技術開発普及を中心とした将来枠組みのシナリオ 211
(コラム)注目される途上EBサイト 239
4 引用・参考文献 241"
第3版の刊行にあたって(抜粋)
本書の新訂版を出版してから1年余りがすぎた。この間、京都議定書が発効し、気候変動、あるいは地球温暖化防止への世界の動きにはずみがついた。その1つが2005年7月開催された主要国首脳会議・G8グレンイーグルズサミットで気候変動が主要議題になったことである。これを踏まえ、第3版では第3章を新たに「展望編」とし世界の様々な動きや第2約束期間(2013年以降)の取り組みについて書き下ろした。
気候変動に関する国際交渉の関心は、京都議定書の第1約束期間(2008年~2012年)終了後の2013年以降(「ポスト2012」、「ポスト京都」、「ポスト京都議定書」などの略称が使われている)を睨んだ将来の枠組みづくりに移っている。2013年以降の検討の焦点は、京都議定書を継続して2013年以降を第2約束期間とするか、あるいは京都議定書にこだわらない新たな枠組みを検討するか――に大別される。これにからんで、途上国や米国の参加問題や温室効果ガスの削減目標を義務とするか、自主的取り組みとするかなどが重要な論点となっている。
ここで忘れてはならないのは、2013年以降の枠組みの検討は189の国と地域が批准している気候変動枠組条約の旗
目次
1 基礎編(地球温暖化は本当に進んでいるのか?;気候変動枠組条約とは?;京都議定書とは? ほか)
2 活用編(クリーン開発メカニズム(CDM)を行うには?
CDMプロジェクトの計画を策定するには?
CERはどのように発行・分配されるのか? ほか)
3 展望編(世界のカーボンマーケットと排出量取引(ET)
森林炭素取引を仲介するコンサルタント
世界銀行の炭素基金 ほか)
著者等紹介
小林紀之[コバヤシノリユキ]
1940年東京都生まれ。1964年、北海道大学農学部林学科を卒業し、住友林業(株)に入社。1987年に海外第2部長、1991年にグリーン環境室長に就任。同社の環境部門の責任者として熱帯林再生や様々な環境分野の研究と対策を担い、1998年に理事、2001年に研究主幹。2003年6月に同社を退職し、2004年4月から日本大学大学院法務研究科(法科大学院)教授、同大学生物資源科学部兼担教授。博士(農学)(北海道大学)。現在は、環境省森林等の吸収源に関するWG、林野庁のCDM、JI植林促進検討WG、同CDM植林技術指針調査委員会、森林総合研究所CDM植林生物多様性影響評価委員会などの委員をつとめる。また、世界銀行Bio Carbon Fund技術諮問委員、環境省の京都メカニズムに関する検討会委員、森林総合研究所外部研究評価委員など多くの委員を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。