内容説明
なになに?「たまにはテレビを消そう。自分の目で『見て』みよう。」なんとこれ紀元前三世紀の韓非子「犬馬難。鬼魅最易。」を敷衍したものだ。テレビを受け身で眺めているうちに、それが実物とはちがう疑似映像だということをつい忘れてしまう。自分の意志で「自分から」「見るつもりで」「見る」ことが大事。
目次
他山の石、以て玉を攻くべし。
花発けば風雨多し人生別離足る
吾日に三たび吾が身を省みる。
径路窄き処は、一歩を留めて人の行くに与う。
高山に登らざれば、天の高きを知らざるなり。
当に三余を以てすべし。
入るを量りて以て出ずるを為す。
人の小過を責めず、人の隠私を発かず、人の旧悪を念わず。
三人行けば、必ず我が師有り。
蝸牛角上何事をか争う〔ほか〕
著者等紹介
栗田亘[クリタワタル]
コラムニスト。1940年東京生まれ。65年朝日新聞に入り2002年まで在社。社会問題や世相、教育のあり方などの社説を執筆する論説委員を経て、「天声人語」を担当。2000本のコラムを書いた。現在、日本エッセイスト・クラブ理事。朝日新聞書評委員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モリー
61
日頃、何気なく使っている諺や慣用句の中には漢文に由来する言葉が多いことを改めて知りました。論語や荘子、韓非子、老子、菜根譚、白氏文集、文選、後漢書…、これらの古典を読んだことが無い私でも「三省」や「蟷螂の斧」など日常使う言葉を通して少なからずその影響を受けていたようです。しかし、諺や慣用句として人口に膾炙する以前の原典に近づくことで初めてその真意に気づくことや身にしみることがあるように思います。例えば、三省という言葉は一日を振り返り、少なくとも三つの反省点を振り返ることだと思い込んでいました。反省。🐒2022/10/02
サラダボウル
17
少し前の小説を読んでいると、私は知らない言葉が多いなぁと感じる。本書は小冊子のような手軽なサイズ。筆者は軽やかなコラムとともに漢文を紹介してくれる(児童書ですがそう見えません)。人って1000年以上前から、あんまり変わってないなぁ(蝸牛角上何事かを争う)と思う。オトナになると猛烈に叱ってくれる人もいなくなるから、時々自分で本書の言葉を読まなきゃなぁと感じる(でも寝る前に読むと心地良く寝てしまう‥)。2022/10/18
ロバくん
3
漢文ひとつに約3ページの解説。これがすごく分かりやすく、無駄なくためになります。著者は、朝日新聞の『天声人語』を担当されてただけあって内容が凝縮されています。器の小さな私が、少しでもその器を大きくできたらと思いながら読みました。この本は75ページと非常に薄いため、繰り返し読むべきなのでしょう。日を置いて再読しようと、決心しました。『厩焼けたり」の解説はいいお話しでしたし、『当に三余を』は身につまされました。2017/02/01
toki@kikakulove
0
評価【SR】/【essence・人の小過を責めず、人の隠私を発かず、人の旧悪を念わず】【review・意味は他人の小さな過失はとがめず、個人的な秘密はあばかず、昔犯した罪は忘れるというもの。特に「人の小過を責めず」は社会に出るとなかなか難しい。この言葉を反芻していれば、眉間にしわを寄せて歩くこともない。人間関係をうまくやるコツだろう。】2016/03/20
-
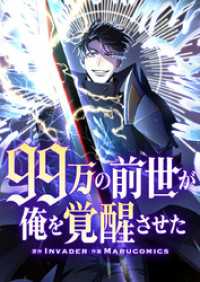
- 電子書籍
- 99万の前世が俺を覚醒させた【タテヨミ…
-

- 電子書籍
- 白衣の英雄(コミック) 分冊版 8 モ…
-
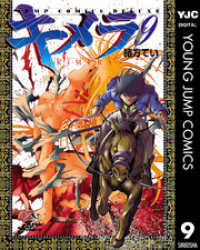
- 電子書籍
- キメラ 9 ヤングジャンプコミックスD…
-
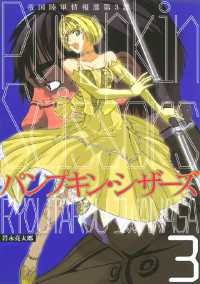
- 電子書籍
- Pumpkin Scissors(3)





