目次
なぜ今、痴呆症高齢者にグループホームか(はじめに―痴呆症とはなにか;優れた痴呆症ケア;グループホームとは何か;グループホームを開くに際して、知っておいた方がよいこと;家族であるということ;倫理)
スウェーデンの高齢者ケアと痴呆症高齢者グループホーム(スウェーデンの福祉観と高齢化;2025年には10人に1人のスウェーデン人は痴呆症の被害者になる;高齢者福祉とグループホーム;痴呆症のグループホームの一例;新しいタイプの痴呆症ケア;スウェーデンの人たちが考える優れたグループホームとは;痴呆症の特性をケアに結びつける;グループホームでのケアをいつまで続けるのか;グループホームの費用)
著者等紹介
小笠原祐次[オガサワラユウジ]
立正大学社会福祉学部社会福祉学科教授。1938年岐阜市に生まれる。1972年東京都老人総合研究所社会学部主任研究員。1983年日本福祉大学助教授。1987年特別養護老人ホームみぎわ園副園長。1990年日本女子大学人間社会学部教授。1997年4月より現職
ベック=フリス,バルブロ[ベックフリス,バルブロ][Beck‐Friis,Barbro]
教授、医学博士。1931年ストックホルムに生まれる。スウェーデンのウプサラ大学にて医学教育を受ける。1969年から1993年まで、モータラ病院で老人医学およびリハビリ学部長、医局長を務める。1993年より、ウストイエタランド県メディカルアドバイザーに任命される。1996年より、シルビア王妃を会長とするシルビアホームの役員、指導、教育を担当。社会省による『政府公式報告書1993:93』作成に関わる。スウェーデン政府、社会省のエクスパートアドバイザーを務める。1958年から現在に至るまで、ウプサラ大学をはじめスウェーデン各地の大学等で学生、医師、看護婦に講義を行う。緩和療法、老人性痴呆症に関する論文、著書多数
ハリソン友子[ハリソントモコ]
スウェーデンイエテボリ市に在住。通訳、翻訳などのフリーランサー。社会福祉関係、イエテボリ市公共関係の通訳等として活躍
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
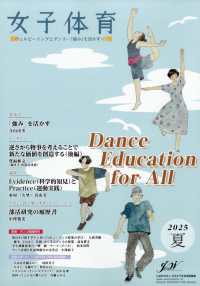
- 和雑誌
- 女子体育 (2025年8月号)
-
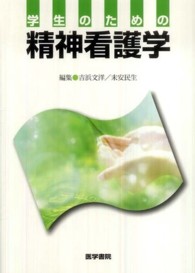
- 和書
- 学生のための精神看護学




