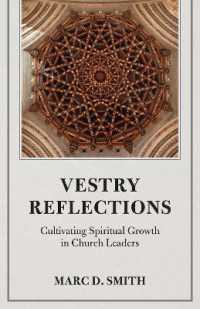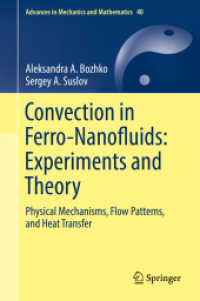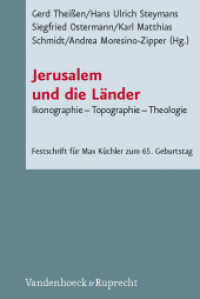内容説明
この矛盾だらけの現在をもたらした原因を、さかのぼって理解するのには、「歴史」特に「長期の歴史」が、不可欠となっている。二人の歴史家は、この数十年間進んでいた歴史の個別専門化の後に、「長期」の物語が回帰していることに注目した。この回帰は歴史研究の未来にとって、また、この長期の物語をいかにして伝えるかの課題にとって、実に重要だと言う。本書は、デジタル時代における歴史学と人文科学の役割をめぐる論争へ、価値ある闘いを挑む。
目次
序章 人文科学のかがり火?
第1章 過去を振り返って未来を見つめる―長期持続の興隆
第2章 短期的過去―長期持続の後退
第3章 長期と短期―一九七〇年代以後の気候変動、統治、不平等
第4章 大きな問題、ビッグ・データ
結論 社会の未来としての過去
著者等紹介
平田雅博[ヒラタマサヒロ]
1951年、青森県に生まれる。東京大学文学部西洋史学科卒業・東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。愛媛大学法文学部助教授などをへて、現在、青山学院大学文学部教授
細川道久[ホソカワミチヒサ]
1959年、岐阜県に生まれる。東京大学文学部西洋史学科卒業・同大学大学院人文科学研究科博士課程退学。博士(文学)。現在、鹿児島大学法文教育学域法文学系教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
40
図書館書棚にて、冒頭にトマ・ピケティが推薦していたので間違いないと思い借り出した次第。世界じゅうの市民は政治的停滞や二大政党制の限界について不満を述べている(7頁)。大学は宗教機関と並んで伝統の伝達者であり、深い知識の庇護者である(9頁)。歴史学は共同体に共同体の意味を説明した。市民にはより大局的な観点から、現在を理解し、未来志向の行動を指導できる座標を提供した(16頁)。歴史学という刃は諸刃である。一方は未来の新たな可能性を切り開く刃であり、他方は雑音、矛盾、過去の嘘を切り裂く刃である(20頁)。2018/03/19
うえ
6
短期的観点による史学(ナタリー・デーヴィスやロバート・ダーントン)らの労作を否定し長期持続の観点からの史学を提唱する。「多様な因果関係に関する歴史家の理論なくしては、原理主義や教条主義がはびこってしまう…歴史家は全体的なレベルでの社会変動を概観する新しい方法論を考案する最先端に立つべきである。少なくとも、学術雑誌、政策文書、ニュースにおけるキーワード使用可能検索を経済報告書、気候データはもちろん、集合体としてのキーワード検索とツイートとさえも比較し対照すべきである」ニューエイジの仏教物理学みたいだなあ。。2021/09/10
佐藤丈宗
5
1970年代以降から短く狭い範囲に限定されたミクロな歴史研究が増え、歴史学が社会に提示できるようなマクロな歴史像が描かれなくなったという。そういう面も確かにあるだろうが、筆者の示す歴史家のポテンシャルや役割に自負と矜持がみえる反面、過大評価しているような気がしないでもない。筆者が例示する歴史学の可能性は素晴らしいものだ。しかし、それが社会に評価され反映されないのはなぜか? 必要なのはこの本が生まれた過程を、自己の専門研究だけに立て籠る歴史家に問い、議論に引きずり出すことだろう。この本ははじまりにすぎない。2017/10/15
-
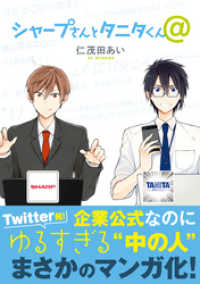
- 電子書籍
- シャープさんとタニタくん@【電子限定特…
-

- DVD
- ビターコーヒーライフ