内容説明
古代メキシコに彗星の如く出現し、強烈な輝きを放ちながら、わずか200年ほどで消滅したアステカ王国。そこで壮大に行なわれた“生贄の祭り”の神髄は、「人間の血を神々に捧げ、神々の血を人間が頂く」ことであった。本書は、古代語文献や考古学・人類学の史料、60点を超える図像資料を駆使して、新しい解釈でアステカ人の精神性に肉薄する、本邦では他に例のない大胆な挑戦である!
目次
序 古代メキシコとの出会い
第1章 アステカ人の供犠と宇宙論
第2章 神々に血を捧げる
第3章 神々から血を頂く
第4章 花と笑い
第5章 クエポニ―戦場に咲くアステカ戦士
結び 宗教現象における創造の力
著者等紹介
岩崎賢[イワサキタカシ]
1972年佐賀県唐津市に生まれる。2005年、筑波大学大学院(博士課程)哲学・思想研究科を修了。博士(文学)。現在、茨城大学・中央大学などで非常勤講師を務める。専攻:宗教学、メソアメリカ宗教史、ラテンアメリカ地域研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
15
図書館本。アステカ神話の最高神が題名の『テスカトリポカ』を読んで、そもそも神様の名前だと言うことも知らなかったし、ただただ残酷なシーンにアステカの神々は恐ろしいと思ってしまったので、勉強のために読んでみた。難しい箇所もあったが、なぜアステカの神々は荒ぶるのか、なぜ生け贄を望むのかが少しわかった。戦わなければ生き残れない世界だったから神もまた猛々しく、生命は循環しているから血を捧げるのだ。それにしても年間どれだけのヒトが生け贄になったのか。心臓を抉られ、首を落とされ、皮を剥がれる。肉親だったら発狂しそうだ。2021/11/26
テツ
14
アステカ帝国で行われていた生贄。神に生命を捧げる儀式。神は人により力を得て人は神の恩恵を受けて(そして気まぐれや怒りにより殺され)持ちつ持たれつ両者は存在していく。死生観や人命尊重の意識などは時と場所により変化し続けていく物だから一概にどれが素晴らしいかなんて僕には判断出来ないけれど、洗練された文明人の我々から見たら血生臭く野蛮に見えるアステカの人々にとってはきっと神様って身近に感じることが出来ただろうな。どんな世界が幸せかなんて簡単には決められないよな。生きたまま心臓を抉り出されるのは勘弁だけれど笑2016/12/13
真田ピロシキ
5
書いてる二次創作小説で国家に使い捨てにされ暴力と権力を憎む女を主人公にしており、ラスボスをアステカ戦士の亡者にしたので参考資料として購読。基本、名誉としての生贄を支配者の方便だろうという先入観で読んでいたので、死を恐れず受け入れる死生観は胡散臭く、太陽を産んだ生贄の神が貧しく病んでいるのも貧民に栄誉という欺瞞で犠牲を強いてるように感じる。しかもコイツ、志願じゃなく命令で大日本帝国じみてる。筆者に言わせれば自分はアステカを逸脱者と見做しているのだろう。だが昔の人間だからってそこまで違うとは思えなくてね2024/01/31
コキア
3
アステカの儀式について掘り下げたく。 儀式は供養という考えで、自ら率先して生贄になることは名誉なこと。心から神に捧げたい為(血と心臓を…) それが彼らの当たり前の思想で死生観 印象的なのは「クエポニ」するという言葉(ナワトル語) クエポニとは、咲く、成長する、光り輝く、など アステカ戦士にとって 人生は闘いであり躍動であり舞である メキシコの国旗はアステカ神話がモチーフになっているのね‼︎ (サボテンの上でヘビを食べてる鷲がいる土地)2023/07/29
takao
2
ふむ2024/07/28
-

- 電子書籍
- 【無料ためし読み版】つばさのイチオシ!…
-
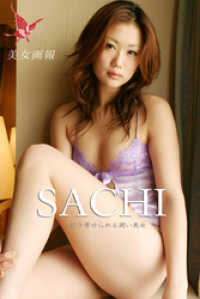
- 電子書籍
- 美女画報 SACHI 引き寄せられる潤…






