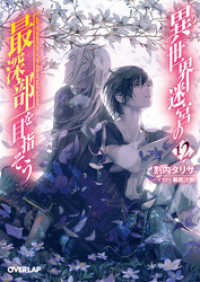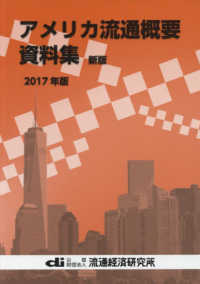出版社内容情報
『史学雑誌』第118編第6号「新刊紹介」より (評者:大豆生田 稔氏)
本書は,富山県の農民運動指導者矢後嘉蔵(1900-1984)の足跡を浮き彫りにしたもので,自身の著作や原稿,裁判書類,インタビュー記事などにより,1920年代半ばから50年代にいたる活動をえがいている。(略)こうして1920年代半ばから,富山での精力的な活動がはじまる。(略)小作争議を裁判闘争戦術で指導し,30年には立入禁止,土地取上などの事件を闘った。その経緯は,回想や自ら残した書類などによって生き生きと語られ興味深い。(略)大審院まですすむ裁判闘争は,40年にようやく結審したが,いずれも永小作権の認容という点では「勝訴」であった。「不敗の農民運動家」という本書のタイトルは,このことによる。(以下略)
『大原社会問題研究所雑誌』2009.6号 No.608より(評者:横関 至氏)
本書は,戦前・戦中・戦後を通して富山県農民運動の指導者であった矢後嘉蔵(1900年生まれ,1984年死去)の生涯の歩みをまとめたものである。富山県での農民運動は永小作権との関連や全農全会派の拠点組織の存在という点から異彩を放っており,その歴史的分析は久しく待たれていた。待望の書物の誕生である。(略)
1 本書の概要
‐‐‐
2 従来の研究での矢後評価
‐‐‐
3 疑問点
‐‐‐
4 構成上の幾つかの問題と要望点
‐‐‐
5 岩本由輝氏の解題について
‐‐‐
おわりに
幾つかの注文を書き連ねて来たが,本書の聞き取りと資料は矢後嘉蔵の粘り強く合法的な活動を雄弁に物語っており,本書は極めて貴重な書物である。(略)矢後嘉蔵の名は,農民組合解散後も裁判闘争を継続し永小作権を認める判決をださせた農民運動指導者として,合法場面で活動しつつ非合法活動の人々を支援し敗戦直後の時期の富山県での社会党と共産党の共同行動の基礎を作り出した人物として,富山県の社会党を代表する政治家として,後世に残されていくことであろう。妻や子供から尊敬されず死後には関連資料も捨てられ忘却されたままになってしまう運動家が多いなか,娘さんによってこうした書物を作ってもらえた矢後嘉蔵は幸せである。(以下略)
『図書新聞』2008.10.18より、評者:南雲道雄
土着、独自の運動を貫いた草莽の闘士―矢後嘉蔵の人柄と肉声が聞こえてくる―
農民運動家矢後嘉蔵、といっても知る人ぞ知るで、関係者以外、その名を記憶する人はごくわずかと思われる。1930年代から40年代、いわゆる戦中・戦後にまたがる激動の「昭和」を、農民運動一筋に生きた人物であった。本書は、その84年の生涯と運動の事績を跡付ける詳細な伝記的資料の集積である。主な活動拠点が富山県なので、異色ですぐれた組織者、活動家であったにもかかわらず、一般には知られにくい面があったと考えられる。
・・・中略・・・
一口に農民闘争、小作争議とは言っても、様々であって、複雑な形態で生起する事は、第二部の訴訟関係資料
でもうかがえる。合法で裁判に立ち向かうとすれば、小作農民の現実や状況の正確な把握はもちろん、検察や
裁判官に劣らぬ現実認識と知識、勇気が必要であろう。その好例として目を引いたのが<永小作権>確保の訴訟。昭和6年、33歳のとき、小作人側の証人として、法廷で述べた調書の内容。永小作権保護の慣行で、地主は、小作人に不都合がない限り、同一小作人に永久に耕作させる、というもの。矢後は従来慣行の実質を武器とし、この訴訟を勝ちとった。この例に見られるように、その後の矢後の運動とたたかい方は独特で、当時の“全農本部”の方針とは異なる地域と風土に根ざした活動を展開したものと思われる。(以下略)
目次
第1部 矢後嘉蔵の生涯と事績
第2部 矢後嘉蔵年譜
第3部 小作争議訴訟関係資料抜粋
解題1 農民運動家矢後嘉蔵の戦前・戦後
解題2 矢後嘉蔵の土着の思想と「永小作権」