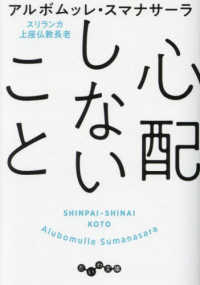出版社内容情報
『西洋史学』2007年No.228(2008.3発行)書評より
「啓蒙思想はフランス革命にいかなる影響を与えたのだろうか。」本書は、長年に亘ってこのテーマを中心に研究を積み重ねられてきた著者が、既発表の論稿を軸にして一書に纏めあげられたものである。・・・略・・・・
本書でとくに焦点があてられるのは、革命家バレールとその出身地ともいえるフランス南西部の町トゥルーズである。・・・略・・・第一部では、バレールの生涯の解説をふまえて、バレールがトゥルーズの地方アカデミーに応募した懸賞論文(第一―第三章)や弁護士としての活動(第四章)、さらにボルドー科学アカデミーへの応募論文に関する精緻な分析がなされる。・・・略・・・第二部では、トゥルーズ全体の啓蒙活動に視点が移され、アカデミーの活動(第一章)や、バレールと同様弁護士でありながらアカデミーの活動も行ったラクロワ、ジャム、マーユ三人それぞれの事例分析(第二―第四章)が提示される。・・・略・・・本書全体をとおしてとくに感じられるのは、各章における史料調査や言説分析の実証性とその精度や水準の高さであろう。・・・略・・・本書は、「啓蒙とフランス革命」に関するわがくにの研究の到達点であり、このようコメントによっていささかもその価値が減じるものではない。
『日本18世紀学会年報』No.23(2008.6.16)書評より
啓蒙思想とフランス革命の間には因果関係ないしは影響関係があるとする見方が、長い間、内外のフランス革命史家の間に広まっていた。思想史家たちの多くも、のちに勃発するフランス革命のことを強く意識しつつ啓蒙思想を論じてきた。フランス革命とは、これすなわち、資本主義経済を担い繁栄するブルジョワジーと封建的領主制に立脚し衰退する貴族の間の階級闘争で、前者の利害意識・世界観・理念を表明したものが啓蒙思想だというのである。・・・略・・・山崎氏はまず、フランス革命の対極に「啓蒙思想」でなく「啓蒙運動」を置き、著者のタイトルを『啓蒙運動とフランス革命』とする。一定の著名作家・哲学者の作品を直ちに想起される「啓蒙思想」よりも、単に宗教・政治・法律といった広義の文化現象を自覚的・批判的に考察し、それに基づいて改革をめざす態度を漠然と意味する「啓蒙運動」を選び、問題を設定し直すのである。そして、ある革命家の三部会開催以前の思想形成をあとづけ、それを革命期の行動とつきあわせる。選ばれた革命家はツゥルーズ高等法院弁護士で、三部会議員あよび国民公会議員、とくにモンタニャール派独裁期の公安委員会委員として活躍したベルトラン・バレール(1755-1841)である。・・・略・・・第二部では、ジュ・フロローを中心に、革命期のトゥルーズにおける「知識人」社会の思想状況・知的雰囲気が紹介される。・・・略・・・なお、バレールの著作同定を試みた第一章、モンテスキューが超人的ヒーローとして登場する80年代の戯曲を紹介した第二章、サン=ジュスト著『革命の精神』を「生きられた啓蒙思想」ないしは「啓蒙思想の読解」の一事例として分析した第三章、ルソーとフランス革命というテーマの研究が「アプロプリアシオン」の概念の適用によってどう異なるか具体例を挙げて論じた第四章が補論として付いている。本論と同様、論証は緻密で、説得的である。
目次
第1部 バレールの思想形成(バレールの生涯;懸賞論文(社会思想;学問と哲学)
弁護士バレールの活動
「モンテスキュー頌」
革命へ)
第2部 トゥルーズでの啓蒙運動(アカデミーの活動;ピエール・フィルマン・ド・ラクロワ;アレクサンドル=オーギュスト・ジャム;ジャン=バチスト・マーユ;結論)
補論(バレール作「モンテスキュー頌」のテクスト;モンテスキューをめぐる三つの戯曲;サン=ジュスト著『革命の精神』をめぐって;ルソーとフランス革命―バルニとロビスコ)
著者等紹介
山崎耕一[ヤマザキコウイチ]
1950年神奈川県生まれ。一橋大学社会学部卒業。同大学大学院社会学研究科博士課程を単位習得により修了後、同大学社会学部助手、武蔵大学人文学部助教授、同教授を経て、2000年4月より一橋大学社会科学古典資料センター教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。