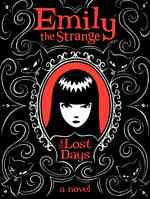目次
第1章 村の役割、種類、住人(中世、「ゼムリャ」は国土を指し、「ドルジャヴァ」は領地や領主権を指した;ゼムリャが国土の一部だけを指す場合もあった ほか)
第2章 村の輪郭、村が負った責任(無人地は「自由の地」?;村の外郭としての境界 ほか)
第3章 村の発展段階、村の土地所有(分村と村の発展段階;村の流動性と分村の成立 ほか)
第4章 村の土地共同体、村のザドルガ(土地共同体は実在したのか;「農業共産主義」は実在したか ほか)
著者等紹介
越村勲[コシムライサオ]
1953年富山県に生れる。1977年一橋大学法学部卒業。1980年ザグレブ大学大学院政治学研究科修士課程修了。1985年一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了(社会学博士)。一橋大学特別研究員、千葉大学助手、東京造形大学助教授などをへて、1998年より同教授、中央大学・一橋大学講師
唐沢晃一[カラサワコウイチ]
1967年神奈川県に生れる。1992年早稲田大学文学部西洋史学専修卒業。2002年早稲田大学大学院文学研究科史学西洋史学科博士後期課程修了。2003年早稲田大学文学部非常勤講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
人生ゴルディアス
4
ユーゴスラヴィア紛争しか知らず、歴史書でも大体蛮族の住処とされるバルカン半島の村と家の歴史。まず邦語文献が少なく選択肢がほとんどない。本書も百二十年前の本の翻訳なので、この業界の苦労がしのばれる。『ハプスブルク軍政国境の社会史』も並行して読んでるけど、こっち読むとセリシュテの意味がだいぶ変わる。放牧の山の民が多く(世界のどこでも国家権力に従いにくい人々)戦乱に悩まされて難民が当たり前みたいな過酷な地域だったようだ。マイナーな国の本なのでとにかく地名がわからない。ぐぐってもうまく出てこないことが多い。2019/02/11
しいかあ
0
民俗誌的なのとか考古学的なやつを期待していたら、中世の行政文書を読み解いてそこから浮かび上がってくる村や家族のかたちについて解説した本だった。なのでまあ個人的にはちょっと期待はずれ。これだけ読んでもいまいち要領を得ないので、バルカン地域の歴史や文化を他の本とかで補ってやると、概観がつかめるのだろうなあと思う。2021/11/15
-
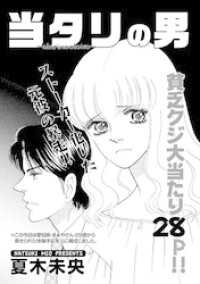
- 電子書籍
- 増刊 地獄の主婦SP vol.2~当タ…