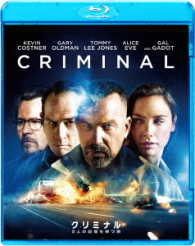内容説明
地震大国・日本に住む全ての人に、―しっかり食べて生き延びる「災害食」推進へ本気の提言。阪神・淡路、東日本大震災、そして熊本地震…もう待ったなし!
目次
第1章 熊本地震が投げかける災害食の問題点と教訓(熊本地震発災後3日間の飲食物供給状況;発災直後の炊き出しが意味すること ほか)
第2章 災害食とは―選び方のポイント(なぜ食べ物を備えるのか;災害食の3つのステップ ほか)
第3章 災害時に足りない野菜―備蓄のコツ(災害時に最も食べたかったのは野菜;災害時になぜ野菜が不足するのか ほか)
第4章 自治体に求められる飲食料備蓄とは(救援物資はなぜ同じような食料ばかり届くのか;自治体に求められる災害弱者向けの備蓄 ほか)
第5章 災害時の炊き出し準備―アルファ化米の活用法(ご飯を炊けない人が増えている―マニュアルと訓練を;手ぶらはおかしい避難訓練 ほか)
著者等紹介
奥田和子[オクダカズコ]
福岡県生まれ。広島大学教育学部卒業。学術博士。専門は食生活デザイン論。甲南女子大学名誉教授、NPO法人日本災害ボランティアネットワークNVNAD理事。日本災害食学会顧問(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ochatomo
5
阪神大震災を経験した著者が熊本地震の場合を調査 個人備蓄は3日~1週間分必須 野菜ジュースが水分兼野菜の補給になってお勧めとのこと アルファ化米はスープやおかずをいれて作ることもでき、ハイゼックス法等使い慣れておくことが肝心 炊き出しは衛生面で手洗い水が確保できてからとする 米をたくさん炊く場合は沸騰湯に水切りした米を入れる湯炊き法を用いる 炊飯時に米の0.5%の塩を加えればそのまま握り飯にできる(湯のみにラップを敷いて作る) 2016刊2018/07/09
鵞鳥
2
熊本の地震時のデータが参考になります。たしかに、野菜類の備蓄はなかなか足りてない気がします。2020/11/12
あちこ
2
わたし用に借りた本。これはぜひとも、市役所や県庁の、そういう部門の人に読んでもらいたいねえ。経験をいかすって当たり前のことだけど、そもそも知らないとどうしようもないもの。2017/03/21
ISBN vs ASIN vs OPAC
0
一線級資料。避難所運営マニュアルはそろそろ整備されていてしかるべきだと思うのだが、まだない?ある?探してみよー。にしても、アルファ化米の戻し方は百万円級情報、ってか炊飯でも試せんのかな?やってみてー!2024/05/23
-

- 電子書籍
- Berry's Fantasy 竜王陛…