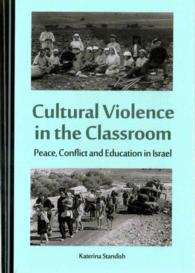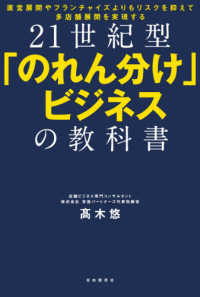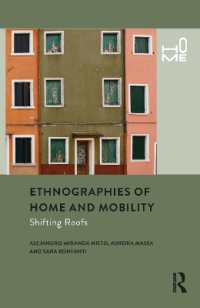内容説明
教師は生徒と対等な人間関係を築き上げる努力をするべきだ。必死に生きる卒業生たちの現在から、学校の役割をみる。
目次
第1章 不満そうなオーラを発していた生徒の“変身”―坂口智佳 35歳
第2章 “答えのない授業”を経験して―田中耕太 31歳
第3章 私の授業を見学にきた大学院生―山下愛 27歳
第4章 文化祭に燃えたクラス―D高校の卒業生たち 26歳
第5章 人生最後の担任でのサプライズ―石田梓・青山翔・畑中諒 20歳
第6章 2014年の中高生と私
第7章 いま、という時代―まとめに代えて
著者等紹介
小泉秀人[コイズミヒデト]
1952年3月生まれ。都立立川高校、東京大学経済学部卒業後、高校の社会科教員ひとすじ。都立高校で非常勤教員をつとめるかたわら、2015年4月より、首都大学東京と専修大学で講師をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
パフちゃん@かのん変更
55
高校の社会の授業と言えば先生がひたすら話して板書するイメージだが、小泉先生は参加型の授業を作り上げる。そのための毎回のプリントづくりや資料などの努力を惜しまない。こんな授業を受けてみたいものだ。生徒一人一人が大切にされ、みんなが仲良くなる。大人になった彼らはそこで培った力が「相手と交渉したりするときや、人を巻き込むときに役に立っている」とのこと。2017/01/05
ぴーたん
3
授業が終わっても「井伊直弼が殺された原因はなんだろう?」と議論する女子高生たち。授業外で「このことについて友達と話してみたい!」と思える授業ってどんな授業なんだろう?この先生が持つ膨大な知識と、歴史と今をつなげる問いが優れているのだろう。この本は定年を過ぎた元都立高校の先生が20代から30代の教え子達に会いに行き、学校での学びが卒業後にどう活かされているかインタビューするという内容。生徒とつながれたと実感できるようになったのは40代も半ばを過ぎてからという。自信がない私も少し希望が持てた。2015/06/13