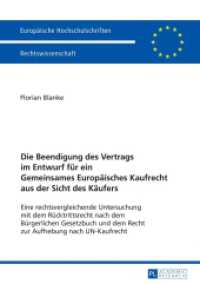出版社内容情報
助け合う関係の歴史、再び学ぶ共存の哲学。
「孤独な現代の個人主義者のこころにも、どこか深く響きわたるものをもった本である」(朝日新聞・書評)
v
クロポトキンの「相互扶助論」は1996年5月に初版が発行されました。当初、そんな古い本は出しても売れないのではないかといった慎重論が、社内でも支配的でした。日本で普及された大杉栄の翻訳本は、当時は名訳の声が高いものでしたが、いま読んでみるとなかなかなじみにくい、分かりにくいという声もありました。思い切って現代語に直してみました。それでも初版は恐る恐るの1000部でした。ところが、発行してみると当初の心配は杞憂でした。その年の8月、「朝日新聞」に書評が載りました。あっという間に増刷。そして、今回(2000年4月)の増刷。相互扶助の精神は時代によって求められていたのでした。
内容説明
ダーウィンの進化論の影響を強く受けながらも、それの「適者生存の原則」「不断の闘争と生存競争」を批判し、生命が「進化」する条件は「相互扶助」にあることを論証した。究極の市場経済としての現代においては、相互扶助関係の前提としての「社会」が崩壊の危機に瀕している。現代こそ甦る「相互扶助」思想の原典、ここに現代語訳で復刻。
目次
動物の相互扶助
蒙昧人の相互扶助
野蛮人の相互扶助
中世都市の相互扶助
近代社会の相互扶助
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
35
単行本は1902年初出。それでも色褪せない。読み進むにつれ、生物学から文化人類学へシフトした感じがする。【社会の再建へ】(ⅱ頁~1996年)。これは音読したが、20年前だが不朽の真理。「競争してはいけない。競争は常に種に有害なものである。そしてそれを避ける方法は幾らでもある」のが自然の傾向(95頁)。ロシア百姓の諺:決して乞食の袋を下げぬとか、牢屋には行かぬとか言ってはいけない。カビール人は実行する。貧者が助力を求めれば、富者は畑へ行って働く。貧者が相互的に富者のために働くのと少しも違わない(166頁)。2016/04/08
きいち
14
歴史も自然科学も、平和の破壊や生存競争は記しても平和を記さぬ、それはただ事件にならないからだけ、生きる物の基本原則はお互いの助け合いにあるのだ!そんなふうに何とも大らかに歴史を読み替えてくれる。アナーキストとしか知らず、革命家の暗いイメージだったクロポトキン(そして訳者の大杉栄)、とことん陽性で人を食った魅力的な文章ではないか。◇苦学中の宮本常一がはまった本、ということで読んでみたのだが、宮本の集めた瀬戸内や対馬の民俗を思わせる事例も多く、読んでて「これなら日本もそうだ」とワクワクしたろうなと楽しくなる。2013/12/01
χ
2
人間・自然賛歌にあふれてる。動物、原始人、原住民、中世ヨーロッパ、貧民層、労働者間に相互扶助の習慣がある、という内容。その方が生き延びる確率が高まるからだけどそれだけとは思えない自己犠牲の話は美しい。1人でも欲を出すことでこのバランスが崩れてしまうのだろう。発展を望む気持ちや可能性が少ないならすごくなじむシステムだと思う。内向的な身としては抵抗があるけど2012/04/24
スズキパル
1
蒙昧人の氏族社会、野蛮人の共産村落、中世都市における同業組合などを例に出しながら、人間の相互扶助の営みがいかに文化や科学の発展に寄与したかを説く。社会進化論に基づく生存競争や個人主義がもてはやされいた当時の世相への批判も強く感じられた。アナキストとして有名なクロポトキンだが、中央集権国家による社会の諸機能の吸収や、偏狭な個人主義にたいして警鐘を鳴らすその思想は、現代のコミュニタリアニズムにも近いよう思った。2014/06/03
tk
1
メモ。 アナーキズムがわからない。2012/05/02