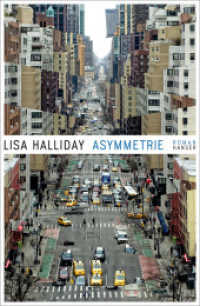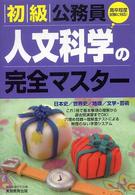内容説明
肯定が否定であり、否定が肯定である「即非の論理」こそ禅の公案を解く鍵。これはたとえば、語り得ぬゆえに指し示されるほかない神は、神ではない、ということを証す論理ではないか。前期『論考』に発する論理実証主義、後期『探求』の影響下にある日常言語学派など、現代哲学の源流というべきウィトゲンシュタインの哲学によって禅の核心を解く。
目次
1 ウィトゲンシュタインという哲学者
2 哲学とは知性解放の戦いである
3 登り切った梯子は投げ捨てねばならない
4 考えるな、見よ
5 「即非の論理」のウィトゲンシュタイン的理解
6 ウィトゲンシュタインは宗教的人間であったか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shiba
2
『はじめてのウィトゲンシュタイン』を読んでいて、ちょっと禅っぽい?と思って探したら見つかった本/世界をあるがままに見んとするウィトゲンシュタインの思想は、カテゴリ化や体系性を重んじる西洋の土壌では受け入れられにくく、むしろ東洋的であったという話/鈴木大拙にも触れてみたいかもと思った(鈴木大拙の論を引用している部分はとても難解だったけれども)/ウィトゲンシュタインについての説明が若干わかりにくく、先述の入門書の内容を覚えているうちに読んでよかったと感じた2024/04/27
村崎未夢
0
ウィトゲンシュタインの思想と禅の思想を比較し、主に鈴木大拙を引用しながら禅の見解のウィトゲンシュタイン的解釈の可能性を示した本。その試みがうまくいっているかは、正直なんとも言えない(禅の思想に対する言及があまり多くなく、全体として十分な比較が出来ているわけではないように思う)のだが、ウィトゲンシュタインの前期・後期の思想が端的にかつ分かりやすくまとまっているので、ウィトゲンシュタイン哲学の入門書としては良いと思った。2018/01/03