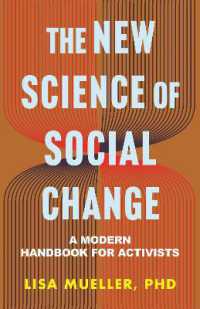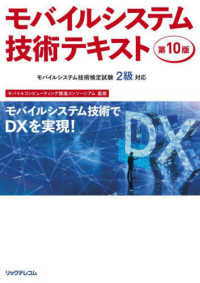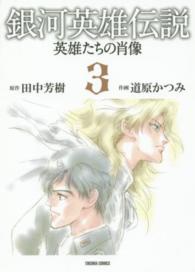- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
目次
ここに二つのパイプがある
こわされたカリグラム
クレー、カンディンスキー、マグリット
言葉の陰にこもった働き
肯定=断言の七つの封印
描くことは肯定=断言することではない
ルネ・マグリットの二通の手紙
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
彩菜
29
画布には恐ろしく単純なパイプの画とそれを名付ける文、「これはパイプではない」。何と言う異様さ。画像と言語が分離している。…物を見る事と語る事は同じではない、その距りを画布は二つの原理により結び付けてきた。①言語と画像の従属関係。②物への類似=その物であるという断言。画布にパイプと書いてあれば其処に在るのはパイプの画でなくてはならず、その画がパイプに似ていればその画はパイプだと断言している事になる。画布という共通の場で、言語と画像は戯れ絡み「物」のただ一つの形象を創る。画布、それは私達の思考の事でもあるのだ2021/10/25
roughfractus02
10
西洋絵画の成立をあるモデルに表象とその肯定という2つの類似の原理として捉える著者は、パイプの図に「これはパイプではない」とキャプションのあるマグリットの絵に、鑑賞者が現実世界に存在する物の再現として見てきたオリジナルを基点とする類似のオーダーから、オリジナルのない相似のオーダーへの移行を見る。この移行は「これはパイプではない」という文の意味を単なる線の連なりに変える。『言葉と物』の分析で拡張されたソシュールの言語の恣意性なる概念が、この小著では絵画も含む表象システムに向けられる。現実世界もまた模造なのだ。2024/11/26
Meroe
5
「これはパイプではない」と画中に書かれたマグリットの絵画。画中画の中に描かれたパイプ、その下の文字、不安定なイーゼル、画中に対応するものを持たないその上のパイプ。文字と画像の共犯関係。「世にもおとなしい画に、『これはパイプではない』といった類いのただし書きがついていれば、それだけでたちまち図像がそれ自身の外に出、自らの空間から切り離され、遂にはそれ自身から遠くにか近くにかはいざ知らず自己に似たもの、あるいは異なったものとして漂い出ることを強いられるには十分だった」。2012/03/13
kentaro
4
⚫︎カリグラムは、鳥とか花とか雨の形のもとに「これは鳩である、花である、降りしきる驟雨である」と言いはしない。そう言いはじめる瞬間から、言葉が語りはじめ、意味を解き放ちはじめる瞬間から、鳥はすでに飛び去り、雨は乾いてしまっているのである。カリグラムはそれを見ている人にとっては、これは花である、これは鳥である、とは言ってはいず、まだ言うことができないのである。それはまだあまりに形に捕えられており、類似による表象にあまりに従属させられているのでそのような肯定を言明することができないのだ。そしてそれが読まれると2024/10/01
wadaya
4
芸術家がぶつかる壁の一つに個性の問題がある。自作品や考えが他人のものに類似していると感じることがあるからだ。物と物は相似する(複製)けれども芸術作品は類似であっても相似ではない(模倣)フーコーは思考は相似なしに類似すると言っている。つまり類似には個性が宿ると言っている。「これはパイプではない」既成概念の破壊かと思ったが、そうではなくて(フーコー的笑)類似の肯定について絵画を例に書かれている。確かピカソも言っていた「個性は誰にも似ていないことではなく、誰にでも似ていること」だと。自信を持って自身を描こう!笑2018/06/08