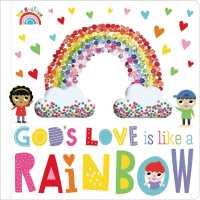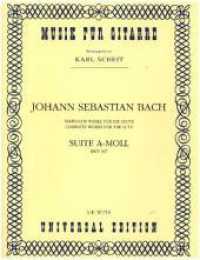内容説明
修験道の行者である山伏らが中近世にかけて集団化していく動向に着目し、彼らと顕密寺院との関わり等を詳細に検討。中世修験道が地域社会において果たした社会的意義を究明する。
目次
修験道研究の動向と本書の視角
第1部 中世修験道の地域的基盤(中世後期顕密寺院における山伏の実態;中世後期顕密寺院の「寺領」形成過程とその展開;中世後期顕密寺院における如法経信仰の展開と生業)
第2部 中世修験道の展開(中世地域社会における修験の「宿」;中世後期の「国峰」と修験の「宿」―越知山修験の維持管理をめぐって)
第3部 修験道の「集団化」と近世への展開(中世後期の熊野参詣の「衰退」をめぐる再検討;中世熊野参詣の変容と熊野御師の動向;戦国期の修験道本山派山伏への展開と山伏集団の構造―信濃国佐久郡大井法華堂の事例から;中近世移行期における修験の「家」の展開―紀伊国加太荘「向井家文書」の分折から)
中世修験道の総括と展望
著者等紹介
小山貴子[コヤマタカコ]
1972年東京都生まれ。2020年専修大学にて博士(歴史学)取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。