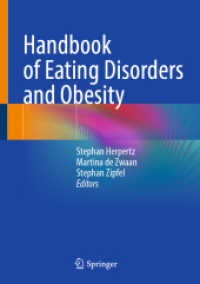内容説明
騎馬文化は日本列島でどのように受容され、展開したのか。馬具の形式を実年代も絡めて検討し、その生産と流通の構造を解明。さらに馬具と仏教工芸の関連を追究し、古墳時代社会における騎馬文化の歴史的意義を明らかにする。
目次
序章 古墳時代における馬具の受容と展開の解明をめざして
第1章 馬具研究の現状と課題
第2章 日本列島における馬具と騎馬文化の受容(日本列島における初期馬具の展開;鋳銅鈴付馬具編年の再検討 ほか)
第3章 金銅装馬具の国産過程とその歴史的背景(筑紫の君の誕生と磐井の上番―岩戸山石馬の馬装が語るもの;愛知県豊橋市大塚南古墳出土花形鏡板の年代と歴史的意義 ほか)
第4章 日本列島騎馬文化受容の諸段階と歴史的背景
著者等紹介
桃〓祐輔[モモサキユウスケ]
1967年、福岡県生まれ。筑波大学大学院歴史・人類学研究科文化人類学専攻を単位取得退学。東京国立博物館事務補佐員、筑波大学助手、福岡大学人文学部助教授、准教授を経て、福岡大学人文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
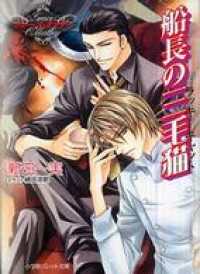
- 電子書籍
- パレット文庫 グレース・オマリー 船長…