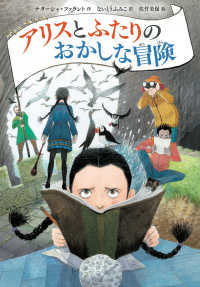内容説明
中国で生まれた漢字は、どのように東アジア世界に広がり受容されていったのか。文字文化伝播のありようを、政治や呪術、食文化など多様な切り口から描き出す。
目次
漢字文化と渡来人―倭国の漢字文化の担い手を探る
中国秦漢・魏晋南北朝期の出土文字資料と東アジア
古代韓国の木簡文化と日本木簡の起源
古代の「村」は生きている
文字がつなぐ古代東アジアの宗教と呪術
正倉院文書の世界―公文と帳簿
沈没船木簡からみる高麗の社会と文化
資料からみた日本列島と朝鮮半島のつながり
著者等紹介
小倉慈司[オグラシゲジ]
1967年東京都生まれ。1995年東京大学大学院人文社会系研究科単位修得退学。1996~2010年宮内庁書陵部編修課勤務。2010年~国立歴史民俗博物館准教授、総合研究大学院大学文化科学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りー
2
2014年に国立歴史民俗博物館で行われたフォーラム「古代東アジアの文字文化交流」が元になった本。日本で権威の象徴として呪符的に扱われていた文字は、5世紀、暦や生産管理などの技術として使われ始めるが、6世紀に入っても一部で使われる程度。最古の木簡が640年代。激変したのが660年の百済滅亡→670年代飛鳥浄御原宮期に木簡が激増=大規模な百済系の移民受け入れによる識字人口の増加。10年単位の物凄い早さで文字が広がり律令制国家が出来上がっていくスピードにびっくり!現代のデジタル化を思わせるけど、それ以上かも。2018/03/28