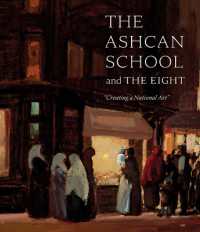内容説明
近世社会において寺院はどのような役割を果たしていたのか。地方寺院に保管された文書をもとに、彦根藩主井伊氏をはじめとした諸大名や住職など、寺社をめぐる人びとの多様な活動を詳細に検証。中近世移行期から幕末に至る地域社会の有り様を活写する。
目次
日本近世の宗教と社会をめぐる研究
中近世移行期の井伊谷龍潭寺
江戸時代の引佐地方・龍潭寺―旗本知行所支配の形成・展開と地方寺院
龍潭寺の「アジール」
由緒の井戸
遠州における朝廷権威の浸透と禅宗寺院―遠州井伊谷における「宗良親王墓」の整備をめぐって
近世における在地宗教者の歴史意識―二宮神社神主中井直恕の「礎石伝」とその意味
彦根藩井伊家の井伊谷参詣
遠州報国隊員山本金木の蔵書と歴史意識
遠州報国隊の歴史的位置
幕末維新期の龍潭寺とその後の引佐地域
江戸時代の地方寺院―「個人」成立の「場」として
著者等紹介
夏目琢史[ナツメタクミ]
1985年、静岡県浜松市生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了、博士(社会学)。日本学術振興会特別研究員、足立区立郷土博物館専門員などを経て、一橋大学附属図書館助教。公益財団法人徳川記念財団特別研究員、井の国歴史懇話会顧問(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 美しく燃えて