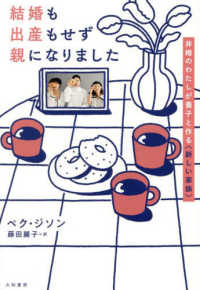出版社内容情報
人類の造りだした人工物の中で最も長期的に使われ続けている土器をめぐって、民族学と考古学の双方の視点からその意義を探る。
内容説明
新進の研究者を結集して過去・現在の研究成果を検証し、将来的展望をみすえつつ縄文研究の新地平を探る。
目次
1 総論(縄文時代のものづくりと組織)
2 道具製作の技術・工程(打製石斧の製作―駒木野遺跡出土の石器群を中心に;磨製石斧の製作;剥片剥離技法と石材供給 ほか)
3 工房と組織(土器製作のムラ―多摩ニュータウンNo.245・248遺跡を中心として;石器製作のムラ―一ノ坂遺跡;木器製作のムラ―鳥浜貝塚 ほか)
4 供給・交易システム(黒曜石鉱山;黒曜石の供給;黒曜石交易システム―関東・中部地方の様相 ほか)
著者等紹介
小杉康[コスギヤスシ]
1959年生。北海道大学大学院准教授
谷口康浩[タニグチヤスヒロ]
1960年生。國學院大學准教授
西田泰民[ニシダヤスタミ]
1959年生。新潟県立歴史博物館
水ノ江和同[ミズノエカズトモ]
1962年生。文化庁
矢野健一[ヤノケンイチ]
1959年生。立命館大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 鉄骨構造学 (新版)