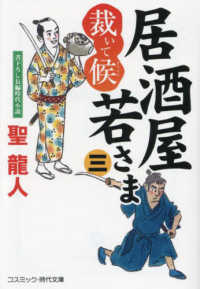内容説明
両宮山古墳。岡山県赤磐市に所在する五世紀後半築造の全長206mの巨大古墳。造山・作山古墳に続いて築かれた吉備の大首長墳で、備前の一大古墳群の中核をなす。この古墳をもって吉備の巨大古墳の時代は終りを告げる。大規模な二重濠や陪塚配置の検討を通じて古墳時代の吉備と畿内の関係を考えることができ、葺石・埴輪の欠落という特異な状況も注目される。「地域の個性をあらわすシンボル」「未来を見通す望遠鏡」である遺跡の過去・現在・未来を、最新の発掘データをふまえ、1冊に凝縮する。
目次
1 古墳の位置と環境
2 研究の歩み
3 調査の経過―測量と発掘
4 両宮山古墳の概要
5 両宮山古墳とその周辺
6 巨大古墳の総長
7 二重周濠の地方波及とその意義
8 陪塚の空間表示
9 まとめにかえて―両宮山古墳の諸問題
著者等紹介
宇垣匡雅[ウガキタダマサ]
1958年、岡山県生まれ。岡山大学法文学専攻科(史学専攻)修了。現在、赤磐市教育委員会社会教育課参事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
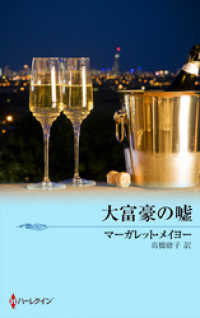
- 電子書籍
- 大富豪の嘘 ハーレクイン
-
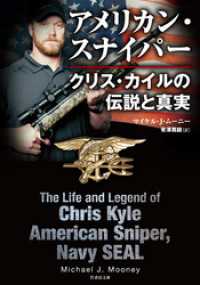
- 電子書籍
- アメリカン・スナイパー クリス・カイル…