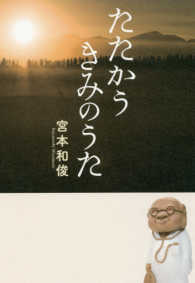内容説明
縄文土器はどのようにして作られたのか。多くの資料を詳細に観察することにより、全製作工程のメカニズムに迫る。
目次
土器を焼く技術の発明
土器作りの基本工程
原材料
土器の成形
器面の仕上げ(整形)
文様の施文
器面の仕上げ(研磨・削り)
乾燥
焼成
縄文土器の文様
縄文土器はいつ作られたのか
縄文土器は男が作ったものなのか、女が作ったものなのか
著者等紹介
可児通宏[カニミチヒロ]
1943年岡山県生まれ。1967年国学院大学文学部史学科卒業。1967年多摩ニュータウン遺跡調査会調査員。1973年東京都教育委員会(学芸員)。1980年(財)東京都埋蔵文化財センターへ出向。2003年東京都教育委員会を定年退職。東京都教育委員会嘱託員、国学院大学講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ミルチ
6
筆者は大学生の頃から縄文土器を研究されていて、考古学の視点や各論文、世界各地の土器作りの民族誌、実際に作ってみての考察を本にされていた。土器を作る意味、土作りの難しさなど形成に至るまでがいかに高度な技術が必要かがよく分かります。土器作りは女性仕事といわれるが、高さ1m、重さ50kgの大型土器は力仕事なので男性が作ったのではと言う筆者の意見には納得。まあ縄文時代なのでみんなで楽しく作ってたんだろうな…。2020/09/16
pepe
0
多彩な文様がある縄文土器。作る方からみても色々奥が深い。粘土採掘した跡もみつかっているのは面白い。著者は、西アジアでいわれている粘土をパッチワークのようにつなげてつくるSSC法が縄文土器にもあったとする点には懐疑的。土器が作られる時期も、夏に獲物がとれなくなる端境期に男性が従事したという見解も面白い。2023/03/11