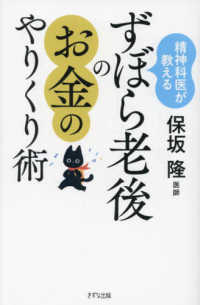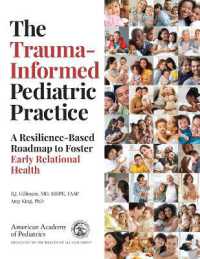内容説明
ひとつの由来から派生し日本列島内で連綿と変化してきたとされる縄紋土器群。それこそが日本列島に固有の「縄紋文化」が存在したことの大前提となっている。だが、その大前提に問題はないのか?著者は、山内清男の説の矛盾点を明らかにすることから始め、50年余の研究史を検証するなかで、縄紋土器研究に新たな地平を切り拓いている。
目次
序説 20世紀末縄紋土器研究の評論からの問題提起
前篇 縄紋土器研究の新旧(山内型式論の概略と受容;山内型式論の体系性;山内型式論の再検討;今日的土器型式論)
後篇 縄紋土器研究の新展開(一系統的縄紋土器起源論の教訓;泉福寺洞穴の豆粒紋の構造;一帯型隆起線紋土器の比較;一帯型隆起線紋土器の由来 ほか)
付篇 石剣考
著者等紹介
大塚達朗[オオツカタツロウ]
1952年、埼玉県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。現在、南山大学人文学部助教授。主要著作論文に『寿能泥炭層遺跡発掘調査報告書―人工遺物・総括編―』埼玉県教育委員会、1984年(共著)。『縄紋土器大観 1』小学館、1989年(共著)。『図解・日本の人類遺跡』東京大学出版会、1992年(共著)。「橿原式紋様論」『東京大学文学部考古学研究室研究紀要』第13号、1995年
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。