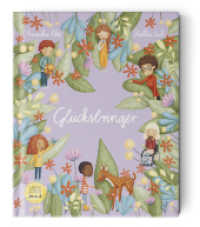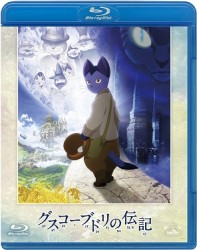内容説明
現実が現実であるのは人々が暗黙の裡に信じている了解事項の集合のせいであって、…すべてを逆手にとって現実を変える。日本に滞在中に千葉県の九十九里浜で書かれた、現実と幻想が交錯するマジック・リアリズム。
著者等紹介
カーター,アンジェラ[カーター,アンジェラ] [Carter,Angela]
1940年、イギリスのサセックス州イーストボーンに生まれる。ブリストル大学で英文学を学び、1966年に『シャドウ・ダンス』で作家活動を始めた。第3作の『さまざまに感じる』がサマセット・モーム賞を受賞。その賞金を手に1969年に来日し、2度の一時帰国をはさんで1972年まで日本に滞在した。執筆活動は、小説をはじめとして戯曲や脚本、詩、評論やエッセイ、子供向けの本など幅広い。おとぎ話の翻訳も手がけ、執筆活動のかたわら、カーターは英米の大学でも教えた。1992年肺癌のために死去
榎本義子[エノモトヨシコ]
1942年神奈川県生まれ。早稲田大学文学部卒業。ニューヨーク市立ブルックリン・カレッジ修士課程修了。フェリス女学院大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
![建築土木教科書 2級土木施工管理技士[第一次検定]出るとこだけ!](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1735800.jpg)
- 電子書籍
- 建築土木教科書 2級土木施工管理技士[…