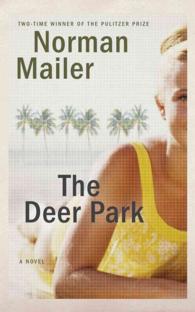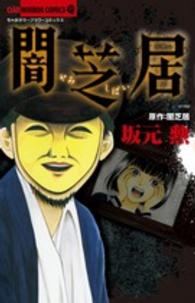目次
第1章 パイプオルガンの起源と変遷(オルガンの起源をたずねて;3種類のオルガン;ルネッサンス時代のオルガン;バロック時代のオルガン)
第2章 バッハの黄金期から現代まで(バッハが使用したオルガンについて;18世紀後半のオルガンの傾向;19世紀のロマンティックオルガン;20世紀―現代のオルガン)
第3章 オルガンの演奏台(コンソール)の諸装置について(演奏台―手鍵盤と足鍵盤の諸形式;各種ストップとその音色、音量、音高;演奏補助装置のいろいろ)
第4章 オルガン演奏技法入門(オルガン演奏の歴史的性質と特色;アクションの機能と演奏技法;鍵盤について;ストップのスケール)
第5章 オルガニスト(作品演奏;伴奏と合奏;即興演奏;演奏楽派について)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
paluko
12
現在の住処に引っ越してから、幸いにも月に一度(最近では二度)パイプオルガンの演奏に接することができるようになりました。ひと口にパイプオルガンと言っても、楽器(会場)毎に素人耳にもわかるくらい音が違います。正直、細かい用語とかはよく理解できていませんが本書を読むことで楽器の歴史(昔は拳で叩いて演奏していた!とか)、音階の変遷、求められる音色・表現の変化など、オルガニストはピアニストよりいっそう楽器や様式について深い理解が求められるのだなと実感しました。コックピットのようなコンソール(演奏台)の写真は圧巻。2023/09/14
なおた
0
『パイプオルガンの本』というタイトルだけでは、どんな本であるか分からなかったのですが、パイプオルガン発展史、手鍵盤、足鍵盤、ストップ、etc...、アクションとタッチ、アーティキュレーション、ストップ、技法、etc...、演奏について、etc...と、そんな内容が書かれた本でした。わたしの念頭にあったイメージとは異なる1冊でした。2024/03/02
-
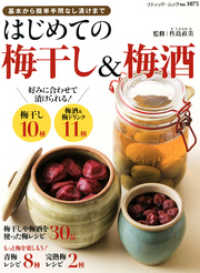
- 電子書籍
- はじめての梅干し&梅酒 ブティック・ム…