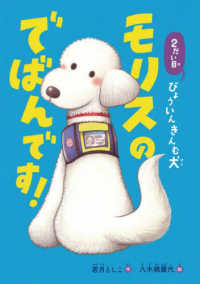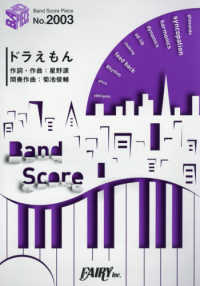内容説明
数値目標やスローガンでは問題は解決しない。いま日本は何を為すべきか?
目次
COP21への長い道のり
COP21に向けての争点
COP21はどう進んだのか
COP21はなぜ成功したのか
パリ協定で何が決まったのか
パリ協定をどう評価するか
世界は脱炭素化に向かうのか
26%目標達成のカギは原子力
長期戦略と長期削減目標
地球温暖化防止に取り組むならば原子力から目をそらすな
長期戦略の中核は革新的技術開発
炭素価格論について考える
著者等紹介
有馬純[アリマジュン]
1959年生まれ。1982年、東京大学経済学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)入省。2002年に国際エネルギー機関(IEA)国別審査課長、2006年に資源エネルギー庁国際課長、2007年に国際交渉担当参事官、2008年に大臣官房地球環境担当審議官、2011年に日本貿易振興機構(ジェトロ)ロンドン事務所長兼経済産業省地球環境問題特別調査員を経て、2015年8月より東京大学公共政策大学院教授、現職。21世紀政策研究所研究主幹、アジア太平洋研究所上席研究員、国際環境経済研究所主席研究員も兼務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yuno
3
長らく気候変動交渉を担当した元経産官僚の本。前半は当事者の視点から書かれたパリ協定に至る経緯、各目標数値の考え方、協定の条文の解釈など、後半は環境・エネルギーに関する政策提言。先進国のみが法的義務を負い、欧米に比して高い削減目標を掲げさせられた京都議定書が日本にいかに不利だったか、その点を改善したパリ協定がいかに画期的であるか、等が書かれている。COP21に提出した26%削減目標がいかにハードルの高いものかが力説されているが、それがCOP26で46%になってしまったときの著者の失望は想像に難くない。2022/11/06
摩天楼
2
昨年のCOP23参加前に前半を読み、後半は放置されていたが、やっと読み終わった。著者が経済産業省に長く勤めておられた方なので、地球温暖化対策・政策について、経済的な観点から知見を得られる。経済面を考慮すると中々厳しいものがあるが、これが現実なのである。楽観的に「野心的な」目標を唱え、政府に文句を言い続けるのではなく、「国富」を考えざるを得ない国の視点を取り入れることは、地球温暖化対策に真に向き合う上で必要なのであろう。 (ところで、本書後半部分には何点か誤植があったが、よほど急いで作られたのだろうか)2018/04/12
香菜子(かなこ・Kanako)
0
精神論抜きで人類の未来のために地球温暖化対策は不可欠だとわかった。2017/03/31