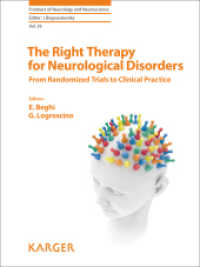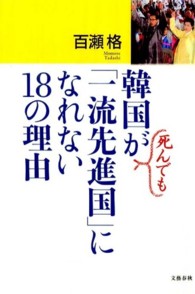内容説明
過ぎし昭和が歌謡曲に乗って甦る!もうひとつの昭和文化史。
目次
第1章 昭和は佐藤千夜子で始まった―大正末年~昭和十一年(ラジオとレコードが流行歌を変える;西条八十・中山晋平のコンビ誕生 ほか)
第2章 戦時下にも歌は流れた―昭和十二年~二十年(日中戦争の戦火広がる;淡谷のり子、ついにブルースを歌う ほか)
第3章 焼け跡によみがえった歌声―昭和二十年~三十年(“赤いリンゴに唇寄せて…”;人気を独占した流行歌“三人男” ほか)
第4章 歌は時代に寄り添いながら…―昭和三十年~四十五年(「もはや“戦後”ではない」時代の到来;“低音ブーム”と美空ひばり塩酸事件 ほか)
第5章 歌い継がれていく昭和の名曲―昭和四十六年~昭和の終焉まで(七〇年代歌謡界を席巻した阿久悠;モンスターを生み出した背景 ほか)
著者等紹介
塩澤実信[シオザワミノブ]
長野県生まれ。日本ペンクラブ、日本出版学会会員。東京大学新聞研究所講師、日本ジャーナリスト専門学校講師などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MASA123
10
昭和の流行歌の歴史をたどる本。久石譲さんが「人はみな青春時代の歌が好きだ」と語っているが、本書の終盤に、やっと自分の青春時代の歌がでてくるので、本全体の記述にあまり興味がもてなかった。 ユーミンや陽水が登場する頃の話なら、もっと興味がもてたのですが・・・ 昭和元年はわずか7日間で昭和2年から3年にかけて、外資の蓄音機会社3社、ビクターとコロムビア(米)、ポリドール(独)が設立。レコード会社専属の作詞家、作曲家、歌手による流行歌が作られていった。蓄音機の周波数が50~6000ヘルツに改善され音質向上。2023/09/13
メルセ・ひすい
2
15-56 昭和は遠くなりにけり 平成生まれが大卒っっ ★やはりビートルズのインパクトが凄い。 昭和は佐藤千夜子で始まり、そして戦時下にも歌は流れた…。焼け跡によみがった歌声、歌い継がれていく昭和の名曲などを綴った、過ぎし昭和が歌謡曲に乗ってよみがえる、もうひとつの昭和文化史。 2011/09/05
kenkou51
0
昭和の戦前、戦中、戦後の歌謡曲の歴史が知れて面白かった。読む前は5章以外はほぼ知らない曲や人物ばかり。ただ、本文中に登場していた曲や人物は検索すると出てきて、こういう歌なのかと実際に聴くことが出来るのはありがたい。結構裏話的なことも載っていて美空ひばりと笠置シズ子、淡谷のり子の関係など興味深い。2017/11/09
takao
0
ふむ2025/03/02
ぞだぐぁ
0
ルミナスウィッチーズの予習のため読んだ。戦前から平成直前までの昭和の流行歌について歌手についての話や逸話についてまで書かれている。著者と歌手が並んで写っている写真が結構入っている所に、人となりについての記述の信ぴょう性が増す。強い。2019/11/25
-
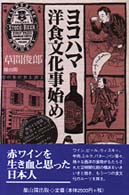
- 和書
- ヨコハマ洋食文化事始め