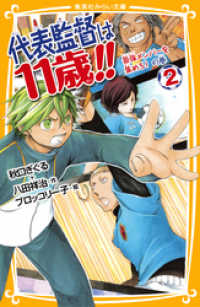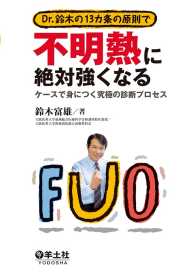内容説明
松吉の家にびんぼう神が住みつき、家はみるみる貧しくなっていく。ところが松吉は悲しむどころか、なんと神棚を作ってびんぼう神を拝みはじめた―。
著者等紹介
高草洋子[タカクサヨウコ]
富山県生まれの東京育ち、現在は兵庫県宝塚市に住む2児の母。主業は主婦、副業は夫の事業の手伝い。日本画を上野泰郎氏に、水墨画を佐藤紫雲氏に師事する。個展「光の詞」を1996年6月に大阪市のマサゴ画廊、’97年3月に東京のアトリエ「ピュア」にて開催。見えない世界を絵や文章にすることが大好き。今の夢は畑や自然の中で木や草花、虫、自然のすべてと語り合えるような生活をすること
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
☆よいこ
80
貧しい農村の松吉の家にびんぼう神が住み着いた。びんぼう神は、結婚したばかりの松吉とおとよが貧しさの中で喧嘩するのを楽しみにしていたが、ふたりはいつも仲睦まじく息子のうし松が生まれて幸せそうにしていた。《なんでわしは、神様って呼ばれるんじゃろう?》びんぼう神をありがたがる松吉を見て、びんぼう神は自分の存在意義に悩む。びんぼう神は福の神からもらったもみ殻を松吉にやる。大飢饉が来て、松吉の稲だけが実るが松吉はそれを村人に配る。うし松が病で死にかけ、びんぼう神はうし松を救いたいと奔走する▽良本2023/08/01
けんとまん1007
41
”びんぼう”とは一体何だろう?頭では知っているが、いざとなるとそうは思えない。どうしても、モノが先にたつ。もちろん、人は生きていくためには、食べ物が必要なのは間違いの無いところ。ただ、どこまで、食べ物も含めた”モノ”に囚われてしまうのかということだろう。そして、人は一人では生きていけないということ、世代としてつながるということも。一方、貧乏神様自身の考え方の変化も、とても深いものがある。他の神様も含め、それぞれの担うべき役割と、それを尊重することが大切だということ。難しいことだが、少しでもできればと思う。2015/01/25
ゆきち
39
びんぼう神様は、松吉の家に居座っていることに居心地の悪さを感じていた。びんぼう神様に松吉たち家族は不平不満を言わないからだ。びんぼう神様は、考える。『じぶんの存在意義とはなんだろう。人を不幸にするじぶんが神様と呼ばれるのはなぜだろう』…日本昔話で少し知っていた話よりも内容の深い物語は、とても感動的で考えさせられた。教えてくれた読友さんに感謝したい。2014/12/07
ベーグルグル (感想、本登録のみ)
38
見かける度に何度も手に取って読んでおり、毎回ハッとさせられる。『足るを知る』大切な事を教えてくれる本。2014/11/12
夜長月🌙
35
読み友さん3人のおすすめ本。びんぼう神も人の子?(人の子ではないか!)感謝されれば情も湧く。びんぼう神は松吉親子の無心の信心に目覚め成長していく。思いやり寄り添うことでほんの少しずつ変わっていくものがあるはず。私利私欲で動いているように思える人たちも大きな宇宙の一片でしかない。2014/11/22