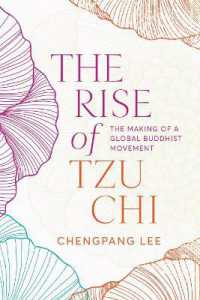内容説明
『五輪書』は、人生のさまざまな局面に待ち受けるさまざまな敵との戦いに勝つためのノウハウを記した「ビジネス書」であり、乱世を生き抜くヒントを与えてくれる「人生の指南書」でもある。
目次
地之巻(兵法の道ということ;兵法の道を大工にたとえること ほか)
水之巻(兵法の心の持ちようのこと;兵法の身なりのこと ほか)
火之巻(場の次第ということ;三つの先ということ ほか)
風之巻(他流派が大きな太刀を持つこと;他流派の「強みの太刀」ということ ほか)
空之巻
著者等紹介
宮本武蔵[ミヤモトムサシ]
1584‐1645年。江戸初期の兵法家、剣術家、画家。天正12年兵庫あるいは岡山生まれ。名は玄信。号は二天。新免無二斎武仁の子。若年から剣の修業のため諸国を巡り、二刀流を編み出し、二天一流と称した。巌流佐々木小次郎との決闘のほか、生涯六十余回の勝負に一度も敗れなかったと伝えられている。晩年は熊本藩主細川忠利に仕えた。水墨画にも長じた
城島明彦[ジョウジマアキヒコ]
昭和21年三重県に生まれる。早稲田大学政経学部卒。東宝、ソニー勤務を経て、「けさらんぱさらん」で第62回オール讀物新人賞を受賞し、作家となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ykmmr (^_^)
37
『読書ノート』記念すべき、100冊めは…『五輪書』であった。誰もが知っている剣豪…武蔵。彼の実績を知ると感想を書くのも烏滸がましいが、まず、他の自伝書にも意外に言える事だが、基本、『秀才型』かつ、やり方は至って『シンプル』。自分の流派は断固として、『軸』その中に、多数の他流派や世の中の世情を取り入れて行く。自分の『流派』のこだわりと、他流派に対しての着眼点がしっかりしていて、その捉え方がまさに職人。そして、常に心身安定にて、自己研鑽を怠らない。こちらがまさに秀才型。2021/08/21
Yuma Usui
15
五輪書の現代語訳。現代語訳者の城島明彦氏の葉隠と五輪書との関係についての考察は一理あると感じた。特に団体競技や個人競技などスポーツを行う人に対して有益な内容と思う。現代語訳だとしても一度の読書では内容を掴めない箇所が多くあり、何度か再読して武蔵の考えを消化してみたいと感じた。2018/08/18
645TJC
15
戦いに勝つための原則は?①戦いの目的をはっきり意識する。目的が手段を最適化する。目的が曖昧では行動がブレ、成果もブレる②常に実戦を想定して稽古する。平時から戦時を意識していなければ、いざという時に対処できない③学ぶ順序。大きいところから小さいところ、浅い所から深いところへ④相手の拍子を崩す。相手のタイミングに合わせず、動揺させ冷静さを失わせる⑤心眼を中心に。自分の軸をぶらさず、体が変幻自在に即応できる心理状態を保つ⑥目付け(観の目・見の目)。遠いものを近くへ、近いものを遠くへ。全体像を把握して適切に対処。2016/06/26
森林・米・畑
12
読みやすいシリーズ。五輪書読んでから吉川英治の宮本武蔵へ進もうと思った。今、剣術は必要ないが、この考えは話術にも置き換えることが出来るのではないか?剣術は人を打つ(殺す)為のものであるが、現代は議論で戦う。剣術は人を殺す為だけの武器であるが、話術は人を叩くだけではない。励ましたり誉めたり慰めたり喜び合ったり出来る人間の武器であると思う。五輪書の考えを応用して、今風に活用できる。2016/07/17
いなぎ
9
企画の目論見通り「いつか読んでみたかった」ので、まずはここから手を出してみた。大変読みやすくしてあり、置いていかれるような感覚もなく無事読了▼武蔵は徹底して『実戦での勝利』を追い求めており、その実現の手段としての兵法について解説している。「智力」を重視しており、「深く考えてもらいたい」「研究してもらいたい」と繰り返している。実戦の人だったのだろうと思わせる▼現代人にとって参考になりそうな話もたくさんあるし、火之巻の「ひしぐ」とか「まぶるる」、「うろめかす」といった言葉の響きをただ面白がるだけでも楽しめる2023/02/19