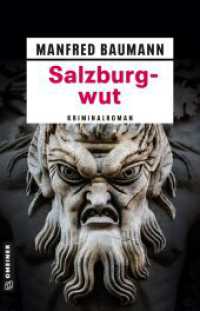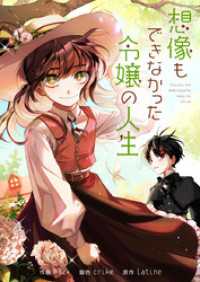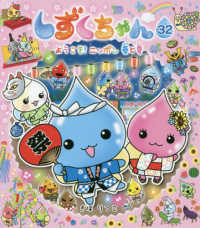内容説明
この一冊で文化人類学がわかる!文化人類学の学説史を丹念に読み解き、方法論の発展について論究した。
目次
文化人類学を学ぶために
文化人類学とはどのような学問か?
進化主義と伝播主義
近代人類学の夜明け1 マリノフスキーをめぐって
近代人類学の夜明け2 ラドクリフ=ブラウン
アメリカ文化人類学の出発:ボアズとその弟子たち
構造主義以前の文化人類学
構造主義の系譜
構造主義と文化相対主義
構造主義以後の文化人類学
アメリカ「帝国」完成期の文化人類学
教育人類学と心理人類学
教育人類学の理論的問題点
人種主義(racism)と人権(human rights)
日本人類学の道程
今後の文化人類学
著者等紹介
原尻英樹[ハラジリヒデキ]
立命館大学産業社会学部教授(エスニシティ論担当)。1958年福岡県大牟田市生まれ。九州大学教育学部卒業。同大学大学院教育学研究科博士後期課程中退。ハワイ大学政治学博士(Ph.D.)、九州大学教育学博士(教育人類学)。放送大学教養学部文化人類学助教授等を経て、現職。専門分野:文化人類学、教育人類学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲニウスロキ皇子
1
日本人学者が書いた文化人類学史は少ない。この他には、竹沢尚一郎の『人類学的思考の歴史』くらいだろうか。竹沢は、人類学者の群像劇の記述に終始しており、肝心な現在の「学」の歴史的な流れを曖昧なままである。それに対して本書は、例えば機能主義ならばその考えが生まれた社会的な背景に即した「学の流れ」の記述を心がけているように思える。著者の思想を色濃く反映している点もあるが(人類学の流れを構造主義以前と以降に大まかに分けている等)、人類学が現在に至るまでどのような歩みを進めてきたのかを考えるには有益である。2011/05/05
ユウキ
0
文化人類学の学説の大まかな流れを記した概説書・入門書は実は結構ある。だがどれもページ数の都合だろうか、わかりやすくは書いてあってもどうしてこのタイミングでこういう学説が出てくるのかという説明は殆ど無いか、腑に落ちないことが多かった。学ぶ側からすれば隔靴掻痒の感があったが、本書はそういう要望に応えてくれる労作。この本で一番驚いたのは、今日では名前を聞くことが非常に少ないドイツ哲学者ディルタイが英米の初期の人類学に重大かつ広範な影響を与えていたことだ。全く知らなかった。ディルタイの著作は一度はあたっておきたい2018/03/01