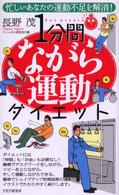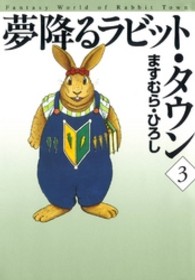- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学一般
内容説明
「どうして図書館は行政内で評価されないのか」「市民に図書館を届けるにはどうすればいいのか」『図書館長論の試み』の著者が発信する公共図書館員へ向けての新たなメッセージ!4人の図書館長経験者も「行政の中の図書館」における職員のあるべき姿を描出。
目次
1部(市民にさらに支持される図書館員になるには;庁内でさらに理解される図書館員になるには;まちの活性化にさらに寄与できる図書館員になるには)
2部(図書館の仕事の価値を知ってもらうことは難しい?(千邑淳子)
フィンランドの図書館司書に教えられたこと(津田惠子)
「流動する図書館員」はどこにたどり着いたか(永見弘美)
図書館ってやっぱり人だよね(村山秀幸))
著者等紹介
内野安彦[ウチノヤスヒコ]
1956(昭和31)年茨城県鹿嶋市生まれ。鹿嶋市、塩尻市に33年間奉職。両市で図書館長を務め、定年を待たず早期退職しフリーランスに。現在、古書店「雀羅書房」店主(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ででんでん
45
他の部署との連携。自分の街を知る。2022/10/27
kum
34
図書館が行政の中で存在感や有用性を示せなければ、当然人も予算も削られる。旧来のあり方から一歩踏み出し、図書館に関わる職員の意識も変わっていかなくてはいけないということがよくわかった。現場の声として、指定管理館館長である永見氏の話も興味深い。自治体と指定管理は本来対立関係ではなく、目指す姿や使命を共有していい図書館を一緒に作っていくべきパートナー。けれど立場の違いから、そこに複雑な軋轢が生まれることも容易に想像できる。図書館員の多くが非正規雇用である問題についてもあらためて考えさせられた。2022/04/11
鳩羽
5
図書館の評価者を市民、同僚(役所の行政職)、地域の三つに分けて、これらの評価者、協力者、サービス提供者といった人々のニーズを汲み取れているのか、そして、サービスの存在を伝えられているのかを、広報やアンケートといった身近なものから考えていく。図書館関係者は、人間もサービスも専門的な方向を向きがちというか、同職ギルドみたいな意識が強い気がする。特定の利用者の声を拾いがちになるのは、司書が望む要望を拾うマッチポンプになっていないか、冷静に判断しなければならないと思った。まちの強み弱みの話が興味深かった。2022/02/08
SHO
3
今度図書館に行ったら、地域資料に注目してみようと思いました。2022/07/07
Go Extreme
3
市民にさらに支持される図書館員になる: 図書館の広報 アンケート結果 ローカルなテーマの展示 各文化サービスの居場所 庁内でさらに理解される図書館員になる: 議会議員定数 製造・販売している嗜好品 まちの強み・弱み まちの活性化にさらに寄与できる図書館員になる: 知的財産・地域ブランド情報 図書館ならではの情報提供 市民の活動に寄り添う 図書館の仕事の価値を知ってもらうことは難しい? フィンランドの図書館司書に教えられたこと 「流動する図書館員」はどこにたどり着いたか 図書館ってやっぱり人だよね2022/05/31
-

- 電子書籍
- 太陽の烙印 -忍者バトルロイヤル 巨悪…