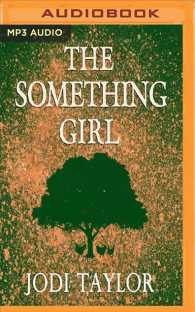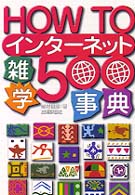目次
フクロウの飛翔
ボローニャ時代
困難な出発
ローマ、ナポリそしてミラノ
オペラ作曲家という哀れな職業
「ドッズィネッティ」対ドニゼッティ
個性の認識
『愛の妙薬』とドニゼッティの新しい喜劇のキャラクター
フェッラーラの宮廷で、バイロン、ゲーテ、ユゴーと共に
ナポリの王立音楽院の教授とパリのイタリア歌劇場付き作曲家〔ほか〕
著者等紹介
バルブラン,グリエルモ[バルブラン,グリエルモ][Barblan,Guglielmo]
音楽学者。1906年5月27日、シエナに生まれ、1978年3月23日、ミラノで亡くなる。フォリーノおよびベッカーにチェロを、リウッツィおよびサンドベルジェルに音楽学を学ぶ。1929年にローマにてチェロの、また1932年にボルツァーノにて作曲のディプロマを取得、法学も修める。1950年まで演奏家としての活動の傍ら、ローマの『ボルツァーノ地方紙La Provincia di Bolzano』の音楽評論を担当する。1932年からボルツァーノの国立音楽院で音楽史およびチェロを教え、1949年からミラノの国立音楽院で図書館長を勤め、1965年からは同音楽院の音楽学の教授となる。その傍ら、ミラノ大学の音楽史の講師、1964年から1968年までイタリア音楽学協会理事長、1964年からローマのサンタ・チェチーリア音楽院の教授、1965年からアッカデミーア・キジアーナ音楽院の副理事などを兼任。イタリア今世紀屈指の音楽学者として知られている
ザノリーニ,ブルーノ[ザノリーニ,ブルーノ][Zanolini,Bruno]
作曲家、音楽学者。1945年8月22日、ミラノに生まれる。1970年、ミラノの国立音楽院のピアノ科を修了、1972年、ミラノ大学の文学科卒業。さらに、ディオニーズィおよびベッティネッリに師事し作曲を学び、1973年に上記音楽院の作曲科を卒業。現在ミラノの国立音楽院の作曲家教授。1974年、『505 Cinquecentocinque per cl.,vcl.e vibr.』の作曲を手はじめに、『トッカータToccata per org.,tr.e trb.』ほか、器楽曲、室内楽曲、合唱曲などを中心に、活発な作曲活動を展開し、さまざまな賞を獲得する一方、著作でも活躍している
高橋和恵[タカハシカズエ]
ソプラノ、イタリア音楽研究家。洗足学園大学声楽科卒業。(財)日本オペラ振興会研究生修了後、藤原歌劇団入団。1987年、イタリア文化会館語学研修員として渡伊。フィレンツェで研修後、ミラノに移り声楽を学ぶ傍ら、コンサート歌手として活躍。1993年帰国。1995年、文化庁派遣演奏家としてふたたび渡伊。イタリア音楽、とくに18、19世紀を中心に、演奏・研究活動をとおしてその普及に努める。(財)日本オペラ振興会オペラ歌手育成部講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。