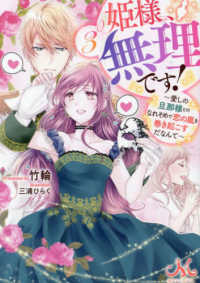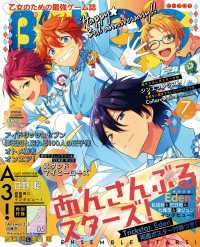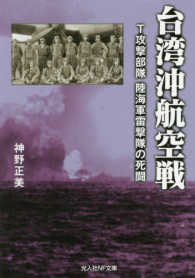内容説明
大阪の八尾は江戸時代、河内木綿の里として知られた。しかし、開国と工業化の大波の中で伝統的な木綿産業は衰退し、代わって近代的な木綿産業が大阪経済を支えるようになる。そして今、伝統に根差した木綿リサイクルが蘇ろうとしている。木綿を素材として人々の暮らしと経済システムの変化を描く!!
目次
河内木綿との遭遇
麻から木綿へ
江戸時代の木綿リサイクル
商都大阪の繁栄
海外木綿製品の流入
「鉄と石炭」の革命
木綿リサイクルの崩壊
商都大阪のゆらぎ
大阪紡績業の勃興
河内の人々の模索
綿業世界一の栄光
木綿から合成繊維へ
高度経済成長による工業化
河内木綿の復活
公害と地球温暖化
木綿リサイクルの復活
「生態系サービス」としての木綿
著者等紹介
前田啓一[マエダケイイチ]
1955年兵庫県生まれ。出版社勤務、在シカゴ日本国総領事館専門調査員などを経てフリーライターとなり、経済分野を中心に執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sakie
17
木綿は温暖な地で江戸時代に栽培が盛んになった。しかし開国と共に輸入品に押される。明治16年、渋沢栄一が紡績会社設立。国産の綿でも試行錯誤したが、輸入品の綿糸のほうが良質だったため、明治19年以降中国産、インド産で操業。大正5年には河内の木綿栽培は壊滅した由。合成繊維が現れるまでもなかったようだ。なお、私の興味を引いた「リサイクル」とは、以前においては布地をボロボロになるまで使い倒した後、肥やしとして畑に鋤き込むことであり、現代においては"自然に優しい"に同義と扱われているあたり、不満と言わざるを得ない。2022/07/13
わ!
6
ライターさんが書いた本なのですが、わかりやすくまとまっている本でした。情報の先頭には「◯◯によると」といった引用文献の明示がなされていますし、大阪の経済史も含んで丁寧に書かれています(大阪経済史などは、木綿に関連する内容に特化していますが)。「河内木綿」とは聞くものの、その実物をほとんど見たことがない割に、文献では大阪でを代表する産物として書かれていて、どのような趨勢を経て、現在の状態に至ったのかを知りたかったため、とても嬉しい内容の本でした。八尾市が木綿に対して、こんなに熱心なことは初めて知りました。2025/03/26