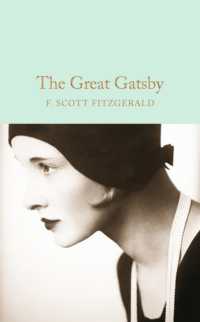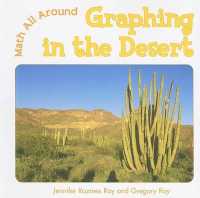内容説明
1871年冬、琉球宮古島の船が漂流の末、台湾南部の海で座礁した。船に乗っていた66人は台湾に上陸し、やがて大耳人と呼ばれる人々に出会う。村へ案内され、食べ物と宿を提供されたが、その夜の出来事に驚愕して、こっそりと村を逃げ出す。その無礼を憤った大耳人は彼らを追いかけ…。1874年の台湾出兵(牡丹社事件)の発端となった事件を描いた作品。
著者等紹介
巴代[パタイ]
1962年台東県卑南郷泰安村タマラカウ(大巴六九)部落生まれ。プユマ族。本名は林二郎。卑南国民中学卒業後、中正預校、陸軍官校で学び、職業軍人になる。教官を務めたのち、2006年退役。2005年台南大学台湾文化研究所修士。2002年「薑路」で原住民報導文学賞を、2008年『笛鸛』で台湾文学賞を受賞。台湾原住民族文学ペンクラブ会長
魚住悦子[ウオズミエツコ]
1954年兵庫県相生市生まれ。大阪大学大学院文学研究科修士課程修了。文学修士。天理大学・武庫川女子大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かやは
7
1871年に起こった、台湾の原住民による遭難した宮古島の人々を殺害した事件を基にした小説。異なる文化との出会いは、現代のような前提が存在しないことを改めて考えさせられた。人間の「恐れ」に対する対応は動物のように単純ではない。人間には想像力がある。それは物事を解決するための能力ではあるが、ずっと悪い方向に転がしてしまうものでもある。一人一人は冷静であっても、群衆となったときはその場の感情に飲み込まれてしまう。側から見てたら愚かに思える選択も、当事者になったら自分だって冷静には振る舞えないだろうなと思った。2021/03/23
100名山
3
1871年冬に琉球王国宮古島の船が台湾南部で座礁して3名がなくなるものの66名が上陸を果たしますが、意思の疎通が出来ずに12名を残し先住民に惨殺された史実に基づいた小説です。これを理由に日本は台湾に侵略し、琉球処分へと歴史は流れて行きました。先住民の血を受け継ぐ著者が聞き取りや資料から書き起こしています。先住民と琉球人の目線が書き分けられ同時進行します。セデックバレをイメージし今は宮古島と陸続きになった下地島のきれいな海を思い浮かべながら読み進めました。先住民の男が歌や鼻笛で女の気を引く話が効果的でした。2019/03/19
-
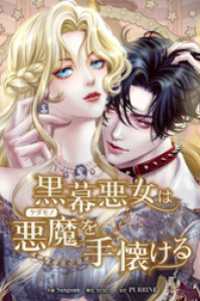
- 電子書籍
- 黒幕悪女は悪魔を手懐ける【タテヨミ】第…
-
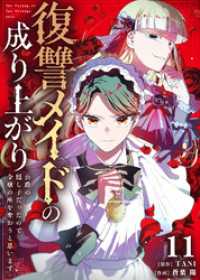
- 電子書籍
- 復讐メイドの成り上がり~公爵の隠し子だ…