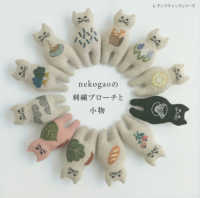内容説明
遠く120kmも離れた糸魚川産のヒスイ大珠が五箇山に出土した謎を探るうち、縄文時代の「交易」は、定住生活から生まれ、その生活を可能にしたのは土器の発明であった…と考えるようになった著者。縄文土器の製法や装飾性など、土器模作を通して生まれたユニークな仮説から縄文人の知恵や暮らしを考察する。
目次
1 五箇山の歴史をさかのぼる(五箇山の縄文遺物;ヒスイの大珠 ほか)
2 なぜ五箇山にヒスイが(縄文時代の住居;縄文時代中期の建物 ほか)
3 世界の中の縄文時代(世界最古の土器;縄文の時代区分 ほか)
4 縄文時代の土器(草創期の土器から考える;早期の土器から考える ほか)
5 縄文晩期から弥生・奈良・平安へ(五箇山の縄文時代以後)
著者等紹介
酒井則行[サカイノリユキ]
1946年(昭和21年)12月3日富山県東礪波郡城端町で生まれる。幼児期五箇山で暮らす。城端町立城端小学校に入学。大阪府北河内郡門真町立門真小学校卒業。真門町立門真中学校入学・卒業。大阪府立寝屋川高等学校入学・卒業。山梨県都留市立都留文科大学国文科入学・卒業。門真市立4小学校に勤務・退職。2009年3月「縄文土器模造品66考古展」を開く。現在、「縄文土器再生」をテーマに実用的模造品制作(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 単位の発達の心理学的研究