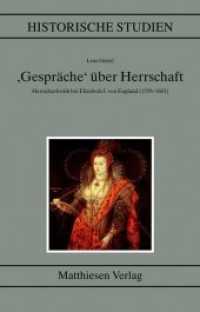内容説明
占領下の厳しい冷戦のなか、ドイツを分断して1949年に誕生した東ドイツ。わずか40年の短命国家の外交の任務はつねに、国の存立の保障の確保にあった。たえず国家の「存在の不安」に悩まされていたからである。本書を通じて、ベルリン問題の本質がわかるし、ハンガリー動乱、ベルリンの壁の建設、「プラハの春」、ブラント政権の「新東方政策」、度重なるポーランド騒擾など、現代世界史の真相があらためて生々しく迫ってくる。
目次
第1部 国際的な承認以前の東ドイツ外交(1945/49‐1972)(構造と人物:五〇年代における東ドイツの外交機関;建国以前の外交の端緒;ソビエト指揮監督下の外交とドイツ政策(1949‐1955)
問題は相変わらず、存在感は増大する(1955‐1961)
持続と変化の間で:六〇年代における外交機関
新たな挑戦と変わらぬ目標との間で:六〇年代における東ドイツ外交(1961‐1969)
モスクワとボンとのはざまで:東ドイツと「新東方政策」(1969‐1972))
第2部 「基本条約」後の東ドイツ外交(1973‐1989)(七〇年代/八〇年代における東ドイツの外交機関;順応と自立の間で:ホーネッカー時代初期の東ドイツ交外(1973‐1981)
飛翔と転落:八〇年代における東ドイツ外交)
著者等紹介
ヴェントカー,ヘルマン[ヴェントカー,ヘルマン][Wentker,Hermann]
1959年ボンの生まれで、現在ライプツィヒ大学の近・現代史の教授であるとともに、「現代史研究所」のベルリン支部の所長を務めている。主にDDRの外交やドイツ・ドイツ間関係に関する、またソビエト衛星圏諸国に関する研究をしている
岡田浩平[オカダコウヘイ]
1937年生まれ。1967年早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。1969年早稲田大学専任講師、1972年助教授、1978年教授。2008年停年退職。現在早稲田大学名誉教授。専攻は1933~1945年の間のドイツ亡命文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
富士乙
Fumihiko Kimura