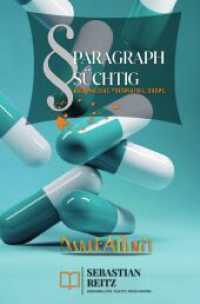内容説明
植民地台湾において、島田謹二は、戦間期のフランス比較文学をいかに受容したのか。本書は比較文学と台湾文学の領域を横断しつつ、『華麗島文学志』に結実した、島田の比較文学思想が、「植民地主義」や「国家主義」との関連で形成された過程を、1930年代台湾の言説空間を明らかにしながら、検証していく。
目次
序章 沈黙と誤解から理解へ
第1章 『華麗島文学志』読解の手がかりとして―「比較文学」とは何か
第2章 『華麗島文学志』の誕生
第3章 『華麗島文学志』とその時代―郷土化・戦争・南進化
第4章 「外地文学論」の形成過程
第5章 四〇年代台湾文壇における『華麗島文学志』
第6章 太平洋戦争前夜の島田謹二―ナショナリズムと郷愁
終章 二つの文学史における『華麗島文学志』の意義
著者等紹介
橋本恭子[ハシモトキョウコ]
埼玉県生まれ。学習院大学文学部フランス文学科卒業。パリ第八大学文学部修士課程修了。台湾国立清華大学中文系修士課程修了。2010年5月、一橋大学言語社会研究科博士後期課程修了。博士(学術)。日本社会事業大学非常勤講師。一橋大学言語社会研究科博士研究員。専門は比較文学・台湾文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。