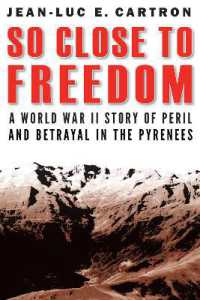内容説明
「独立」以来、「国民」が使いこなせない旧宗主国の言語を「国家公用語」としているセネガル。公共性を担保する言語のない、「曖昧な多言語主義」状況をつくりだす国際機関、巨大NGOの「援助という名の介入」。人々の言語生活の実態調査から、その問題点を明らかにするとともに、言語的多様性と社会的共同性がいかにして両立しうるかをさぐっていく。
目次
第1部 インヴィヴォな管理―ウォロフ語の拡大とウォロフ化への抵抗(ウォロフ語の拡大;ウォロフ化への抵抗―多言語使用という選択;フランス語の位置)
第2部 インヴィトロな管理―作為と不作為(フランス植民地帝国とセネガルの諸言語;独立後のセネガルにおける言語と政治;セネガルにおける言語ナショナリズムの系譜)
第3部 言語政策と介入(終章;結論)
補論(セネガルにおけるアラビア語文学―イスラームと文学の言語;七都市調査結果の分析―三類型)
著者等紹介
砂野幸稔[スナノユキトシ]
1954年滋賀県生まれ。熊本県立大学文学部教員。京都大学博士(地域研究)。専門はアフリカ地域研究(文学、言語文化、歴史)、フランス語圏文化研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
samandabadra
0
ある国家という体をなしていない国家の言語状況をまとめたもの 。言語政策という枠組みからの圧力 (第一章:作者のいうインヴィヴォな管理)と 社会に生きている人々の言語使用の変化 (第二章:インヴィトロな管理)を把握し 一種のエスノグラフとしてまとめたものとして 非常に参考になった。第一章、第二章を踏まえたうえでの 言語政策の考察も非常に面白かった。 とくに第三世界における。国家ではなくソトからの介入の影響は 自分の研究するフィールドでも もっと視野に入れなければならない問題かもしれない 2009/04/05