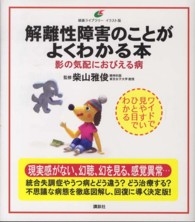出版社内容情報
(1998年『酸化チタン光触媒のすべて-抗菌・防汚・空気浄化のために』普及版)
--------------------------------------------------------------------------------
経済状態が怪しい。日本の将来に暗雲が立ちこめているような気がしてしょうがない。以前,米国のAT&Tベル研究所(当時)に客員研究員として滞在していた時,研究所で毎日,米国人を中心に,日本人,フランス人,ドイツ人,カナダ人など10人ぐらいの研究者と昼食を囲んでいた。そのときよく話題になったのが,日本の経済力の強さであり,アメリカの国力の落ち込みとアメリカ人若者の科学技術離れであった。確かにアメリカの街角は恐ろしく汚く,こわいし,大学の研究室へ行くとアメリカ人の学生は希で,研究を担っているのはほとんどアジア人や他の有色人種という様相であった。一方,日本といえばバブル前の活性期で,株価は徐々に上昇し,研究費も徐々に増え,基礎研究の重要性が叫ばれ,非常に社会全体が自信満々であった。小生自身も,経済でも,科学技術でもアメリカなんかすぐに追い越す,いや,すでに追い越しているかもしれないと思っていた。わずか10年ほど前のことである。
ところがここ数年で様相は一転してしまった。経済でも,科学技術でもアメリカが自信満々になり,日本は自信喪失気味である。経済のことは専門外なので,その理由はわからないが,科学技術に関して言えば,多少自分なりの感想を持っている。原因の一つは日本人の科学技術研究の多くが付和雷同型になっていることではなかろうか。超電導に可能性があると誰かが言い出せば,どの企業でも同じような研究を行い,何百もの(たいして意味のあるとは思えない)特許や論文を量産することで安心してしまう。
光触媒研究もしかりである。光触媒反応による水素発生が発表された1980年から数年はおびただしい数の水素発生の研究がなされ,1980年代の終わりにある大手メーカーが冷蔵庫の脱臭に光触媒を使うことを考えたら,しばらくは冷蔵庫脱臭に関する特許が多くのメーカーから次々と出された。その後,抗菌建材や,セルフクリーニング建材あるいは超親水性が知られると,皆同じような研究を始め,なんと多くの(あまり大差のない)特許などが出されていることか。
これらの研究が無駄だと言っているわけではない。過去の研究を十分にリサーチして,独自のポジションを持った研究の重要性を強調したいのである。光触媒の過去の研究ターゲットの変遷から学べるように,研究というものは視点を変えると全く違った展開が出てくる場合が多い。
本書は1997,98年度の神奈川科学技術アカデミー教育講座(光触媒コース)の講義録をもとにして,現段階での光触媒研究の最先端を,抗菌や空気浄化,防汚,超親水性の問題を中心に,直接これらの研究に携わっている研究者,技術者の役に立てるよう解説したものである。しかし,前述のように光触媒技術は,まだまだ新しい展開があるに違いなく,この本がそのような未来を目指す新進気鋭の研究者にも多少なりとも役立つことを期待してやまない。
最後になったが本書が日の目を見ることができたのは,編集を手伝ってくれた菱沼光代さん,および厳しい夜駆け,朝駆け攻撃をしてくれた(株)シーエムシー一般書部の真勢正英氏のおかげである。ここに深く謝意を表する。
1998年6月22日 編者,著者を代表して 橋本和仁
--------------------------------------------------------------------------------
石崎有義 東芝ライテック(株) 技術本部
齋藤徳良 日本曹達(株) 機能製品事業部
(現)(独)科学技術振興機構 エネルギーナノ材料研究事務所
砂田香矢乃 (財)神奈川科学技術アカデミー
竹内浩士 工業技術院 資源環境技術総合研究所
(現)(独)産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門
橋本和仁 東京大学 先端科学技術研究センター
藤嶋昭 東京大学 大学院工学系研究科
(現)(財)神奈川科学技術アカデミー 理事長
道本忠憲 日東電工(株) テープマテリアル事業部門
日東電工(株) エンジニアリングプラスチック事業部
宮下洋一 ダイキン工業(株) MEC研究所
(現)ダイキン工業(株) グローバル戦略本部 マーケティング部
村澤貞夫 (株)シグナスエンタープライズ
渡部俊也 東京大学 先端科学技術研究センター
(執筆者の所属は,注記以外は1998年当時のものです。)
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 光触媒研究の軌跡
1. ホンダ,フジシマ効果の発見
感光材料の研究から/酸化チタンとの出会い/光による水の分解/水素発生への期待/エネルギー変換効率
2. 半導体電極から光触媒へ
電子・正孔対の生成/電極反応からミクロ電池へ/ミクロセルの効率を上げるには/有機物を入れると水素が発生/光は水素以上に高価なものである
3. 光触媒の可視光化の探求
酸化チタン以外の物探し/自己溶出現象/酸化チタンの修飾ドーピング/色素吸着/Gratzel Cell
4. 光触媒の適用研究の変遷
有機合成への適用/<非選択的な反応>/環境浄化への適用/<強力な酸化力>/<有害物質の分解>/微弱光を利用した室内外の清浄化/<きっかけは便器>
5. 酸化チタン光触媒の応用形態の変遷
懸濁系から担持系/薄膜担持系/分散担持系/暗反応とハイブリッド化/<吸着剤とのハイブリッド>/<抗菌金属とのハイブリッド>/超親水性による防汚効果/両親媒性の発見
第2章 光触媒反応の基礎
1. 半導体のエネルギー構造と光効果
半導体のバンド構造/半導体の光効果/シリコン太陽電池/光触媒反応/フォトコロージョン/酸化チタンの結晶構造と光触媒活性/吸収光は近紫外線/無色透明性
2. 光触媒反応の特徴
光は量子化されている/入射された光子数しか反応しない/熱力学からみた光触媒
3. 微弱光を利用する光触媒反応
「光にかかるコスト」からの解放/生活空間の紫外線量/光触媒をどう使うか/空気浄化のモデル実験/殺菌効果のモデル実験/防汚効果のモデル実験/1つの材料で多機能は狙えない/<空気浄化に適した材料>/<防汚・抗菌に適した材料>
4. 水処理への応用
拡散係数/光触媒の形態/触媒活性/量子効率/水処理の難しさ/超純水の製造/海上流出油の浄化/反応物質を気相へ追い出す/オゾン反応とのハイブリッド化/バイオ反応,UV反応とのハイブリッド化
5. 光触媒酸化分解反応機構
光照射初期過程/活性種の同定/光強度の強い場合/光強度の弱い場合/長寿命活性酸素種の生成の量子効率/長寿命活性酸素種の表面濃度/短寿命活性酸素種の生成の量子効率/活性種の空気中への放出はあるか/有機物の分解機構/吸着油の光触媒分解
6. 酸化チタン表面の光誘起両親媒性
両親媒性/超親水性/酸化分解反応との関係/酸素の効果/水中での超音波照射効果/超親油性/表面の微細構造/ハイドロテクスチャー構造/酸化分解型光触媒反応と光誘起親水化反応関係
7. グレッチェル電池の基礎と展望
湿式太陽電池/人工光合成型/レドックスカップル型/色素増感反応/エネルギー変換効率の上がった理由/ルテニウム錯体とポーラスな電極/実用太陽電池としての問題点
第3章 光触媒材料
1. 酸化チタンの性状
1. 酸化チタンの特徴
屈折率が最大/被覆顔料/紫外光で励起/誘電率が大きい
2. 酸化チタンの主な用途
塗料/インキ・顔料/合成樹脂/製紙用/化学繊維/白ゴム/その他
3. 酸化チタンの使用量
世界の消費量/国内販売量/地域別消費量
4. 酸化チタンの生産能力
地域別生産能力/世界の主要メーカー/国内の生産能力
5. 酸化チタンの原料
イルミナイト/天然ルチル/砂鉄/アップグレード品/チタン・スラグ/合成ルチル
6. 酸化チタンの製造方法
硫酸法から塩素法へ/硫酸法のプロセス/<イルミナイトを硫酸に溶解>/<冷却し硫酸鉄を分離>/<ろ過・濃縮の後,加水分解>/<加水分解工程における粒度分布の制御>/<硫酸法における酸化チタンの結晶型>/<ろ過清浄し廃硫酸を始末>/<さまざまな処理ののち焼成>/<粉砕・分級,表面処理>/塩素法のプロセス/<ルチル鉱の塩素化>/<四塩化チタンの精留,酸化>/<酸化チタンを分離し,塩素はリサイクル>
7. チョーキング現象と表面処理
チョーキング現象/表面処理/紫外線吸収剤
8. 酸化チタン光半導体の実用化
画像記録材料/光還元記録/チタンマスター/グレチェルセル/光触媒
9. 光触媒としての酸化チタン製品
よい光触媒とは/粉末製品とその用途/<ST-01>/<ST-21>/<ST-41>/<ST-31>/粉末の分散化/脱臭フィルター/コーティング液/セメントバインダー/水処理への期待
2. 酸化チタンの担持法
2.1 酸化チタン膜コーティング法
1. ゾルゲル法
ゾルゲルとは何か/ゲルとは何か/ゾルゲル法とは/長所・短所
2. ゾルゲル法の原料
原料化合物/金属アルコキシドとは/金属アルコキシドの合成/<アルコール交換反応>/<複合アルコキシド>/チタンアルコキシドの反応性/<加水分解反応>/<加水分解因子>/<アシレートの形成>/キレート化合物/<β-ジケトン>/<ヒドロキシカルボン酸キレート>/ <β-ケトエステル>/<グリコールキレート>/主な有機チタネート/Ti-O-Siの結合を作るには
3. ゾルナル法によるコーティング膜
ディップコーティング法/<5つのステップ>/<膜厚の変動因子>/<ディップ液管理モデル>/スピンコーティング法/バイロゾル法/<バイロゾルの特徴>/<透明薄膜の形成>/<膜厚と透過率>/<裏面照射>/<防汚効果>/<抗菌効果>
4. 高活性膜を設計するには
有機チタネート化合物の結晶化/膜厚の効果/膜の表面状態/NOxの分解例/<透明性>/<AFMイメージ>/<膜厚と分解性>
5. コーティング剤の実際
高温焼き付けタイプ/低温硬化2層タイプ
2.2 酸化チタン粉体分散法(1)酸化チタン粉末担持紙
1. パルプは優れた担体
アセトアルデヒドの分解/タバコのヤニの分解
2. 紙の安定性を保持するには
紙の破裂強度/<酸化チタンの影響1>/<酸化チタンの影響2>/酸化チタンの凝集/<凝集プロセス>/<強度の変化>/<光触媒活性>/粉落ちの問題
3. 実用的応用例
吸着剤との組み合わせ/種々のサンプル製作
2.3 酸化チタン粉末分散法(2)酸チタン粉末担持フッ素樹脂膜
1. フッ素樹脂の特性
担持材料としての特徴/使用目的と構造/フッ素樹脂の種類/PTPE樹脂の特徴<耐酸化性など>/<低誘電率>/<耐薬品性>/<すべり性>/<撥水性>/<非粘着性>/塗膜の接触角と用途
2. PTFE樹脂の加工方法
PTPE材料/モーリディングパウダーの成形方法/ファインパウダーの成型方法/ディスパージョン加工
3. 光触媒含有フッ素樹脂の開発
開発に至る経緯/フッ素樹脂撥水膜の構造/耐紫外線性/屋外暴露試験/洗浄効果/色素分解能/抗菌性/脱臭・浄化用途への展開
3. 超親水性材料
1. 超親水化現象とは
水との接触角の低下/励起波長/膜厚と超撥水性/界面活性剤にはない耐久性
2. 超親水性材料開発
蓄水性物質との混合/基材とコーティング法
3. 工業用に期待される機能
防曇性/防滴性/易水洗効果/2つのセルフクリーニング
第4章 光触媒活性評価法
サンプルの形態/光源を選ぶ/単色光を得る/光量の測定
1. 酸化分解活性評価法
1. 吸着物質の分解(防汚効果)
1.1 重量変化法(油分解)
標準的実験条件
1.2 吸光度変化(色素分解法)
色素の選択/必要な装置/前処理/色素吸着/透明試料の活性評価/油分解活性との比較/白色不透明試料の活性評価/着色不透明試料の活性評価/活性の絶対値の決定は難しい/標準的実験条件
2. 空気中物質の分解(空気浄化効果)
2.1 解析のための基礎理論と反応速度の決定因子
Langmuir吸着等温式/吸着平衡定数と飽和吸着量の求め方/物質の捕獲確率は必ずしも吸着平衡定数から予測できない/Langmuir-Hinshelwoodの速度式/反応速度の光強度依存性/反応速度の濃度依存性
2.2 静置系での活性評価
必要な装置/光触媒活性は光強度や気相濃度によって異なる/標準的実験条件
2.3 流通法での活性評価
除去率の求め方/流速と除去率の関係
2. 抗菌性の評価法
1. 抗菌性評価の手順
菌株の入手方法/菌株の保存方法/<継代培養保存法>/<凍結保存法>/菌液の調整/<前培養>/<洗浄>/<検量線の作製>/<菌液の希釈>/抗菌性の評価/<光触媒試料>/<菌液の滴下>/<光照射>/<菌の回収>/<菌の培養>/実験結果/<菌の回収率>/<菌の生存率>/<抗菌性の比較>/<水処理系での実験>/器具や培地の準備/無菌操作/用地の定義
2. 光触媒による抗菌性の特徴
対数増殖期の菌に対する効果が大/エンドトキシンも分解/抗菌性の作用機構/銀と酸化チタンの組み合わせ
3. その他の評価方法の紹介
フィルム密着法(ラップ法)/滴下法(ドロップ法)/シェークフラスコ法
3. 親水性評価法
接触角の測定/Youngの式/接触角の変化速度の意味/親水性評価の3因子/親水化速度/限界接触角/暗所維持性/初期接触角/酸化分解活性と超親水性活性の相関/親油性
第5章 光触媒の実用化
1. 抗菌タイル
1. 反応性と光源の強度
反応性の評価法(ガス分離法)/<抗菌効果>/微弱光の有効性/<分解性>/<殺菌性>/<量子効率>
2. 光触媒タイルの作製法
陶磁器の製造工程/光触媒の焼成過程をどこに組み込むか/製造上の問題点/<光触媒活性>/<薄膜の硬度>/活性低下の原因および解決方法/<釉薬と焼成条件>/<相転位と粒成長>
3. 光触媒タイルの機能
抗菌力の実証/テーブルテスト/モデルテスト/汚れ,菌,臭いの相関/フィールドテスト/防汚効果の実証
4. 光触媒タイルの施行例と商品化
病院への施工例/ラット飼育室への施工例/抗ウイルス効果/防カビ試験/タイルの商品化/<商品企画の観点から>/<デザインと機能>/<価格設定>/<耐久性>/<安全性>
2.セルフクリーニング照明
1. 照明と光触媒
光化学反応/酸化チタンと照明製品
2. 照明用ランプと紫外線
白熱電球(ハロゲン電球)/蛍光ランプ/蛍光ランプの種類/蛍光ランプの使用上の注意/光触媒励起用蛍光ランプ/HIDランプ
3. 照明器具
4. 紫外線について
用語/紫外線の種類/太陽光からのUV強度/生体への影響/紫外線の測定方法
5. 今後の動き
3.空気清浄機
1. 快適室内環境(IAQ:Indoor Air Quality)とは
2. 生活環境の健康・快適志向
住宅の高気密化/NOxに対する規制/高齢化と老人医療/アレルギー症の増加/食品衛生
3. 主な空気汚染物質
空気汚染物質の分類/光触媒の対象となる空気汚染物質とは/汚染物質の発生源と健康への影響
4. 法規制の動向およぴ汚染物質の現状
生活環境における規制/揮発性有機化合物(VOC)/ホルムアルデヒド/二酸化窒素(NO2)/タバコ煙/悪臭物質<臭気分類>/<におい成分とその割合>/<規制基準値>
5. 光触媒による空気清浄化
脱臭方式の原理別分類/光触媒方式の利点/オゾン脱臭との比較/光触媒の実験装置/静的試験におけるアセトアルデヒドの脱臭性能/光強度と脱臭性能/風速と脱臭性能/接着剤との併用/NOxの分解性能/殺菌作用/空気清浄機の構造
4. 環境大気の浄化
1. 我が国の大気汚染の現状
2. 光触媒による人気汚染物質の除去
3. 光触媒の固定化の要件
4. 固定化光触媒とその性能
試験方法/比表面積の重要性/フッ素樹脂シート/セメント硬化体/無機系塗料/浄化材料の比較
5. 環境大気の浄化(パッシブ浄化)
6. 半閉鎖的空間の浄化差(アクティブ浄化)
7. まとめと将来展望
5. 超親水性
1. 応用例と実施試験
窓ガラス/<常温硬化タイプのコーティング剤>/車のサイドミラー/易水溶性/セルフクリーニング/易乾燥性
2. 製品設計に関わる性能
親水化速度と暗所維持性/耐久性/透明性/対摩耗性/接触角の性能の関係/親水型と分離型
3. 今後の展望
物質表面の制御/超親水化材料
第6章 今後の展望 -快適な空間を創造する技術として-
付表 主な(酸化チタン)光触媒関連文献一覧表 1991年~1997年
--------------------------------------------------------------------------------
内容説明
本書は1997、98年度の神奈川科学技術アカデミー教育講座(光触媒コース)の講義録をもとにして、現段階での光触媒研究の最先端を、抗菌や空気浄化、防汚、超親水性の問題を中心に、直接これらの研究に携わっている研究者、技術者の役に立てるよう解説したものである。
目次
第1章 光触媒研究の軌跡
第2章 光触媒反応の基礎
第3章 光触媒材料
第4章 光触媒活性評価法
第5章 光触媒の実用化
第6章 今後の展望―快適な空間を創造する技術として
著者等紹介
橋本和仁[ハシモトカズヒト]
東京大学先端科学技術研究センター
藤嶋昭[フジシマアキラ]
東京大学大学院工学系研究科。現、(財)神奈川科学技術アカデミー理事長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。