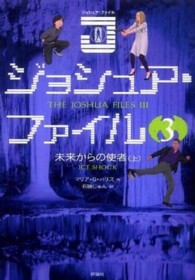出版社内容情報
【執筆者一覧(執筆順)】
渋谷 昇 拓殖大学 工学部
平戸昌利 グローバル・テクノマネジメント研究所 所長
徳田正満 九州工業大学 工学部
(現)武蔵工業大学 工学部
橋本良樹 吉野電化工業(株) 常務取締役
柏木邦宏 東洋大学 工学部
遠藤 誠 昭和電工(株) 総合研究所
野村恭司 神東塗料(株) 技術開発本部
吉田 博 ジオマテック(株) 技術本部
(現)ジオマテック(株) 企画本部
岩崎厚夫 住友スリーエム(株) 電気電子製品事業部
畠山賢一 姫路工業大学 工学部
(現)姫路工業大学 大学院工学研究科
戸川 斉 (株)トーキン・イ・エム・シ・エンジニアリング システム事業部
(現)(株)トーキンEMCエンジニアリング EMCテクニカルセンター
吉田栄吉 (株)トーキン R&Dセンター
(現)NECトーキン(株) ファンクショナルデバイス事業本部
元島栖二 岐阜大学 工学部
岩永 浩 長崎大学 工学部
V.K.Varadan ペンシルバニア州立大学 電子音響工学研究所
森元昌平 タツタ電線(株) 新規事業部
(現)タツタシステム・エレクトロニクス(株) 機能性フィルム事業部
遠矢弘和 日本電気(株) EMC技術センター
(現)日本電気(株) 実装研究所
吉永孝司 日本電気(株) EMC技術センター
(所属は1998年9月時点。( )内は2003年9月現在)
【構成および内容】
第1章 EMC規格・規制の最新動向
1.IECのイミュニティ規格 渋谷 昇
1.1 IEC
(1)基本EMC刊行物
(2)共通規格(Generic Standard)
(3)製品(群)規格(Product(Family)Standard)
1.2 基本イミュニティ規格の内容
(1)IEC61000-4-2 静電気放電
(2)IEC61000-4-3 放射電磁界
(3)IEC61000-4-4 電気的高速過渡バースト(EFT/B)試験
(4)IEC61000-4-5 サージイミュニティ試験
(5)IEC61000-4-6 伝導性イミュニティ試験
(6)IEC61000-4-8 電源周波磁界要求
(7)IEC61000-4-11 電圧低下および瞬断
1.3 共通規格の内容
(1)共通エミッション規格(IEC61000-3,4)
(2)共通イミュニティ規格(IEC61000-1,2)
1.4 製品(群)規格の概説
(1)IEC61326シリーズ 計測制御機器
(2)IEC60601-1-2 医用電気電子装置
2.EUのEMC指令 平戸昌利
2.1 EU規制の導入理由は
2.2 PLとEU指令
2.3 欧州規格(EN)とEC指令
2.4 EMC指令の導入
(1)適用範囲
(2)保護必須条項
(3)整合規格
(4)適合性の証明
2.5 EMC指令の要求事項とは
(1)基本EMC規格
(2)共通EMC規格
(3)製品群EMC規格
(4)製品別EMC規格
2.6 EN規格と規格制定機関
(1)EN規格の構成と番号の割り当て
(2)EN規格の適用
2.7 試験機関と適合性評価について
(1)適合性評価(規格に基づいて)
(2)適合性評価手続き
(3)モジュール適合性評価
2.8 CEマーキング(EMC指令)取得
(1)対象製品
(2)対応方法
(3)指令と規格の関係
(4)技術ファイル(TCFルート)
(5)適合宣言
(6)グローバル体制下の適合の役割分担
2.9 EMC指令による試験内容は
2.10 EMC指令対応の設計の考え方と対策(測定内容を含む)
(1)エミッション設計の考え方
(2)イミュニティの設計の考え方
(3)電源についての基本的な考え方
2.11 日本企業としての対応
(1)技術者の立場
(2)企業トップとしての立場
3.EMC規格のJIS化
3.1 電気・電子総合規格委員会での検討経緯
3.1.1 EMC規格整備の基本方針
(1)国際規格と整合した国内規格の制定
(2)政府が直接関与する規格(JIS)は必要最小限
(3)法規制と連携した企画(JIS)作成
(4)国際規格作成過程への日本の協力体制強化
3.1.2 EMC規格をJIS化する必要性
3.1.3 規格体系およびJIS化の範囲
(1)原則
(2)IBCの規格体系
(3)JIS化の範囲とその体系
3.2 JIS/EMC制定委員会の検討状況
3.2.1 設立経緯と組織
3.2.2 JIS原案の作成状況
3.3 JISに使用するEMC用語
3.4 イミュニティ関連規格のJIS化
第2章 電磁シールド材料
1.無電解メッキと材料 橋本良樹
1.1 はじめに
1.2 無電解メッキによるシールド技術
1.2.1 無電解メッキ法
1.2.2 電磁波シールド用無電解メッキ工程
1.3 無電解メッキ法の特徴
1.3.1 高いシールド効果
1.3.2 均一な薄膜のシールド
1.3.3 低い接触抵抗
1.4 無電解メッキ法の留意点
1.5 片面無電解メッキ法
1.5.1 片面無電解メッキの工程概要
1.5.2 片面無電解メッキの特長
(1)他の片面シールド広報との比較
(2)両面無電解メッキとの比較
1.5.3 無電解片面メッキ法の留意点
1.6 EMI規制と今後
2.イオンプレーティングと材料 柏木邦宏
2.1 イオンプレーティング
2.2 イオンプレーティング技術
2.3 イオンプレーティングの基本原理
2.4 高周波イオンプレーティング
2.5 イオンプレーティングの効果
(1)プラズマやイオンが基板に及ぼす影響
(2)プラズマやイオンが膜に及ぼす影響
(3)放電がガス圧の膜に対する影響
2.6 反応性イオンプレーティング
(1)酸化膜
(2)炭化膜
(3)窒化膜
2.7 イオンプレーティングによるプラズマ重合膜
2.8 イオンプレーティングによる新材料
(1)機械的機能膜
(2)電気的機能膜
(3)化学的機能膜
(4)光学的機能膜
2.9 新しい応用
(1)カラーフィルター
(2)ブラックマトリクス
(3)高絶縁膜の形成
(4)複合膜の電気的特性
(5)有機ダイオード
2.10 おわりに
3.導電性プラスチック 遠藤 誠
3.1 背景
3.2 EMIシールドの原理
3.3 筐体によるEMIシールド
3.4 導電性プラスチックとは
3.5 導電性プラスチックの導電機構
3.6 従来の導電性プラスチックとその問題点
3.7 現状の導電性プラスチック
①東芝ケミカル-エミクリア
②神戸製鋼所-CFRP,コパトロン
③東洋インキ製造-リオコンダクトEMI-S
3.8 まとめ
4.導電性塗料 野村恭司
4.1 はじめに
4.2 電磁波シールド塗料の歩み
4.3 導電性塗料による電磁波シールド技法の特徴
4.4 組成と特徴
(1)導電性フィラー
(2)バインダー(樹脂)
(3)溶剤
(4)添加剤
4.5 性能
4.6 UL認証制度について
4.7 導電性塗料の今後
5.ITO 吉田 博
5.1 はじめに
5.2 ITO膜
5.2.1 歴史
5.2.2 用途
5.2.3 作製方法
5.2.4 特徴と特性
5.3 樹脂基板へのITO成膜
5.3.1 基板からの放出ガス
5.3.2 静電気
5.4 ディスプレイフィルターへの応用
5.4.1 構成例
5.4.2 分光反射率特性
5.4.3 電磁波シールド
(1)測定方法
(2)測定結果
5.5 今後の展開
6.導電材料 岩崎厚夫
6.1 はじめに
6.2 シールド材料を選定するにあたって
6.3 金属箔ラミネート
6.4 金属箔テープ
①金属箔+導電性粘着剤タイプ
②エンボス加工金属箔+非導電性粘着剤タイプ
③金属箔+非導電性粘着剤タイプ
④その他(フィルムラミネート金属箔+導電性粘着剤)
6.5 電磁カードシールドスリーブ
第3章 電波吸収体
1.電波吸収理論 畠山賢一
1.1 電磁波の反射
1.2 損失媒質
1.3 整合の方法
(1)フェライト焼結体を用いた吸収体
(2)導電膜を利用した吸収体
(3)1/4波長厚みの単層吸収体
(4)多層構成の吸収体
1.4 電波吸収体の使用に関する留意点
(1)電磁波発生源の近傍に電波吸収体を置く場合
(2)斜め入射で使用する場合
2.電波吸収体の評価法 戸川 斉
2.1 同軸・導波管を用いる方法
2.2 ストリップライン法
2.3 フリースペース法(NRL法)
2.4 パラボラ反射鏡を用いる方法
3.軟磁性金属を使用した吸収体 吉田栄吉
3.1 はじめに
3.2 軟磁性金属を用いた吸収体出現の背景
3.3 軟磁性金属材料の分類
3.4 透過率の周波数特性の制御
3.5 材料選定に際しての考え方
3.6 金属磁性体の製造方法の一例
3.6.1 金属磁性粉末の製造方法
3.6.2 マトリックス化への手段
3.7 高周波ノイズ対策への適用事例
(1)リボンケーブルからの放射ノイズ抑制
(2)信号ケーブルからの放射ノイズ抑制
(3)1.9GHz無線ユニットの内部干渉抑制
4.新しい電磁波吸収体・カーボンマイクロコイル
-コスモ・ミメティックなカーボンマイクロコイルの気相合成と電磁波吸収特性
元島栖二,岩永 浩,V.K.Varadan
4.1 はじめに
4.2 実験方法
4.3 実験結果と考察
4.3.1 カーボンコイルの合成条件
(1)炭素源
(2)触媒の種類とその形態
(3)不純物ガスの種類と流量
(4)反応温度
4.3.2 モルフォロジー
(1)粉末状(短尺)カーボンコイル
(2)コイル形態の制御
4.3.3 成長機構
4.3.4 微細構造および組成
4.3.5 コイル状の金属炭化物および窒化物ファイバーの合成
4.3.6 カーボンコイルの機械的・電気的・熱的特性
(1)機械的特性
(2)電気的特性
(3)熱的性質
4.3.7 カーボンコイルの電磁波吸収体特性
4.4 おわりに
第4章 電磁シールド対策の実際
1.銅ペーストを用いたEMI対策プリント配線板 森元昌平
1.1 プリント配線板におけるEMC
1.2 EMI対策配線板の構造
1.2.1 アンダーコート
1.2.2 銅ペースト
1.2.3 オーバーコート
1.3 EMI対策配線板の特徴
1.4 EMI対策配線板によるEMIの低減
1.4.1 グラウンド電位の安定化
1.4.2 高周波電流のループ面積の縮小
1.4.3 リンギングの抑制
1.4.4 クロストークノイズの抑制
1.4.5 シールド効果
1.5 EMI対策配線板の設計
1.6 採用時の留意点
1.6.1 材料選択および製造工程管理
(1)アンダーコート材料
(2)銅ペースト
1.6.2 回路設計
(1)回路例1:発振回路
(2)回路例2:フィルター回路
2.コンピュータ機器の実施例
2.1 はじめに
(1)扉/筐体の基本構造
(2)ケーブルの基本構造
2.2 コンピュータの特徴
2.3 床面の開口処理
2.4 側面の開口
2.5 スロットアンテナ
(1)スロットの長さ
(2)スロットの幅の影響
(3)スロットアンテナの効率
(4)実測値
2.6 特殊な電磁シールド構造
2.7 電磁シールド材料
内容説明
小型化するパソコンや携帯電話は、職場や家庭にまで電磁波の洪水をもたらしており、1996年には携帯電話による、目には見えない電磁波が人体や医療器具に与える影響が大きくクローズアップされている。欧州連合(EU)は、1996年1月から電磁波の発生(EMI:Electro Magnetic Interference、電磁放射障害)と被害(EMS:Electro Magnetic Susceptibility、電磁的感受性)の両面を視野に入れた電子機器のEMC(Electro Magnetic Compatibility)規制実施に踏み切った。本書は、EMC規格・規制の動向、電磁シールド材料、電波吸収体、電磁シールド対策の実施例も加えた構成となっている。
目次
第1章 EMC規格・規制の最新動向(IECのイミュニティ規格;EUのEMC指令 ほか)
第2章 電磁シールド材料(無電解メッキと材料;イオンプレーティングと材料 ほか)
第3章 電波吸収体(電波吸収理論;電波吸収体の評価法 ほか)
第4章 電磁シールド対策の実際(銅ペーストを用いたEMI対策プリント配線板;コンピュータ機器の実施例)
-

- 和書
- 集合住宅ファイル・ブック