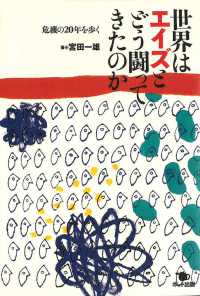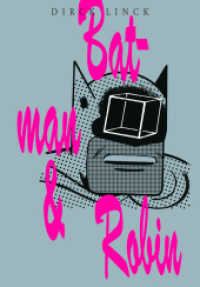出版社内容情報
執筆者一覧(執筆順)
多賀信夫 東京大学名誉教授
平田義正 名城大学 薬学部
中山大樹 山梨大学 工学部
椿 啓介 筑波大学 生物科学科系
(現) 東京農業大学 総合研究所
土倉亮一 京都教育大学 教育学部
中桐 昭 筑波大学 生物科学系
岡崎尚夫 三共(株) 醗酵研究所
清水 潮 東京大学 海洋研究所
(現) 東洋水産(株) 研究開発部
大和田紘一 東京大学 海洋研究所
(現) 熊本県立大学 環境共生学部
芝 恒男 東京大学 海洋研究所
(現) (独)水産大学校 食品化学科
絵面良男 北海道大学 水産学部
(現) 北海道大学名誉教授
今田千秋 東京大学 海洋研究所
(現) 東京水産大学大学院 水産研究科
奥谷康一 香川大学 農学部
(現) 香川大学名誉教授
横浜康継 筑波大学 下田臨海実験センター
(現) 志津川町自然環境活用センター
越智雅光 高知大学 理学部
坂上良男 東京工業大学名誉教授
小林淳一 三菱化成生命科学研究所
(現) 北海道大学 大学院薬学研究科
遠藤 衛 サントリー(株) 生物医学研究所
本多 厚 東京薬科大学 第一生化学研究所
安元 健 東北大学 農学部
(現) (財)日本食品分析センター 多摩研究所
伏谷伸宏 東京大学 農学部
中島敏光 海洋科学技術センター 海洋開発研究部
橋本 惇 海洋科学技術センター 深海研究部
(執筆者の所属は,注記以外は1986年当時のものです)
構成および内容
第1章 海洋生物資源の有効活用
1.海洋微生物資源の有効利用 多賀信夫
1.1 はじめに
1.2 海洋微生物の生理学的・生態学的特性
1.3 海洋微生物の有効利用とその可能性
1.3.1 生物活性物質の生産
1.3.2 餌料として微生物の利用
1.4 おわりに
2.海洋生物由来の生理活性物質 平田義正
2.1 はじめに
2.2 海洋生物由来の生物活性成分研究の特徴
2.3 海洋生物からの生産物の実用化例
2.3.1 ネライストキシン(Nereistoxin)
2.3.2 カイニン酸(Kainic acid)
2.4 海洋生物の生理活性物質ならびに行動抑制物質
2.4.1 海洋生物ホルモン
2.4.2 海洋生物のケモレセプション
2.5 生物発光
2.5.1 ウミホタルの発光
2.5.2 オワンクラゲ(Aequorea)の発光
2.5.3 腔腸類ウミシイタケ(Renilla)
2.5.4 発光魚
2.5.5 ホタルイカの発光
2.5.6 その他の海産生物発光
2.6 その他の生理活性物質
2.7 おわりに
3.海洋生物資源の有効利用 中山大樹
3.1 海洋生物資源という概念について
3.2 海洋の性格
3.3 水産資源の性格
3.3.1 水産資源の性格
3.3.2 浅海
3.3.3 深い海の表層
3.3.4 深海底
3.4 栄養塩の補給
3.5 遺伝子資源
3.5.1 生理活性物質と微生物
3.5.2 海洋微生物の生態
3.5.3 海洋光合成微生物集殖法
3.6 潜在資源の有効利用
3.6.1 受光面の利用
3.6.2 溶存物質の利用
3.6.3 空間の利用
第2章 海洋微生物
1.海生菌の探索・分離・培養 椿 啓介
1.1 はじめに(海生菌類とは)
1.2 海生菌類の分類学上の位置と特徴
1.2.1 採集と分離培養
1.3 海生菌類の同定
2.海生菌(Arenicolous)の探索・分離・培養 土倉亮一
2.1 はじめに
2.2 砂浜海岸に住んでいる海生菌類
2.2.1 初期の調査
2.2.2 試料採取と観察の効率的な方法
2.2.3 本邦の砂浜海岸に分布する海生菌
2.2.4 砂浜に住む海生菌の採取適期はいつごろか
2.2.5 砂浜の表層と底層で菌数は異なるか
2.3 砂浜へ漂着する海生菌
2.3.1 砂粒状に有機質を与えて海生菌をつりとる
2.3.2 種々の有機質による海生菌の検出数
2.3.3 海藻に移行しやすい海生菌
2.3.4 砂粒状の子実体形成の温度範囲
2.4 Arenicolous海生菌の分離と培養
2.4.1 子のう胞子の発芽
2.4.2 分離菌株の培地上の性質
2.5 おわりに
3.海洋酵母 中桐 昭
3.1 はじめに
3.2 海洋酵母とは
3.3 海洋酵母の分離源および基質
3.3.1 海水
3.3.2 海泥および海砂などの沈積物
3.3.3 プランクトン
3.3.4 海藻
3.3.5 高等植物
3.3.6 動物
3.3.7 鉱油
3.4 おわりに
4.海洋放射菌 岡崎尚夫
4.1 はじめに
4.2 海洋放射菌の分布と種類
4.3 海洋放射菌の生理的特異性
4.4 生理活性物質探索源としての海洋放射菌
4.4.1 SS-228Y
4.4.2 Aplasmomycins
4.4.3 Istamysins
5.海洋細菌
5.1 従属栄養細菌 清水 潮
5.1.1 従属栄養細菌の分布
5.1.2 従属栄養細菌の分離と培養
5.1.3 充足栄養細菌の分類
5.2 好圧細菌 大和田紘一
5.2.1 はじめに
5.2.2 深海域における微生物群集の代謝活性
5.2.3 個々の細菌と好圧性
5.2.4 熱水噴出口周辺における微生物群
5.3 光合成細菌 芝 恒男
5.3.1 はじめに
5.3.2 Rhodospirillaceae,Chromatiaceae,Chlorobiaceae
5.3.3 好気性光合成細菌 Erythrobacter
5.3.4 海洋からは分離されていない光合成細菌
5.4 低温細菌 絵面良男
5.4.1 はじめに
5.4.2 低温菌の存在
5.4.3 低温細菌の特性
5.4.4 プラスミド
5.4.5 発光性低温細菌
5.4.6 おわりに
6.海洋細菌由来の生理活性物質
6.1 タンパク質分解酵素阻害剤(プロテア-ゼインヒビター) 今田千秋・多賀信夫
6.1.1 はじめに
6.1.2 プロテア-ゼインヒビター生産菌の分離と培養
6.1.3 プロテア-ゼインヒビター生産菌の分類と同定
6.1.4 インヒビター生産菌の培養条件の検討
6.1.5 インヒビターの精製および諸性状
6.1.6 考察およびまとめ
6.2 抗腫瘍性物質 奥谷康一
6.2.1 はじめに
6.2.2 細菌の多糖体とは
6.2.3 Vibrioの多糖体
6.2.4 Pseudomonasの多糖体
6.2.5 フルクタン
6.2.6 Serratiaの多糖体
6.2.7 海泥の細菌の多糖体
6.2.8 Vibrio algosus類維持菌の多糖体
6.2.9 その他の抗腫瘍性多糖体について
6.2.10 おわりに
第3章 海洋植物と生理活性物質
1.多彩な海の植物 横浜康継
1.1 はじめに
1.2 海藻と海草
1.2.1 海底の種子植物
1.2.2 海への回帰
1.2.3 海藻という植物
1.3 海藻の色彩
1.3.1 身近な海藻とその色
1.3.2 紅藻・褐藻・緑藻
1.4 多彩な紅藻
1.4.1 紅藻の色素組成
1.4.2 生育環境と色彩
1.4.3 海中の光と補色適応
1.5 色彩の変化に乏しい褐藻
1.6 緑藻の色素組成
1.6.1 深所の緑藻
1.6.2 浅所の深所型緑藻
1.6.3 シホナキサンチンを欠く深所種
1.6.4 始原緑藻の色
1.6.5 緑の植物の出現
1.7 おわりに
2.海藻由来の生理活性物質-農業用ケミカルズの探索 越智雅光
2.1 はじめに
2.2 微生物に対する活性成分
2.2.1 ハゴロモ科の海藻から得られた活性成分
2.2.2 アミジグサ科の海藻の活性成分
2.2.3 カギノリ科の海藻の活性成分
2.2.4 ユカリ科の海藻の活性成分
2.2.5 フジマツモ科の海藻の活性成分
2.3 植物に対する活性成分
2.4 昆虫に対する活性成分
3.食用海藻由来の抗腫瘍物質 坂上良男
3.1 はじめに
3.2 抗腫瘍物質の探索
3.3 アサクサノリ含有抗腫瘍物質
3.3.1 単離
3.3.2 物理化学的性状
3.3.3 生物学的性質
3.4 オゴノリ含有抗腫瘍物質
3.4.1 単離
3.4.2 物理化学的性状
3.4.3 生物学的性質
3.5 おわりに
第4章 海洋動物由来の生理活性物質
1.薬理活性物質(その1) 小林淳一
1.1 はじめに
1.2 イモ貝の生理活性物質
1.2.1 イモ貝の毒器官
1.2.2 ジェオグラフトキシン
1.2.3 ストリアトキシン
1.2.4 エブルネトキシンとテズラトキシン
1.2.5 その他の生理活性物質
1.3 海綿動物の生理活性物質
1.3.1 アアプタミン類
1.3.2 ケラマジン
1.3.3 テオネリン類
1.3.4 セストキノン
1.3.5 アゲラシジン類とアゲラシン類
1.3.6 プレアリン類
1.4 ホヤの生理活性物質
1.4.1 はじめに
1.4.2 ブロモユージストミンD
1.4.3 パリセン酸
1.5 腔腸動物の生理活性物質
1.5.1 デオキシザルコフィン
1.5.2 イソギンチャクの紫外線吸収物質
1.6 その他の生物
1.7 おわりに
2.薬理活性物質(その2) 遠藤 衛
2.1 はじめに
2.2 抽出と一次スクリーニング
2.3 細胞毒性化合物
2.4 冠血管拡張作用化合物
2.5 海綿から得られた血圧低下作用物質
3.海産プロスタノイドと抗腫瘍活性 本多 厚
3.1 はじめに
3.2 腔腸動物に含まれるプロスタノイド
3.2.1 Plexaura homomalla
3.2.2 Lobophyton depressum
3.2.3 Euplexaura erecta
3.2.4 Clavularia viridis
3.2.5 Telesto riisei
3.3 魚類および貝類に含まれるプロスタノイド
3.4 おわりに
4.Toxinについて
4.1 はじめに
4.2 イソメ毒の農薬への応用
4.3 ナトリウムチャンネルに作用する毒
4.3.1 テトロドトキシン
4.3.2 サキシトキシンと誘導体
4.3.3 シガトキシン
4.3.4 ブレベトキシン
4.4 カルシウムチャンネルに作用する毒
4.4.1 マイトトキシン
4.4.2 オカダ酸
4.4.3 パリトキシン
4.5 その他の毒
4.5.1 ネオスルガトキシンとプロスルガトキシン
4.6 おわりに
5.抗腫瘍物質 伏谷伸宏
5.1 はじめに
5.2 海洋動物の抗腫瘍活性
5.3 海綿動物
5.4 腔腸動物
5.5 環形,軟体,外肛および棘皮動物
5.5.1 環形動物
5.5.2 軟体動物
5.5.3 外肛動物
5.5.4 棘皮動物
5.6 原策および脊椎動物
5.6.1 原策動物
5.6.2 魚類
5.7 おわりに
第5章 海洋生物資源利用の実際技術
1.海洋生物生産のための深層水利用技術 中島敏光
1.1 はじめに
1.2 深層水の諸特性
1.3 生物生産のための深層水利用技術
1.3.1 技術開発の状況
1.3.2 技術開発事例
1.4 今後の展望
2.深海生物調査手法の現状 橋本 惇
2.1 はじめに
2.2 航法システム
2.3 側深と海底面の探査
2.4 光学機器による深海生物調査
2.5 潜水調査船と無人潜水機
2.6 おわりに
目次
第1章 海洋生物資源の有効活用(海洋微生物資源の有効利用;海洋生物由来の生理活性物質 ほか)
第2章 海洋微生物(海生菌の探索・分離・培養;海生菌(Arenicolous)の探索・分離・培養 ほか)
第3章 海洋植物と生理活性物質(多彩な海の植物;海藻由来の生理活性物質―農業用ケミカルズの探索 ほか)
第4章 海洋動物由来の生理活性物質(薬理活性物質;海産プロスタノイドと抗腫瘍活性 ほか)
第5章 海洋生物資源利用の実際技術(海洋生物生産のための深層水利用技術;深海生物調査手法の現状)
著者等紹介
内藤敦[ナイトウアツシ]
三共株式会社
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。