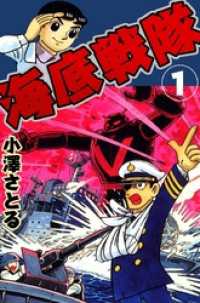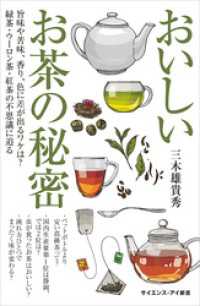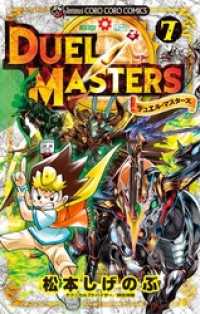出版社内容情報
執筆者一覧(執筆順)
太田 時男 横浜国立大学 学長(現・名誉教授)
大西 敬三 (株)日本製鋼所 代表取締役専務
兜森 俊樹 (株)日本製鋼所 室蘭研究所
(現)同・MSB推進室 水素エネルギー開発センター
田村 英雄 大阪大学 名誉教授 MH利用開発研究会会長
関矢 英士 (株)東芝 エネルギー事業本部
(現)東芝プラント建設(株) 電力事業部
酒井 貴史 三洋電機(株) ソフトエナジー事業本部
米津 育郎 三洋電機(株) 研究開発本部
(現)同・研究開発本部 ニューマテリアル研究所
大隅 正人 三洋電機(株) 研究開発本部
竹田 晴信 (株)日本製鋼所 室蘭研究所
(現)同・MSP推進本部 MSB推進室 水素エネルギー開発センター
脇坂 裕一 (株)日本製鋼所 室蘭研究所
古川 修弘 三洋電機(株) ソフトエナジー事業本部
(現)古川研究所
新海 洋 富士電機(株) エネルギー事業本部
(現)新海技術士事務所
濱 純 工業技術院 機械技術研究所
(現)福岡県工業技術センター
伊福部 達 北海道大学 電子科学研究所 教授
佐々木忠之 茨城大学 教育学部 助教授
渡辺 国昭 富山大学 水素同位体機能研究センター 教授
(現)同・水素同位体科学研究センター 教授
曽我 和雄 北陸先端科学技術大学院大学 材料科学研究科
今村 速夫 山口大学 工学部 助教授
(現)同・工学部 教授
(所属は1994年1月時点。( )内は2001年12月現在)
構成および内容
序文 エネルギー・メディアとしての水素と吸蔵合金のプロスペクト 太田時男
第1章 水素吸蔵合金の開発の現状と将来展望 大西敬三・兜森俊樹
1.はじめに
2.水素吸蔵合金の分離
3.A2B型(CaFタイプ)合金
3.1 Mg2Ni系合金
3.2 Mg2Cu系合金
3.3 その他の合金
4.AB型合金
4.1 TiFe系合金
4.2 その他のAB合金
5.AB2型合金
5.1 TiCr2系合金
5.2 TiMn1,5系合金
5.3 ZrCr2系合金
5.4 ZrMn2系合金
5.5 ZrV2系合金
6.AB5型合金
6.1 CaNi5
6.2 LaNi5
6.3 MmNi5
7.非化合物型合金
7.1 V系BCC合金
7.2 その他のBCC合金
第2章 水素吸蔵合金の標準化の動向 田村英雄
1.はじめに
2.標準化への胎動
3.水素吸蔵合金関連標準制定の経緯
3.1 水素吸蔵合金用語(JIS・H70003)
3.2 水素吸蔵合金の圧力-組成等温線(PCT線)の測定法(JIS・H7201)
3.3 水素吸蔵合金の水素化速度試験法(JIS・H7202)
3.4 現在素案検討中の課題,その他
3.4.1 熱特性
(1)比熱・反応熱測定
(2)熱伝導度測定
3.4.2 寿命特性
3.5 ニッケル・水素電池用電極材料としての水素吸蔵合金評価方法の標準化
4.おわりに
第3章 水素吸蔵合金を用いた余剰電力の貯蔵 関矢英士
1.ガスタービンの蒸気噴射
2.ガスタービンの入り口空気冷却
3.水素圧力利用タービン
4.水素吸蔵合金を利用した二次電池
5.水素発生と水素燃料
第4章 熱利用材料の開発と冷凍システムへの応用 酒井貴史・米津育郎・大隅正人
1.はじめに
2.水素吸蔵合金の反応熱の応用原理
2.1 水素吸蔵合金の反応原理と温度レベルの対応
2.2 冷凍システムへの応用の可能性
2.3 冷凍システムの原理
3.熱利用水素吸蔵合金の開発
3.1 熱利用水素吸蔵合金開発に要求される特性と開発課題
3.2 中高温材料(100~200℃)
3.3 低温用材料(0~-20℃)
3.4 反応速度と寿命特性
3.4.1 反応速度
3.4.2 寿命特性
3.5 まとめ
4.冷凍システムへの応用例
4.1 冷凍システムの要素技術
4.2 試作冷凍システムの仕様
4.2.1 水素吸蔵合金容器
4.2.2 システム構成
4.2.3 運転特性
4.3 試作保冷システム(花の育成システム)
4.4 まとめ
5.おわりに
第5章 ヒートポンプを利用した冷暖房への応用 大西敬三・竹田晴信
1.はじめに
2.ヒートポンプに利用される水素吸蔵合金
3.水素吸蔵合金ヒートポンプの原理と特徴
3.1 熱駆動式MHヒートポンプ
3.2 コンプレッサ式ヒートポンプ
4.水素吸蔵合金ヒートポンプの実例
4.1 熱駆動式ヒートポンプ
4.1.1 試作機(POMAC-Ⅲ)
4.1.2 大型-胴式ヒートポンプ
4.2 コンプレッサ式ヒートポンプ
4.2.1 顕熱回収運転(山型運転)
4.2.2 出力および昇温幅の増大のための運転
4.2.3 熱交換器の電熱性能の影響
5.MHヒートポンプシステムの高効率化の検討
5.1 伝熱性能の改善
5.2 顕熱回収による成績係数の改善
5.3 実用MHコンプレッサ式ヒートポンプ
5.3.1 仕様合金量の低減
5.3.2 コンプレッサの必要吐出量の低減
5.3.3 安全制御システムの充実
5.4 多重効用型システム
6.冷凍システムへの適用
6.1 冷凍システム用低温作動合金
6.2 冷凍サイクルの検討
6.3 冷凍サイクルにおける冷凍発生
6.4 冷凍サイクルにおける課題
6.5 水素吸蔵合金冷凍システムへの期待
7.今後の展望
第6章 水素の精製・回収システム開発への応用 脇坂裕一・竹田晴彦
1.はじめに
2.高純度水素精製装置への応用
2.1 高純度水素への精製原理
2.2 高純度水素精製装置の開発実施例
2.2.1 国内における開発事例
2.2.2 海外における開発事例
3.混合ガスからの水素の回収システムへの応用
3.1 混合ガスからの水素の回収原理
3.2 水素回収システムの開発実施例
3.2.1 国内における開発実施例
3.2.2 海外における主な開発実施例
4.水素精製・回収システムにおける課題とその対策
4.1 水素吸蔵合金における課題
4.2 システム開発の課題
4.3 合金の被毒とその対策
4.4 合金の微粉化とその対策
4.5 装置の大型化および高圧処理
4.6 安全性・信頼性
5.今後の開発の展望
第7章 Ni・MH二次電池の開発への応用と実用化例 古川修弘
1.開発の背景
2.電池用水素吸蔵合金
3.原理
4.電池構造
5.電池構成
5.1 負極の高性能化
5.2 正極の高性能化
5.3 電池構成の高性能化
6.電池特性
7.おわりに
第8章 燃料電池の開発と水素吸蔵合金 新海 洋
1.はじめに
2.燃料電池による発電
3.燃料電池の原理と種類
3.1 歴史と基本原理
3.2 アルカリ形燃料電池(AFC)
3.3 固体高分子電解質形(PEFC)
3.4 リン酸形(PAFC)
3.5 溶融炭酸塩形(MCFC)
3.6 固体電解質形(SOFC)
4.燃料電池の特徴
5.リン酸形燃料電池
6.リン酸形燃料電池の構造
7.原燃料について
8.燃料ガスについて
9.水素吸蔵合金
10.改質装置について
11.発電装置として
12.おわりに
第9章 水素の動力利用技術開発の現状と展望 濱 純
1.はじめに
2.水素動力利用技術開発の動向
3.水素燃焼タービンの開発動向と課題
4.水素自動車の開発動向と課題
5.おわりに
第10章 水素吸蔵合金を利用したアクチュエーターの開発と応用 伊福部達・佐々木忠之
1.はじめに
2.MHアクチュエーターの特徴
3.MHアクチュエーターの原理
4.ピストン式MHアクチュエーター
4.1 構造
4.2 動作特性
5.ベローズ式MHアクチュエーター
5.1 構造
5.2 動作特性
6.油圧式MHアクチュエーター
6.1 構造
6.2 応用例と動作特性
7.ベローズ式MHアクチュエーターへの改良
7.1 構造
7.2 動作特性
8.ピストン型MHアクチュエーターの改良とその応用例
8.1 構造
8.2 動作特性と応用例
9.ベローズ型MHアクチュエーターの小型化と応用例
9.1 設計指針と構造
9.2 動作特性と応用例
10.MHアクチュエーターの展望と課題
第11章 水素同位体の精製・回収と同位体分離への応用 渡辺国昭
1.はじめに
2.水素同位体の精製・回収
2.1 水素同位体の精製・回収上の要件
2.2 不純物ガスの除去性能
2.3 水素同位体の精製・回収への応用例
2.3.1 ウランベッド
2.3.2 ウラン代替材料
3.水素同位体の分離/濃縮
3.1 同位体分離の要件
3.2 同位体効果の概略
3.2.1 熱力学的同位体効果
3.2.2 動力学論的同位体効果
3.3 水素化物生成に見られる同位体効果
3.3.1 熱力学的同位体効果
3.3.2 平衡分離係数
3.3.3 動力学論的同位体効果
3.4 同位体分離への応用例
3.4.1 加熱・冷却サイクル法
3.4.2 クロマトグラフ法
4.水素同位体の貯蔵・供給
4.1 水素同位体ガスの貯蔵・供給上の要件
4.2 水素同位体ガスの貯蔵・供給への応用例
4.2.1 ウランベッド
4.2.2 ウラン代替材料
5.水素吸蔵合金応用状の問題点
5.1 不純物ガス耐久性
5.2 貯蔵合金の不整化
5.3 トリチウムの崩壊/発熱
5.4 保守管理と廃棄物処理
第12章 合成触媒への応用技術 曽我和雄・今村速夫
1.はじめに
2.重合反応
2.1 オレフィンの重合
2.2 アセチレンの重合
2.3 ジエン化合物の重合
2.4 スチレンの重合
2.5 その他の重合
3.合成触媒反応
4.オレフィンと不飽和有機化合物の水素化反応
4.1 吸蔵水素を利用した水素化
4.2 気相水素を利用した水素化
5.一酸化炭素の水素化とアンモニア合成反応
6.脱水素反応
6.1 アルコール,シクロヘキサンを水素源にした新たな水素貯蔵法
6.2 水素貯蔵法への光照射の利用
7.骨格異性化反応
8.その他の反応
内容説明
かねてより新しい機能材料として注目されている水素吸蔵合金は、エネルギーの貯蔵、輸送、変換等の媒体として様々な研究が進められており、Ni水素電池の電極材料としての応用など、すでに実用化されているものもある。現在は、燃料電池自動車の水素タンクへの利用など、その研究はさらに発展を続けているが、基本的な技術、概念に変化はないと思われる。本書は学術的側面から応用技術まで網羅したもので、決定版たりうるものである。
目次
水素吸蔵合金の開発の現状と将来展望
水素吸蔵合金の標準化の動向
水素吸蔵合金を用いた余剰電力の貯蔵
熱利用材料の開発と冷凍システムへの応用
ヒートポンプを利用した冷暖房への応用
水素の精製・回収システム開発への応用
Ni・MH二次電池の開発への応用と実用化例
燃料電池の開発と水素吸蔵合金
水素の動力利用技術開発の現状と展望
水素吸蔵合金を利用したアクチュエーターの開発と応用
水素同位体の精製・回収と同位体分離への応用
合成触媒への応用技術
著者等紹介
大西敬三[オオニシケイゾウ]
(株)日本製鋼所代表取締役専務
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。