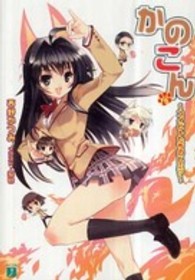出版社内容情報
☆主要コーティング用添加剤17種類の開発動向を網羅!
☆環境対応型コーティングから求められる添加剤への課題を詳述!
☆添加剤メーカーの主要製品一覧も掲載!
執筆者一覧(執筆順)
飯塚 義雄 楠本化成(株) 研究所
坪田 実 職業能力開発総合大学校 造形工学科
長沼 桂 楠本化成(株) 研究所
上原 孝夫 楠本化成(株) 研究所
柳澤 秀好 信越化学工業(株) シリコーン電子材料技術研究所
岡安 寿明 味の素ファインテクノ(株) 機能化学品事業部
桐生 春雄 桐生技術士事務所
吉川 和美 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所
本間 利男 水澤化学工業(株) 研究開発部
田中丸 眞 ダイソー(株) 住設事業部
毛利喜代美 日東化成(株) 化成品事業部
西沢 仁 西沢技術研究所
中山 雍晴 千葉工業大学
武田 進 武田技術士事業所
中道 敏彦 日油商事(株) 塗装営業本部
中嶋 純 京テクコンサルタント
構成および内容
第1章 総論 飯塚 義雄
1 はじめに
2 添加剤の種類と機能
3 Solubility Parameter(S.P)の測定法
3.1 蒸発熱法
3.2 物理定数によるHildebrand法
3.3 分子構造から推定する方法
3.4 S.Pと実際
4 高分子の吸着とそれによってみられる分散・凝集・応用
4.1 高分子の固体表面への吸着と凝集・分散作用
5 湿潤・分散剤の作用
6 おわりに
第2章 塗料の流動性と塗膜形成 坪田 実
1 塗料の流動性
1.1 塗料の構成
1.2 流れるという現象
1.3 粘性と弾性の違い
1.4 流動の種類
1.5 降伏値について
2 塗装時に必要な塗料の粘弾性
2.1 粘弾性体の挙動
2.2 ずり速度の推定
2.3 塗面の平滑性
第3章 溶液性状改善用添加剤
1 湿潤・分散剤 長沼 桂
1.1 はじめに
1.2 分散系の相互作用
1.2.1 疎水性粉体の濡れ性
1.2.2 粒子表面の酸・塩基特性
1.3 界面活性物質と湿潤・分散剤
1.3.1 湿潤・分散剤の分類
1.3.2 高分子湿潤・分散剤の特徴
1.4 分散剤の作用
1.5 分散剤の効果
1.5.1 カーボンブラックに対する分散効果
1.5.2 顔料粒子の電荷制御効果
1.6 おわりに
2 皮張り防止剤 飯塚 義雄
2.1 はじめに
2.2 皮張り防止剤の機能
2.3 皮張り防止剤の種類
2.4 顔料と皮張り防止剤(オキシム系)の関係
3 揺変剤(増粘剤、沈降防止剤、タレ防止剤) 飯塚 義雄
3.1 はじめに 53
3.2 塗料の粘性について
3.2.1 流動の形式
3.2.2 塗料の流動性質
3.3 塗料特性に与える揺変剤の効果
3.4 揺変剤による塗料流動性質の変化の一例
3.5 揺変剤の種類
3.5.1 非水系揺変剤
3.5.2 水系揺変剤
3.6 おわりに
4 消泡剤 上原 孝夫
4.1 はじめに
4.2 消泡剤の分類
4.3 泡の性質
4.4 消泡剤の効果
4.4.1 抑泡剤
4.4.2 破泡剤
4.4.3 溶泡剤
4.5 おわりに
5 色分かれ防止剤 長沼 桂
5.1 はじめに
5.2 色分かれ現象
5.3 色分かれ現象の原因
5.3.1 色浮きの原因
5.3.2 色むらの原因
5.4 色分かれ防止剤
5.5 色分かれ防止剤の効果
5.6 おわりに
6 平滑剤(レベリング剤) 上原 孝夫
6.1 はじめに
6.2 平滑剤の分類
6.3 平滑剤の理論
6.4 平滑剤の作用と効果
6.4.1 被塗物へのヌレの改良
6.4.2 熱対流(Benard cells)の防止
6.5 結論
6.6 おわりに
7 カップリング剤
7.1 シラン系カップリング剤 柳澤 秀好
7.1.1 シランカップリング剤の構造と特徴
7.1.2 無機材料に対する作用機構
7.1.3 シラノール基の安定性
7.1.4 シランカップリング剤の開発動向
7.2 チタネート系カップリング剤 岡安 寿明
7.2.1 はじめに
7.2.2 製法、一般性状
7.2.3 物性および機能
7.2.4 フィラー、顔料の処理方法
7.2.5 カップリング剤の添加量
7.2.6 応用例
7.2.7 用途
7.2.8 アルミネート系カップリング剤
第4章 塗膜性能改善用添加剤
1 防錆剤 桐生 春雄
1.1 はじめに
1.2 インヒビター(腐食抑制剤)としての防錆剤
1.3 防錆剤としての防錆顔料
1.4 代表的な防錆顔料
1.5 おわりに
2 光安定剤・酸化防止剤 吉川 和美
2.1 はじめに
2.2 光安定剤
2.2.1 紫外線吸収剤(UVA)
2.2.2 ヒンダードアミン系光安定剤(HALS)
2.3 酸化防止剤
2.3.1 リン系酸化防止剤
2.3.2 その他の酸化防止剤
2.4 おわりに
3 スリップ剤・スリ傷防止剤 飯塚 義雄
3.1 はじめに
3.2 摩擦係数の測定
3.3 滑剤の種類
3.4 代表的なスリップ剤・スリ傷防止剤
3.4.1 天然ワックス
3.4.2 合成ワックス
3.4.3 シリコーン系
3.5 スリップ剤・スリ傷防止剤の作用メカニズム
3.6 おわりに
4 つや消し剤 本間 利男
4.1 はじめに
4.2 非晶質シリカの分類
4.3 「ミズカシル」の物性と特徴
4.4 つや消し性能とシリカ物性
4.5 おわりに
5 ドライヤー 桐生 春雄
5.1 はじめに
5.2 ドライヤーの作用機構
5.3 ドライヤーと金属
5.4 各種塗料とドライヤーの性状の関係
5.5 ドライヤーと各種油脂の関係
5.6 水溶性塗料用ドライヤー
5.7 おわりに
6 硬化触媒 桐生 春雄
6.1 はじめに
6.2 塗料系の合成樹脂ポリマーの基本構造と架橋反応の形態
6.3 エポキシ樹脂塗料と硬化触媒
6.4 ウレタン塗料と硬化触媒
6.5 おわりに
第5章 機能性付与を目的とした添加剤
1 抗菌・防カビ剤 田中丸 眞
1.1 はじめに
1.2 抗菌・防カビ剤の定義
1.3 抗菌・防カビ剤の開発
1.4 塗料での抗菌防カビ性能の必要性
1.5 理想的な抗菌・防カビ剤の条件
1.6 おわりに
2 防汚剤 毛利喜代美
2.1 はじめに
2.2 海洋付着生物
2.3 汚損生物による被害
2.4 防汚塗料
2.5 防汚塗料の機能
2.6 防汚塗料の種類
2.7 新規加水分解型ポリマー
2.8 評価法
2.9 おわりに
3 難燃剤 西沢 仁
3.1 はじめに
3.2 環境対応型難燃剤の種類と新しい研究の動向
3.3 おわりに
第6章 環境対応型コーティングに求められる機能と課題
1 水性塗料 中山 雍晴
1.1 常温架橋型1液水性塗料
1.1.1 自己乳化したアルキド樹脂エマルションをバインダーとする1液常乾水性塗料
1.1.2 界面活性剤を使用して分散したアルキド樹脂エマルションをバインダーとする1液常乾水性塗料
1.2 常温架橋型2液水性塗料
1.2.1 イソシアネイト基で架橋する塗料
1.2.2 エポキシ基で架橋する塗料
1.3 加熱乾燥型水性塗料
1.3.1 一般工業用水性塗料
1.3.2 水性メタリックベースコート
1.3.3 電着塗料
2 粉体塗料 武田 進
2.1 はじめに
2.2 製造工程
2.2.1 プレミキシング
2.2.2 エクストルーダー
2.2.3 粉砕
2.3 粉体塗装
2.3.1 塗料の供給
2.3.2 静電粉体塗装
2.3.3 オーバースプレイ粉の回収
2.4 塗膜
2.4.1 塗膜形成時のハジキ、ピンホール防止用添加剤
2.4.2 塗膜の平滑性、ユズ肌、鮮映性
2.5 粉体塗料の今後の課題
2.5.1 隠蔽力向上
2.5.2 高耐候性粉体塗料
2.5.3 脱ガス剤
2.5.4 変わり塗り用添加剤
2.5.5 艶消し剤
2.6 おわりに
3 ハイソリッド塗料 中道 敏彦
3.1 はじめに
3.2 硬化触媒
3.2.1 メラミン樹脂硬化システムと酸触媒
3.2.2 その他の硬化システムと触媒
3.3 レオロジーコントロール剤(RCA)
3.3.1 HS塗料におけるたれとRCA
3.3.2 RCAとしてのNAD、MG
3.4 その他の添加剤
3.4.1 耐候性
3.4.2 その他の留意点
3.5 おわりに
4 エマルション塗料 中嶋 純
4.1 はじめに
4.2 エマルション塗料と添加剤
4.2.1 エマルション塗料
4.2.2 添加剤の選択
4.3 環境面から見たエマルション塗料
4.3.1 エマルション塗料の優位性
4.3.2 ISO関連規格
4.3.3 浮遊粒子状物質
4.3.4 内分泌撹乱化学物質(通称環境ホルモン)の規制
4.4 エマルション塗料と環境
4.4.1 エマルション塗料の自主規制
4.4.2 その他
4.5 エマルション塗料の機能について
4.5.1 その問題点
4.5.2 今後のエマルション塗料としての要件
付表 塗料添加剤製品一覧
内容説明
本書は、基礎的内容として「流動性と塗膜形成」の章を設け、各論として17種類のコーティング添加剤の開発の動向をまとめている。さらに環境対応型コーティングから見た添加剤への課題についても触れ、参考資料として添加剤各メーカーより販売されている製品一覧も掲載した。
目次
第1章 総論
第2章 塗料の流動性と塗膜形成
第3章 溶液性状改善用添加剤
第4章 塗膜性能改善用添加剤
第5章 機能性付与を目的とした添加剤
第6章 環境対応型コーティングに求められる機能と課題
著者等紹介
桐生春雄[キリュウハルオ]
桐生技術士事務所所長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。