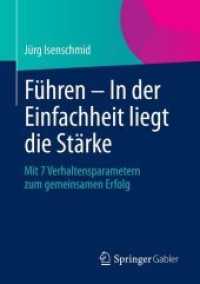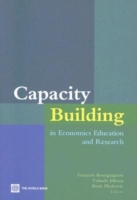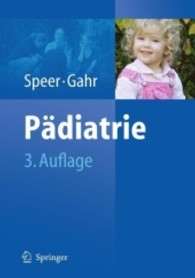出版社内容情報
★「微生物」,「アレルギー」,「化学物質」,「異物混入」と食品製造におけるリスク別に,現状,検査技術の動向,リスク回避のための技術を詳述しています。
★「トレーサビリティ」における現状,技術,事例も掲載しています。
--------------------------------------------------------------------------------
食品の危害因子を科学的に証明するためには微生物学的,理化学的検査技術がなくてはならない。安全性評価のためには国際的に容認される検査技術が要求され,国内では国際的なレベルの公定法や標準法が食品衛生検査指針に示されている。さらには,より迅速な簡易な微生物学的,理化学的検査法の開発や新たな検査技術も報告されてきた。
本書ではこれらのことを踏まえて,食品の安全性を巡る動向や食品検査をはじめとするリスク回避技術の現状と展望についてそれぞれの専門分野の研究者や実務者が執筆をしており,食品産業界に少しでも貢献出来ることを切望するものである。
伊藤武
--------------------------------------------------------------------------------
編集委員(五十音順)
伊藤武 (財)東京顕微鏡院 食と環境の科学センター 所長
川本伸一 (独)食品総合研究所 企画調整部 食品衛生対策チーム チーム長
杉山純一 (独)食品総合研究所 食品工学部 電磁波情報工学室 室長
西島基弘 実践女子大学 生活科学部 食生活科学科 教授
米谷民雄 国立医薬品食品衛生研究所 食品部 部長
執筆者一覧(執筆順)
一色賢司 内閣府 食品安全委員会 事務局 次長
横山理雄 石川県農業短期大学(石川県立大学) 名誉教授
日野明寛 (独)食品総合研究所 企画調整部 GMO検知解析チーム チーム長
有馬和英 (財)東京顕微鏡院 食と環境の科学センター 食品安全部 技術主幹
中野宏幸 広島大学大学院 生物圏科学研究科 教授
矢野俊博 石川県立大学 生物資源環境学部 食品科学科 教授
五十部誠一郎 (独)食品総合研究所 食品工学部 製造工学研究室 室長
寺本忠司 (株)ファルコライフサイエンス 取締役
遠藤明彦 (財)東京顕微鏡院 食と環境の科学センター 調査研究部 技術参与
河合高生 大阪府立公衆衛生研究所 感染症部 細菌課 主任研究員
浅尾 努 大阪府立公衆衛生研究所 感染症部 細菌課 主任研究員
近藤直実 岐阜大学 大学院医学研究科 小児病態学 教授
桑原愛美 岐阜大学 大学院医学研究科 小児病態学
森山達哉 近畿大学 農学部 応用生命化学科 応用細胞生命学研究室 講師
小川 正 関西福祉科学大学 福祉栄養学科 教授
豊田正武 実践女子大学 生活科学部 教授
穐山 浩 国立医薬品食品衛生研究所 食品部 室長
橘田和美 (独)食品総合研究所 企画調整部 食品衛生対策チーム 主任研究官
山本(前田)万里 (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 野菜茶業研究所 機能解析部 茶機能解析研究室 研究室長
永山敏廣 東京都健康安全研究センター 多摩支所 理化学研究科 科長
堀江正一 埼玉県衛生研究所 水・食品担当 部長
長岡(浜野)恵 国立医薬品食品衛生研究所 環境衛生化学部 主任研究官
古賀秀徳 カルビー(株) R&Dグループ R&DDEセンター 基礎研究1チーム チームリーダー
野口玉雄 (財)日本冷凍食品検査協会 技術顧問
村上りつ子 茨城県衛生研究所 理化学部 首席研究員兼部長
牛山博文 東京都健康安全研究センター 食品化学部 食品成分研究科 主任研究員
安田和男 東京都健康安全研究センター 食品化学部 部長
高鳥浩介 国立医薬品食品衛生研究所 衛生微生物部 部長
小菅旬子 宮崎大学 農学部 講師
伊藤誉志男 (財)日本食品分析センター 化学分析部 学術顧問
田口信夫 東京都健康安全研究センター 食品化学部 課長補佐
小田祐一 キリンビバレッジ(株) 開発研究所 開発推進担当 主任
山内啓正 サントリー(株) 品質保証部 安全性科学センター 主任研究員
石郷岡博 サントリー(株) 品質保証部 安全性科学センター 主任研究員
白石裕雄 (株)サトー ソリューション営業部 部長
櫻井サチコ (株)インフォマート 経営企画室 室長
高山 勇 キユーピー(株) 生産本部 技術企画担当部長 主席技術員
--------------------------------------------------------------------------------
目次
【第I編 総論】
第1章 食品の安全性を巡る最新の話題(一色賢司)
1. 63億人の消費者
2. 食品安全基本法と食品安全委員会
3. 食品とリスク分析
4. フードチェーン・アプローチ
5. 食品のリスク評価をめぐる動き
6. 有害微生物対策
7. 有害物質対策
8. 次世代のために
第2章 食品の安全戦略と包装の動き(横山理雄)
1. はじめに
2. なぜ,食品の安全戦略が必要か
2.1 食品の安全戦略とは
2.2 食品の安全戦略の立案と実施
3. 食品の安全を脅かす要因と対策
3.1 食品の安全を脅かす要因
3.2 食品安全対策
4. 食中毒防止のレトルト殺菌包装
4.1 食中毒菌を含めた病因物質
4.2 食品の包装技法
4.3 レトルト食品とは
4.4 レトルト食品の包装材料
5. 安全を重視した無菌包装
5.1 無菌包装食品の種類
5.2 新しい無菌充填包装食品
5.3 高齢者向け無菌化包装食品
第3章 遺伝子組換え作物と食品検査(日野明寛)
1. はじめに
2. 遺伝子組換え体の安全性
2.1 食品の「安全性」とは
2.2 リスクとの付き合い方
2.3 組換え体の安全性評価
3. 表示制度の導入と監視
4. 遺伝子組換え農産物の検査法
4.1 わが国の標準分析法
4.2 抗体を用いた組換え遺伝子由来のタンパク質の検知
5. 安全性審査未了の組換え農産物の検知
6. 国際情勢
7. おわりに
【第II編 微生物性食中毒】(編集:伊藤武)
第1章 わが国における食中毒発生動向(伊藤武,有馬和英)
1. はじめに
2. 食中毒の発生状況
3. 食中毒危害微生物
4. 少量菌感染を起こす病原微生物
5. 微生物による食中毒の発生状況
6. 食中毒による死者数
7. 大規模食中毒の発生動向
8. 原因施設
9. 原因食品
10. 微生物による食中毒が変貌してきた要因
11. 食品の安全性確保とHACCPによる衛生管理
12. おわりに
第2章 食中毒リスク回避のための微生物制御の基礎(中野宏幸)
1. 食品の微生物制御
2. 食品と微生物
3. 加熱
4. 冷殺菌
5. 冷蔵・冷凍
6. 乾燥および水分活性(Aw)
7. pH(水素イオン濃度)
8. 食品添加物
9. 食品包装技術
10. ハードル理論
第3章 微生物による食中毒リスク回避の技術
1. 食品産業における環境殺菌剤(矢野俊博)
1.1 はじめに
1.2 紫外線
1.3 エチルアルコール
1.4 次亜塩素酸
1.5 オゾン
2. 非加熱処理による殺菌技術(五十部誠一郎)
2.1 はじめに
2.2 非加熱操作の特徴
2.3 非加熱操作の食品微生物制御への導入可能性
2.4 表4に記載していない非加熱殺菌処理
2.4.1 ガスの溶解処理の特徴
2.4.2 ミクロバブル超臨界二酸化炭素法
2.4.3 貯蔵雰囲気の気体中の加圧処理での殺虫処理
2.5 おわりに
第4章 微生物・ウイルス検査技術(伊藤武)
1. はじめに
2. 食品微生物検査指針の変遷
3. 公定法(告示・通知)による微生物検査
4. 公定法による汚染指標細菌の検査
5. 公定法・標準法による主な食品病原微生物検査の概略
5.1 黄色ブドウ球菌
5.2 サルモネラ
5.3 腸管出血性大腸菌(志賀毒素産生大腸菌またはベロ毒素産生大腸菌)O157
5.4 腸炎ビブリオ
5.5 カンピロバクター
5.6 食品媒介ウイルスの検査
6. 自主検査と公定法による検査
7. おわりに
第5章 実用化されている簡便・迅速検査技術
1. 指標細菌の簡易・迅速微生物検査技術(寺本忠司)
1.1 はじめに
1.2 指標細菌
1.3 食品細菌検査法
1.3.1 生菌数測定
1.3.2 大腸菌群数測定
1.3.3 自主食品細菌検査
1.4 簡易検査法
1.4.1 ペトリフイルム法
1.4.2 サニ太くん
1.4.3 コンパクトドライ
1.4.4 シンプレート
1.4.5 HGMF法(Hydrophobic Grid Membrane Filter)
1.5 迅速細菌検査法
1.5.1 簡易検査キット
1.5.2 自動細菌数測定法
2. 酵素基質培地とその応用(遠藤明彦)
2.1 はじめに
2.2 酵素基質培地
2.3 主な酵素基質の特徴と特性
2.4 食品中および水中の微生物検査への応用
2.5 おわりに
3. 食中毒病原菌の免疫学的検査技術(伊藤武)
3.1 はじめに
3.2 沈降反応(免疫拡散法)によるサルモネラ検出法(1-2test)
3.3 酵素抗体法
3.4 イムノクロマト法
3.5 自動機器によるELISA法
3.6 サルモネラの免疫学的検出法
3.7 腸管出血性大腸菌O157検出法
3.8 その他の病原菌
3.9 おわりに
4. 食中毒菌の遺伝学的試験法(河合高生,浅尾努)
4.1 はじめに
4.2 Polymerase Chain Reaction(PCR)法
4.2.1 原理と利用法
4.2.2 PCR法の応用
4.2.3 毒素遺伝子に関する最近の知見(セレウス菌および黄色ブドウ球菌)
4.3 Loop-Mediated Isothermal Amplification(LAMP)法
4.4 Transcription-Reverse Transcription Concerted Reaction(TRC)法
4.5 DNAプローブ法
【第III編 アレルギー】(編集:川本伸一)
第1章 食物アレルギーの発症機序と治療・予防(近藤直実,桑原愛美)
1. はじめに
2. 食物アレルギー臨床
3. 食物アレルギーの発症機序
3.1 食物アレルギーの発症機序の概要
3.2 食物アレルギーの発症機序に関する筆者らの成績
3.2.1 抗原認識機構-構造プロテオミックスを含めて-
3.2.2 ヘルパーT細胞のTh1とTh2とそのアンバランスと症状発現
4. 発症機序解明に基づく食物アレルギーの診断法
4.1 各免疫アレルギー学的検査の意義
4.2 食物アレルギーの診断法の実際と手順
5. 食物アレルギーの治療・予防
5.1 除去食療法の適応の考え方
5.2 経口免疫寛容とその発現機序
5.3 ヒトにおける経口免疫寛容現象と食物アレルギーの治療・予防への応用
第2章 食品のアレルゲン性評価の研究動向(森山達哉,小川正)
1. はじめに
2. 食物アレルゲンの概要
3. 食物アレルゲンの同定・検出方法
3.1 医師による問診・臨床検査
3.2 アレルゲンタンパク質の同定-電気泳動・イムノブロッティング法
3.3 アレルゲンタンパク質の同定-クロマトグラフィー・ELISA法
3.4 既知のアレルゲン分子を検出・定量する場合
3.5 アレルゲンタンパク質の同定に際しての注意点
4. アレルゲンデータベース
5. 新規タンパク質のアレルゲン性評価
5.1 食品安全委員会のガイドライン
5.2 アレルゲン性評価の実証方法について
6. 細胞や動物を用いたアレルゲン性の評価
第3章 食品のアレルギー検査技術-公定法や迅速検査技術の開発状況や動向について(豊田正武,穐山浩)
1. はじめに
2. 厚生労働省の通知検査法
2.1 通知検査法の概要
2.2 標準品
2.3 検査原則及び試料調製法
2.4 ELISA法
2.5 ウエスタンブロット法による検査方法
2.6 PCR法による検査方法
2.7 判断樹
3. 簡易測定法
4. ヒト血清を用いた検出法
5. 特定原材料以外の検査法の開発動向
第4章 アレルギー食品の表示問題-国内事情と国際動向について-(橘田和美)
1. はじめに
2. アレルギー物質を含む食品の表示
2.1 表示制度施行の経緯
2.2 表示法概要
2.2.1 表示対象食品範囲と表示の免除
2.2.2 特定原材料等の品名及び範囲
2.2.3 アレルギー表示方法
2.2.4 代替表記
2.2.5 表示を要する量
2.2.6 コンタミネーションへの対応
2.2.7 食品衛生法における取り扱い
3. 見直し事項および課題
3.1 対象品目
3.2 コンタミネーション防止
3.3 特定原材料等不使用の表示促進
3.4 分かりやすい表示
3.5 制度の普及・啓発,研究促進
4. 諸外国の対応
4.1 コーデックス
4.2 オーストラリア・ニュージーランド
4.3 韓国
4.4 欧州連合(EU)
4.5 米国
4.6 カナダ
5. おわりに
第5章 抗アレルギー食品の開発(山本(前田)万里)
1. アレルギー発症の機序
2. 抗アレルギー食品素材の開発
3. お茶(Camellia sinensis L.)について
4. 茶葉中抗アレルギー物質の探索
5. ヒトへの応用
【第IV編 化学物質】(編集:米谷民雄,西島基弘)
第1章 化学的リスク総論(米谷民雄)
1. はじめに
2. ハザードとリスクの違い
3. コーデックスの動き
4. リスク分析の手法
4.1 リスク評価
4.2 リスク管理
4.3 リスクコミュニケーション
5. 健康食品問題
第2章 残留農薬(検査法,部位別濃度,違反事例,残留実態,調理の影響,低減法)(永山敏廣)
1. 食品中残留農薬の規制
2. 食品中残留農薬の検査法
3. 食品中の農薬残留実態
4. 残留農薬の部位別濃度
5. 調理加工に伴う挙動
6. 農産物中の残留農薬量を減らす
7. 農薬の摂取量
第3章 残留動物薬(堀江正一)
1. はじめに
2. 動物用医薬品・飼料添加物
3. 食品衛生法による残留規制
4. 動物用医薬品の残留基準値設定プロセス
5. ポジティブリスト制の導入
6. Codex及び諸外国における残留規制の現状
7. 残留分析法の現状と開発の方向性
8. 最近の薬物残留事例
9. 薬剤耐性菌出現の問題
第4章 有害金属(米谷民雄,長岡(浜野)恵)
1. はじめに
2. 金属分析法における最近の進歩
2.1 ICP-AES
2.2 ICP-AESにおけるCIDやCCDの採用
2.3 ICP-MS
2.4 ICP-MSにおける同重体干渉の除去
2.5 SpeciationとHyphenated technique
3. 食品衛生における各有害金属の課題
3.1 ヒ素
3.2 水銀
3.3 カドミウム
3.4 鉛
4. 点検・汚染防止の方法
第5章 アクリルアミドの分析法,実体,低減法(古賀秀徳)
1. はじめに
2. 食品中のアクリルアミドの分析法
3. 食品中のアクリルアミド含有率
4. 加工食品中のアクリルアミドの低減法
4.1 前駆物質低減
4.2 生成反応阻害条件
4.3 生成阻害成分の添加
5. おわりに
第6章 天然毒
1. 動物性自然毒 (野口玉雄,村上りつ子)
1.1 はじめに
1.2 主なマリントキシン
1.2.1 フグ毒(Tetrodotoxin: TTX)
1.2.2 シガテラ毒
1.2.3 麻痺性貝毒(Paralytic shellfish poison: PSP)
1.2.4 下痢性貝毒(diarrhetic shellfish poison: DSP)
1.2.5 記憶喪失性貝毒(amnesic shellfish poison: ASP)
1.2.6 バイの毒
1.2.7 テトラミン
1.2.8 フェオフォルバイオトaおよびピロフェオフォルバイオa
1.3 中毒予防
1.4 マリントキシンの検出法
1.5 おわりに
2. 植物性自然毒(牛山博文,安田和男)
2.1 はじめに
2.2 アコニチン
2.3 ベラトルムアルカロイド
2.4 アトロピン,スコポラミン
2.5 ソラニン,チャコニン
2.6 リコリン
2.7 4-O-メチルピリドキシン
2.8 アマニチン
2.9 シロシビン,シロシン
2.10 おわりに
3. カビとカビ毒(高鳥浩介,小菅旬子)
3.1 食品のカビ被害
3.2 カビによる食品汚染とカビ毒の規制
3.3 カビとカビ毒の検査法
3.3.1 食品中のカビの検出
3.3.2 食品中のカビ毒の検出
3.4 カビとカビ毒を巡る食品安全管理のポイント
第7章 食品添加物(最近の動向,違反事例,検査法)(伊藤誉志男)
1. はじめに
2. 最近の動向
2.1 規格基準の整備
2.2 安全性の再評価
2.3 第8版食品添加物公定書の作製作業
2.4 日本人の食品添加物1人1日摂取量調査研究
2.5 消費者の不安感
3. 違反事例の大区分とそれからの防止策
3.1 輸出国で許可,日本で不許可の指定外添加物の使用(食品衛生法第10条違反)
3.2 使用基準量以上の過量使用(食品衛生法第11条違反)
3.3 対象外食品への使用(食品衛生法第11条違反)
3.4 表示違反
3.5 違反添加物の使用
4. 検査法での注意点
4.1 検査法の構成
4.2 検査法および検査機器の驚異的な進歩
4.3 食品中での食品常成分と食品添加物の結合(亜硫酸)
4.4 高感度化の必要性(過酸化水素)
4.5 検査操作中に食品成分が分解し違反添加物を生成(二硫化炭素)
4.6 食品中の種々の食品添加物の検査法について
【第V編 異物混入】(編集:西島基弘)
第1章 異物混入対策(田口信夫,西島基弘)
1. はじめに
2. 異物の種類
3. 異物の混入時期及び混入しやすい異物
4. 東京都(保健所)に届けられた食品の苦情
5. 食品から検出された異物の同定方法
5.1 情報収集
5.2 外観等の形態観察
5.3 機器分析
5.4 物理・化学・生物学的試験
6. 異物検査の実例
6.1 フルーツゼリーから毛が出てきた
6.2 パンからコンクリートの破片が出てきた
7. 異物混入防止対策
第2章 顧客責任による異物混入クレームと取り組み
1. RNA法による昆虫混入時期特定(小田祐一)
1.1 はじめに
1.2 カタラーゼテスト(汎用法)
1.3 RNA法の着眼点
1.4 RNA法
1.4.1 試料と方法
1.4.2 結果及び考察
2. 野菜色素体ゲノム情報のデータベース化と今後の課題及び唾液アミラーゼの免疫学的分析(山内啓正,石郷岡博)
2.1 野菜色素体ゲノム情報のデータベース化と今後の課題
2.1.1 はじめに
2.1.2 方法
2.1.3 結果と考察
2.1.4 まとめ
2.1.5 今後の課題
2.2 唾液アミラーゼの免疫学的分析
2.2.1 はじめに
2.2.2 方法
2.2.3 結果
2.2.4 まとめ
【第VI編 トレーサビリティ】(編集:杉山純一)
第1章 安心と信頼確保のためのトレーサビリティ(杉山純一)
1. トレーサビリティーとは
2. 食品に必要な実用トレーサビリティとは
3. SARSに学ぶ
4. トレーサビリティの構築手順
5. 識別子の分類
6. 第三者認証
7. 青果ネットカタログ「SEICA」
8. SEICAにおける信頼性確保
9. その他の信頼性確保手法
10. インフラとしてのSEICAの民間活用
11. 今後の展開
第2章 表示するバーコードと,その印字方法(白石裕雄)
1. トレーサビリティシステムとバーコード
2. バーコードを利用したトレーサビリティ市場例(メディカル市場)
3. バーコード表示の方法
4. 熱転写式と感熱式の違い
5. プリンタ
6. トレーサビリティのメーカーメリット
第3章 食業界における情報共有システム[FOODS信頼ネット]の事例(櫻井サチコ)
1. 食の「安心・安全」への取組みに応える~FOODS信頼ネット~の誕生
2. 食業界における「安心・安全」確保に対する取組みからの気付き
3. 「安全・安心」にかかるコスト増と業務過多
4. 食業界全体で効率良く取組める仕組みへのニーズ
5. 業界標準となりえる仕組みを目指して
6. 業界プレイヤーの意見を取り入れた「FOODS信頼ネット」の構築
7. 情報管理と公開レベルに対して
8. 商品規格書をデータベース化するメリット
9. 業界ニーズから生まれた仕組みを多くの企業様へ・・・
第4章 原料メーカー,加工食品メーカー間の履歴情報遡及(高山勇)
1. まえがき
2. FA(ファクトリーオートメション)について
2.1 パートさんの一言から誕生した小分け配合事故未然防止システム
2.1.1 開発までの経緯
2.1.2 システムの内容
2.2 抜けの無いチェックを目指した工程管理システム
2.2.1 開発までの経緯
2.2.2 システムの内容
2.3 事故未然防止から生まれたトレーサビリティシステム
2.3.1 開発までの経緯
2.3.2 システムの内容
2.3.3 ポイント
3. 加工食品のトレーサビリティについて
3.1 加工工程の流れ
3.2 トレースバック
3.3 トラッキング
3.4 加工現場の改善
4. コードの標準化
4.1 自社での二次元コードの開発
4.2 標準化への検討会
4.3 EAN/UCC標準のコード体系の採用
4.4 ガイドラインの発行
5. 原材料から製品出荷先までの一環したシステムのモデル構築
5.1 第Ⅱ期食品トレーサビリティ研究会の発足
5.2 システムの概要
5.3 野菜の生産情報
5.3.1 野菜処理,加工会社の説明
5.3.2 実証試験のシステム構成
5.3.3 公的機関との連動
5.3.4 他の野菜原料のシステム
5.4 配送先のシステム
5.5 物流メーカーでのシステム構築
5.6 データセンタでの管理
6. あとがき
目次
第1編 総論
第2編 微生物性食中毒
第3編 アレルギー
第4編 化学物質
第5編 異物混入
第6編 トレーサビリティ
著者等紹介
伊藤武[イトウタケシ]
(財)東京顕微鏡院食と環境の科学センター所長
川本伸一[カワモトシンイチ]
(独)食品総合研究所企画調整部食品衛生対策チームチーム長
杉山純一[スギヤマジュンイチ]
(独)食品総合研究所食品工学部電磁波情報工学研究室研究室長
西島基弘[ニシジマモトヒロ]
実践女子大学生活科学部食生活科学科教授
米谷民雄[マイタニタミオ]
国立医薬品食品衛生研究所食品部部長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。