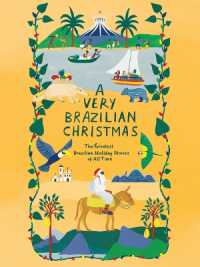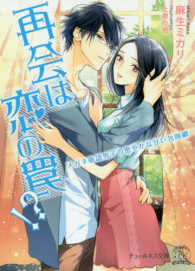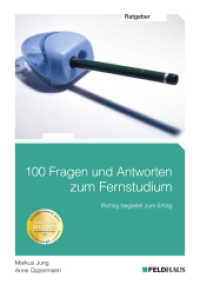出版社内容情報
★電力貯蔵技術とパワーエレクトロニクスについて,原理・最新技術・開発動向を網羅!
★電力の負荷平準化用途をはじめ,自然エネルギーへの活用など豊富な事例も詳述!
--------------------------------------------------------------------------------
本書は,電池電力貯蔵に力点をおいて,ナトリウム硫黄電池,レドックスフロー電池,シール鉛電池,リチウムイオン電池,電気二重層キャパシターを取り上げ,原理・構造,開発動向,導入例を詳述している。また,フライホイール,超伝導コイルよる電力貯蔵についても同じく解説している。電力貯蔵のほとんどが直流電源であるので,不可欠な技術として交直変換を主体としたパワーエレクトロニクス技術を紹介している。さらに,全体を見渡す観点から,電力貯蔵技術の開発動向と市場展望を概観している。
電力事業は世界的にみて規制緩和・再規制に向かっている。どのセクターにおいても自己責任が課せられる社会構造となるので,エネルギー流通の中の貯蔵は必須である。技術開発者,電気事業者,独立電気供給者,高度情報技術運営者,高度生産技術運用者等々には必読書であろう。この分野は今後とも拡大するものと展望できるので,本書はビジネス・モデルを構築するときにも参照されるべきものと信じるものである。
2006年2月 伊瀬敏史,田中祀捷
--------------------------------------------------------------------------------
監修者 伊瀬敏史 大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻 教授
田中祀捷 早稲田大学大学院 情報生産システム研究科 教授
執筆者一覧(執筆順) 大和田野芳郎 (独)産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門長
諸住哲 (株)三菱総合研究所 エネルギー研究本部 主席研究員
中林喬 日本ガイシ(株) 電力事業本部 NAS事業部 専門部長
小路剛史 関西電力(株) 研究開発室 エネルギー利用技術研究所 商品開発研究室
辻川知伸 (株)エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ 研究開発本部 主任研究員
寺田信之 (財)電力中央研究所 材料科学研究所 材料物性・創製領域リーダー
杉本重幸 中部電力(株) 電力技術研究所 電力ネットワークグループ 系統チーム チームリーダー 研究主査
嶋田隆一 東京工業大学 統合研究院 ソリューション研究機構 教授
新冨孝和 日本大学 大学院総合科学研究科 教授
仁田旦三 東京大学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 教授
林秀美 九州電力(株) 総合研究所 電力貯蔵技術グループ グループ長
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 電力貯蔵技術の開発動向(大和田野芳郎)
1. 電力貯蔵技術の用途
2. 電力貯蔵技術の種類
3. 電力貯蔵技術の動向と将来
第2章 電力貯蔵技術の市場展望(諸住哲)
1. はじめに
2. 電力貯蔵の利用形態
2.1 負荷平準化
2.1.1 電力貯蔵の使い方
2.1.2 電力貯蔵技術の導入状況
2.2 系統安定化などでの利用
2.2.1 電力貯蔵の使い方
2.2.2 電力貯蔵技術の導入状況
2.3 自然エネルギーへの対応
2.3.1 電力貯蔵の使い方
2.3.2 電力貯蔵技術の導入状況
2.4 電気料金の時間帯差を利用した負荷シフト
2.4.1 電力貯蔵の使い方
2.4.2 電力貯蔵技術の導入状況
2.5 需要の変動に対する対応
2.5.1 電力貯蔵の使い方
2.5.2 電力貯蔵技術の導入状況
2.6 電力品質対策としての用途
2.6.1 電力貯蔵の使い方
2.6.2 電力貯蔵技術の導入状況
3. 電力貯蔵の市場展望
3.1 電気事業での電力貯蔵
3.2 電力自由化と電力貯蔵
3.3 自然エネルギーの導入と電力貯蔵
3.4 需要家側に設置される電力貯蔵
第3章 ナトリウム硫黄電池による電力貯蔵技術(中林喬)
1. はじめに
2. 原理および構造
2.1 ナトリウム硫黄電池の原理
2.2 固体電解質
2.3 動作温度
2.4 電圧
2.5 単電池の構造
2.6 モジュール電池の構造
2.7 ナトリウム硫黄電池システムの構成
3. 開発動向
3.1 開発の経緯
3.2 電気自動車用ナトリウム硫黄電池
3.3 電力貯蔵用ナトリウム硫黄電池
3.4 負荷平準システム
3.5 非常電源兼用システム
3.6 温室効果ガス(CO2)の削減
3.7 分散型電源等への応用
3.8 普及の促進
4. 導入事例
4.1 負荷平準用システムの事例
4.2 非常電源兼用システムの事例
4.3 瞬低対策兼用システムの事例
4.4 風力発電併設システムの事例
4.5 海外での事例
4.6 まとめ
第4章 レドックスフロー電池による電力貯蔵技術(小路剛史)
1. はじめに
2. 原理および構造
2.1 原理と構造
2.2 電池セルスタック
2.2.1 隔膜
2.2.2 電極
2.2.3 双極板
2.2.4 電解液
2.2.5 電解液タンク
2.2.6 その他設備
2.3 特徴
3. 開発動向
3.1 開発の経緯
3.1.1 鉄-クロム系レドックスフロー電池
3.1.2 全バナジウム系レドックスフロー電池
3.2 各機能
3.2.1 負荷平準化機能
3.2.2 瞬低補償機能・非常用電源機能
3.2.3 風力発電の出力平滑化機能
4. 導入例
4.1 100kWシステム(負荷平準化)(事務所ビル 2000年3月運転開始)
4.2 168kWシステム(負荷平準化)(関西電力(株) 巽実験センター 2001年1月運転開始)
4.3 1,500kWシステム(負荷平準化+瞬低補償)(液晶工場 2001年4月運転開始)
4.4 500kWシステム(負荷平準化)(大学 2001年7月運転開始)
4.5 120kWシステム(負荷平準化+消防非常用電源)(事務所ビル 2003年5月運転開始)
4.6 100kW級多機能型システム(負荷平準化+消防非常用電源+瞬低補償)(事務所ビル 2004年12月運転開始)
第5章 シール鉛蓄電池による電力貯蔵技術(辻川知伸)
1. はじめに
2. シール鉛蓄電池の原理とサイクル特性の改善
2.1 シール鉛蓄電池の原理
2.2 シール鉛蓄電池の構造材料
2.3 サイクル特性の改善
2.4 サイクル用シール鉛蓄電池の電気的特性
2.5 サイクル用シール鉛蓄電池の組電池構造
3. 電力貯蔵システムの構成とシステム運用
3.1 システム構成
3.2 構成要素
3.2.1 急速充電方法
3.2.2 システム監視装置
4. 課題と開発動向
4.1 電力貯蔵システムの課題
4.2 蓄電池長寿命化の動向(サイクル寿命)
4.3 適用領域拡大への動向
5. 導入例
5.1 インテリジェントビルへの導入例(UPSタイプ)
5.1.1 システム構成
5.1.2 試験データ
5.2 事務所ビルへの導入例(双方向タイプ)
6. まとめ
第6章 リチウムイオン電池による電力貯蔵技術(寺田信之)
1. はじめに
2. 原理および構造材料
2.1 正極
2.2 負極
2.3 電解質(電解溶液)
2.4 セパレータ
2.5 その他の材料
2.6 セル
2.7 モジュール・電池パック
3. 開発動向
3.1 日本における開発動向
3.2 欧米における開発動向
3.3 その他の地域
4. 導入例
4.1 運輸部門での電力貯蔵技術の導入
4.1.1 電気自動車
4.1.2 ハイブリッド電気自動車
4.1.3 電動スクーター
4.1.4 その他の乗り物
4.2 定置型電力貯蔵技術の導入
4.2.1 日立製作所/新神戸電機
4.2.2 九州電力/三菱重工業
4.2.3 ジーエスユアサコーポレーション
4.2.4 米国:DOE/SAFT
4.2.5 カナダ:Avestor社
5. おわりに
第7章 電気二重層キャパシタによる電力貯蔵技術(杉本重幸)
1. 原理および構造材料
1.1 電気二重層キャパシタの原理
1.2 電気二重層キャパシタの材料と構造
1.2.1 分極性電極
1.2.2 集電電極
1.2.3 電解液
1.2.4 セパレータ
1.3 電気二重層キャパシタを電力貯蔵に使用するための回路
1.3.1 電気二重層キャパシタの充放電方法
1.3.2 充放電回路
1.3.3 電圧分担均等化回路
2. 開発動向
2.1 電気二重層キャパシタの開発動向
2.2 電気二重層キャパシタ適用電力貯蔵装置の開発動向
2.2.1 電気二重層キャパシタ式瞬低補償装置
2.2.2 電気二重層キャパシタを適用した直流電鉄用電力貯蔵装置
2.2.3 電気二重層キャパシタを用いた鉄道車両用電力貯蔵システム
2.2.4 自然エネルギー発電との組み合わせ用途
2.2.5電気二重層キャパシタ式緊急遮断弁
3. 導入例
3.1 電気二重層キャパシタ式瞬低補償装置
3.2 電気二重層キャパシタ式直流電鉄用電力貯蔵装置
第8章 フライホイールによる電力貯蔵技術(嶋田隆一)
1. フライホイールの原理および構造材料
1.1 エネルギー密度
1.2 材質と形状
1.3 フライホイール軸受と損失
2. 開発動向
2.1 フライホイール電力貯蔵の利点
2.2 フライホイールの開発課題
3. フライホイールの導入例
3.1 核融合用電動発電機
3.2 電車応用(フライホイールポスト)
3.3 短周期負荷平準化および電力系統の安定度向上用のフライホイール(ROTES)
3.4 米国におけるフライホイール無停電電源(UPS)と瞬低対策フライホイール
3.5 今後の動向など
第9章 超伝導コイルによる電力貯蔵技術
1. SMESの原理(新冨孝和)
1.1 貯蔵原理
1.2 開発の歴史
1.3 特徴と用途
1.4 システム構成
1.5 超伝導コイルの構造
1.6 設計例
2. 開発動向(仁田旦三)
2.1 SMESの特徴と応用
2.2 SMESの用途
2.3 開発の歴史と現状
2.3.1 大容量SMESの開発
2.3.2 超電導マグネットを用いたSMESの開発(ハードウエア)
2.3.3 実用化されたSMES
2.4 あとがき
3. 実用化技術の開発と導入例(林秀美)
3.1 国内のSMES開発と導入状況
3.1.1 九州電力の1MW/1kWhSMESの開発
3.1.2 中部電力の瞬低補償用SMESの実用化
3.1.3 国家プロジェクトのSMES開発
3.2 海外のSMES開発および導入状況
3.3 SMES導入促進に向けて
第10章 パワーエレクトロニクス技術(伊瀬敏史)
1. はじめに
2. 二次電池電力貯蔵におけるPCS
2.1 回路構成
2.2 太陽電池接続に対応した系統連系型ロードコンディショナ
2.3 40MWh/10MW電池電力貯蔵システム
3. 超伝導電力貯蔵におけるPCS
3.1 回路構成
3.2 マイクロSMES
4. フライホイール電力貯蔵におけるPCS
4.1 回路構成
4.2 UPSへのフライホイールの適用例
4.3 電鉄変電所におけるフライホイール電力貯蔵の実施例
5. むすび
目次
第1章 電力貯蔵技術の開発動向
第2章 電力貯蔵技術の市場展望
第3章 ナトリウム硫黄電池による電力貯蔵技術
第4章 レドックスフロー電池による電力貯蔵技術
第5章 シール鉛蓄電池による電力貯蔵技術
第6章 リチウムイオン電池による電力貯蔵技術
第7章 電気二重層キャパシタによる電力貯蔵技術
第8章 フライホイールによる電力貯蔵技術
第9章 超電導コイルによる電力貯蔵技術
第10章 パワーエレクトロニクス技術
著者等紹介
伊瀬敏史[イセトシフミ]
大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻教授
田中祀捷[タナカトシカツ]
早稲田大学大学院情報生産システム研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。