出版社内容情報
★RNAに関する発見の経緯や関連分野の動向をまとめた!
★実験プロトコルを組みこみ,役立つ専門書に!
★RNAi,アプタマー,リボザイム,核酸医薬などを網羅!
★RNA工学の第一線の研究者・技術者の分担執筆!
--------------------------------------------------------------------------------
RNA研究の源流は分子生物学の黎明期,年数にして実に半世紀以上前にまでさかのぼる。その当初よりRNAは,生命現象の根幹をなすセントラルドグマに深く関わる重要な分子として認識されてきたものの,その役割はあくまでもDNAと蛋白質との仲介役にすぎなかった。しかしながら,1980年を前後してなされた,一連の転写後プロセスの解明とRNA酵素(リボザイム)の発見によって,RNAが担う予想外の動的なはたらきが明らかにされた。
RNAに関わる予想外の現象はその後も次々と発見され,特にこの10年間になされた業績は,RNA研究を生命科学の檜舞台に押し上げたといっても過言ではないだろう。結晶構造解析によって明示された究極のリボザイムとしてのリボソーム,ヒトゲノムにコードされる予想外に少ないタンパク質遺伝子と逆に大量に存在する非翻訳RNA(non-protein-coding RNA,ncRNA),RNA interference(RNAi)やそれに関連する現象の発見など,まさに生命科学のパラダイムシフトにつながるような研究が並行して進行しているのである。
このような基礎研究の成果は,必然的に応用研究の潮流を引き起こし,医学や分子生物学,細胞生物学,工学,農学等をひろく包括した「RNA工学」と呼ぶべき研究分野をもたらしたのである。RNA工学には,いまだ確立期にあり即実践的な技術とはよべない領域も数多くある。しかしながら昨今の生命科学,とくにRNA研究の進捗状況をみると,これらの技術が我々の身近なところで活躍する日も遠いものではないだろう。その先駆けとなる機能性RNA医薬が2004年12月に米国FDAにより認可され上市された。
本書は,RNAに関する発見の経緯や関連分野の動向が的確にまとめられ,総説として優れているだけでなく,実験のプロトコルを組み込んだ,役に立つ専門書となっている。本書がRNA工学の,ひいては我々人類の明日への一助となれば幸いである。
2005年12月 東京大学 医科学研究所 中村義一,大内将司
--------------------------------------------------------------------------------
中村義一 東京大学 医科学研究所 基礎医科学部門 教授
稲田利文 名古屋大学 理学研究科 生命理学専攻 助教授
中村幸治 筑波大学 生命環境科学研究科 助教授
三好啓太 徳島大学 ゲノム機能研究センター 分子機能解析分野 COE研究員
塩見美喜子 徳島大学 ゲノム機能研究センター 分子機能解析分野 助教授
飯田直子 (独)理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 発生ゲノミクス研究チーム 研究員
杉本亜砂子 (独)理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 発生ゲノミクス研究チーム チームリーダー
高橋邦明 国立遺伝学研究所 系統生物研究センター 無脊椎動物遺伝研究室 助手
上田龍 国立遺伝学研究所 系統生物研究センター 無脊椎動物遺伝研究室 教授
蓮輪英毅 大阪大学 微生物病研究所 附属遺伝情報実験センター 助手
岡部勝 大阪大学 微生物病研究所 附属遺伝情報実験センター 教授
横田隆徳 東京医科歯科大学院 医歯学総合研究科 脳神経病態学(神経内科) 助教授
仁科一隆 東京医科歯科大学院 医歯学総合研究科 脳神経病態学(神経内科) 大学院生
竹下文隆 国立がんセンター研究所 がん転移研究室 リサーチレジデント
落合孝広 国立がんセンター研究所 がん転移研究室 室長
神津知子 埼玉県立がんセンター 臨床腫瘍研究所 主幹
内藤雄樹 東京大学 大学院理学系研究科
山田智之 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 特任助手
程久美子 東京大学 大学院理学系研究科 特任助教授
森下真一 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授
西郷薫 東京大学 大学院理学系研究科 教授
櫻井仁美 国立遺伝学研究所 生命情報・DDBJ研究センター 研究員
ロベルト・バレロ 国立遺伝学研究所 生命情報・DDBJ研究センター 助手
五條堀 孝 国立遺伝学研究所 生命情報・DDBJ研究センター センター長,教授
山田佳世子 B-Bridge International Inc. Business Development
水谷隆之 B-Bridge International Inc. Business Development Director
大内将司 東京大学 医科学研究所 基礎医科学部門 遺伝子動態分野 助手
小黒明広 東京大学 医科学研究所 基礎医科学部門 遺伝子動態分野 助手
Penmetcha K. R. Kumar (独)産業技術総合研究所 生物機能工学研究部門 機能性核酸研究グループ 主任研究員
井上丹 京都大学 大学院生命科学研究科 教授
井川善也 九州大学 大学院工学研究院 助教授
菅裕明 東京大学 先端科学技術研究センター 教授
舩渡忠男 京都大学 医学部 保健学科 情報理工医学講座 教授
高橋美奈子 東北大学大学院 医学系研究科 免疫血液病学
羽生勇一郎 千葉工業大学(財)エイズ予防財団 リサーチ・レジデント
黒崎直子 千葉工業大学 工学部 生命環境科学科 講師
高久洋 千葉工業大学 工学研究科 生命環境科学専攻 大学院教授
北原圭 東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 大学院生
鈴木勉 東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 助教授
和田猛 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 メディカルゲノム専攻 助教授
宮川伸 (株)リボミック
北村義浩 東京大学医科学研究所 先端医療研究センター 感染症分野 助教授
原田和雄 東京学芸大学 教育学部 助教授
--------------------------------------------------------------------------------
目次
序 章 RNA入門(中村義一)
1. はじめに
1.1 RNAの研究の歴史
1.2 RNAルネッサンス
1.3 RNA医工学と疾患
1.4 展望
2. RNAとは(RNAの物性と代謝)(稲田利文)
2.1 RNAの共有結合構造
2.2 修飾塩基
2.3 生合成
2.4 加工
2.5 分解等
2.6 RNaseを用いた解析
2.7 RNAの構造と機能
3. 非翻訳型RNA(ncRNA)(中村幸治)
3.1 生体内で安定に存在するncRNAの探索
3.2 ゲノムワイドなスクリーニングによる新規ncRNAの同定
3.3 真正細菌における機能性ncRNAの遺伝子発現制御機構
3.4 病原細菌におけるncRNAの機能解析
3.5 アロステリックなリボスイッチによる遺伝子発現制御機構
第1章 RNA interference(RNAi)とmicroRNA(miRNA)
1. 概論(三好啓太,塩見美喜子)
1.1 はじめに
1.2 RNAiのメカニズム
1.3 miRNAによる翻訳制御機構のメカニズム
1.4 siRNAとmiRNAによる生体内プロセスの制御
1.5 おわりに
2. 線虫(C. elegans)におけるRNAiの応用(飯田直子,杉本亜砂子)
2.1 はじめに
2.2 線虫RNAiの概説
2.3 RNAiを用いた線虫遺伝子の網羅的機能解析
2.4 実験プロトコール
2.4.1 プロトコール1:dsRNAの合成
2.4.2 プロトコール2:dsRNAの導入と表現型の観察
3. ショウジョウバエ(D. melanogaster)におけるRNAiの応用(高橋邦明,上田龍)
3.1 はじめに
3.2 RNAiハエバンクについての概要
3.3 ショウジョウバエ誘導型RNAiの原理
3.4 UAS-IR transgene構築
3.5 おわりに
4. RNAiによる哺乳動物個体レベルでのノックダウン(蓮輪英毅,岡部勝)
4.1 はじめに
4.2 合成siRNAの投与によるマウス個体におけるRNAi
4.2.1 ハイドロダイナミクス法を用いたsiRNAの導入
4.2.2 siRNAの化学修飾による安定化と高効率な導入
4.2.3 27塩基の2本鎖RNAの可能性
4.3 ベクターによるsiRNA(dsRNA)の発現系を用いたマウス個体におけるRNAi
4.3.1 pol IIIプロモーターを用いたRNAiトランスジェニックマウスの作製
4.3.2 pol IIプロモーターを用いたRNAiトランスジェニックマウスの作製
4.4 実験例(実験プロトコール)
4.4.1 実験材料および実験機器
4.4.2 プロトコール
5. RNAiの神経疾患への応用(横田隆徳,仁科一隆)
5.1 はじめに
5.2 siRNAの特異性:変異遺伝子特異的なsiRNA
5.3 siRNAの特異性:Off-Target効果などの副反応
5.4 神経疾患への応用:ウイルス性,免疫性疾患
5.5 神経疾患への応用:遺伝性神経変性疾患
5.6 神経疾患への応用:弧発性神経変性疾患
5.7 siRNAのin vivoへのデリバリー
5.8 実験プロトコール
5.8.1 Hydrodynamics法を用いたマウスへのsiRNA発現プラスミドDNAの投与
5.8.2 臓器の採取とRNAi効果の評価
5.9 おわりに
6. アテロコラーゲンによるがん治療を目的としたsiRNAのin vivoデリバリーシステム(竹下文隆,落谷孝広)
6.1 はじめに
6.2 siRNAのin vivoデリバリー
6.3 がんモデル動物を用いての研究
6.3.1 アデノウイルスベクター
6.3.2 カチオニックリポソームなどの導入試薬
6.3.3 shRNA発現プラスミドベクター
6.3.4 抗体結合型
6.4 アテロコラーゲン
6.4.1 アテロコラーゲンの性状と核酸との複合体の形成
6.4.2 アテロコラーゲンによる核酸医薬のin vivoデリバリー
6.5 アテロコラーゲンによるsiRNAのin vivoデリバリーの実験プロトコール
6.5.1 プロトコール
6.5.2 局所投与の実験例
6.5.3 全身投与の実験例
6.6 おわりに
7. miRNAと疾患(神津知子)
7.1 はじめに
7.2 miRNAと疾患
7.3 miRNAのクローニング(Ligation-mediated法)
7.4 実験プロトコール
8. 効率的なsiRNAの設計(内藤雄樹,山田智之,程久美子,森下真一,西郷薫)
8.1 はじめに
8.2 効率的なsiRNAの配列規則性
8.3 siRNA設計ウェブサイト
8.3.1 ヒトvimentin遺伝子に対するsiRNAの設計例
8.3.2 siRNA設計オプション
9. miRNAと標的遺伝子の予測(櫻井仁美,ロベルト・バレロ,五條堀孝)
9.1 はじめに
9.2 miRNAのコンピューター予測
9.3 動物のmiRNA標的遺伝子の予測アルゴリズム
9.4 ウェブサーバー・データベースの紹介と比較
9.4.1 miRNA Registryの概要
9.4.2 名前の意味
9.4.3 miRNA判定基準
9.4.4 その他のデータベース
9.4.5 標的遺伝子データベース
10. siRNA医薬品の現状と今後の展望(山田佳世子,水谷隆之)
10.1 はじめに
10.2 創薬関連遺伝子のスクリーニング
10.3 治療薬の開発
10.3.1 HIV治療への応用
10.3.2 HBV/HCV
10.3.3 冠動脈疾患(CAD)
10.3.4 AMD
10.4 薬物送達法の改善
10.4.1 vehicle
10.4.2 キャリアの利用
10.4.3 oligo末端修飾
10.4.4 その他外力を用いた透過促進方法
10.5 off-target等の副作用
10.6 おわりに
第2章 アプタマー
1. 概論(大内将司)
1.1 はじめに
1.2 アプタマーとは
1.2.1 SELEX法
1.2.2 アプタマーの特徴
1.3 SELEX法におけるさまざまな選別プロセス
1.3.1 一般的な選別方法
1.3.2 標的の切り替えをともなう選別方法
1.3.3 精密測定装置を用いた選別方法
1.3.4 光架橋を応用した選別方法
1.3.5 アロステリック・セレクション
1.3.6 複雑な標的を用いた選別方法
1.4 アプタマーの応用技術
1.4.1 標的分子精製への応用
1.4.2 ホットスタートPCRへの応用
1.4.3 機能解析ツールとしての応用
1.5 アプタマーを用いた検出システム
1.5.1 アプタマー・チップ
1.5.2 アプタマー・ビーコン
1.5.3 近接効果を利用した検出方法
1.5.4 生細胞を用いた検出方法
1.6 アプタマー医薬品
1.6.1 抗血管内皮細胞増殖因子アプタマー
1.6.2 抗血液凝固因子アプタマー
1.6.3 その他
1.7 おわりに
2. 翻訳開始因子に対するアプタマーによる制がん戦略(小黒明広)
2.1 がんと翻訳開始因子
2.2 翻訳開始因子に対するRNAアプタマー
2.3 SELEXのプロトコール
2.3.1 RNAプールの作製
2.3.2 標的に結合するRNAの選択
3. Efficient methodologies for RNA aptamer selection, and the isolation of antiviral
aptamers and their application in novel diagnostic platform development(Penmetcha K.R. Kumar)
3.1 Introduction
3.2 Aptamer selection
3.2.1 Aptamer selection methods
3.2.2 Aptamer selection by SPR
3.3 Anti-viral aptamers
3.4 Modulating aptamers
3.5 Conclusion
第3章 リボザイム
1. 概論(井上丹)
1.1 はじめに
1.2 Large ribozyme(ラージリボザイム)
1.3 構造解析
1.4 活性発現のメカニズム
2. 人工リボザイム
2.1 はじめに(井川善也)
2.1.1 リガーゼ・リボザイム
2.1.2 自己切断リボザイム
2.1.3 タンパク合成に関わるリボザイム
2.1.4 その他の人工リボザイム
2.2 アミノアシルtRNA合成機能をもつ人工リボザイムとその技術的応用(菅裕明)
2.2.1 アミノアシルtRNA合成リボザイムの重要性
2.2.2 人工ARSリボザイムの創製
2.2.3 翻訳への応用:遺伝暗号の拡張
2.2.4 PCR・試験管内転写
2.2.5 フレキシレジンの調整
2.2.6 アミノアシル化
2.2.7 無細胞翻訳系
2.3 RNAアーキテクチャ(RNA建築学)と人工リボザイム創製への応用(井川善也)
2.3.1 分子骨格を利用した人工酵素創製リボザイム創製
2.3.2 分子骨格からの人工酵素創製リボザイム創製
2.3.3 RNAアーキテクチャ(RNA建築学)
2.3.4 RNAアーキテクチャからの人工リボザイムの進化
2.3.5 DSLリガーゼ・リボザイムのin vitroセレクション(実験プロトコール)
第4章 RNA工学プラットホーム
1. アンチセンスRNAテクノロジー(舩渡忠男,高橋美奈子)
1.1 はじめに
1.2 アンチセンス法
1.3 ナチュラルアンチセンスRNA(naturally occurring antisense RNA)
1.4 Non-coding RNAs(ncRNAs)
1.5 インプリント遺伝子
1.6 アンチセンスRNAの臨床応用
1.7 実験例
1.8 おわりに
2. RNase PおよびtRNase Zの遺伝子治療への応用(羽生勇一郎,黒崎直子,高久洋)
2.1 はじめに
2.2 実験プロトコール
2.2.1 標的部位の選択およびEGSのデザイン
2.3 実験例
3. リボソームの立体構造と抗生物質の作用機序(北原圭,鈴木勉)
3.1 はじめに
3.2 タンパク合成のメカニズム
3.3 30Sの立体構造と暗号解読の分子機構
3.4 誤翻訳を誘発する抗生物質:アミノグリコシド系
3.4.1 パロモマイシン
3.4.2 ストレプトマイシン
3.5 Aサイトへの結合を阻害する抗生物質:テトラサイクリン
3.6 50Sの立体構造
3.7 ペプチド転移反応を阻害する抗生物質
3.7.1 ピューロマイシン
3.7.2 クロラムフェニコール
3.7.3 リンコサミド
3.8 ペプチド脱出トンネルに作用する抗生物質:マクロライド系
3.9 新規抗生物質デザイン
4. 核酸医薬の安定化戦略(和田猛,宮川伸)
4.1 はじめに
4.2 リボース部位修飾
4.2.1 2´-修飾核酸
4.2.2 LNA
4.2.3 3´-N-ホスホロアミデートDNA
4.2.4 4´-S-RNA
4.2.5 シュピーゲルマー
4.3 バックボーン修飾
4.3.1 ホスホロチオエートDNA/RNA
4.3.2 ボラノホスフェートDNA/RNA
4.3.3 ペプチド核酸
4.3.4 モノホリノホスホロジアミデート
4.4 塩基部修飾
4.5 RNAの末端修飾
4.6 RNAアプタマーの修飾
5. 核酸医薬品のデリバリーシステム(北村義浩)
5.1 ウイルス系デリバリーシステム
5.1.1 レトロウイルス
5.1.2 レンチウイルス
5.1.3 アデノウイルス
5.1.4 アデノ随伴ウイルス(Adeno-associated virus,AAV)
5.1.5 センダイウイルス(HVJ)
5.2 非ウイルス系デリバリーシステム
5.2.1 電気穿孔法
5.2.2 膜融合型リポソーム法
5.2.3 非膜融合型キャリア法
5.2.4 DEAE Dextran法
6. 人工RNA結合ペプチド(原田和雄)
6.1 はじめに
6.2 人工RNA結合ポリペプチドを候補ポリペプチドのライブラリーから同定するためのアプローチ
6.2.1 RNAはポリペプチドによってどのように認識されているか?
6.2.2 RNA-ポリペプチド相互作用検出系の比較
6.2.3 ライブラリーのデザイン
6.3 ファージλNタンパク質によるアンチターミネーションを利用したRNA結合ペプチドの同定
6.3.1 アンチターミネーション法の原理
6.3.2 LacZレポーターを用いたHIV RRE結合ペプチドの単純な(Low-Complexity)ライブラリーからの「スクリーニング」
6.3.3 NPT IIレポーターを用いたHIV RRE結合ペプチドの複雑な(High-Complexity)ライブラリーからの「セレクション」
6.4 おわりに
目次
序章 RNA入門(RNAとは(RNAの物性と代謝)
非翻訳型RNA(ncRNA))
第1章 RNA interference(RNAi)とmicroRNA(miRNA)(概論;線虫(C.elegans)におけるRNAiの応用 ほか)
第2章 アプタマー(概論;翻訳開始因子に対するアプタマーによる制がん戦略 ほか)
第3章 リボザイム(概論;人工リボザイム)
第4章 RNA工学プラットホーム(アンチセンスRNAテクノロジー;RNase PおよびtRNase Zの遺伝子治療への応用 ほか)
著者等紹介
中村義一[ナカムラヨシカズ]
東京大学医科学研究所基礎医科学部門教授
大内将司[オオウチショウジ]
東京大学医科学研究所基礎医科学部門遺伝子動態分野助手(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- バイリンガルの壁 - 子どものことばの…
-

- 電子書籍
- 僕の婚約者の話【タテスク】 第68話 …
-

- 電子書籍
- ウィルソン家の秘密【タテヨミ】第11話…
-
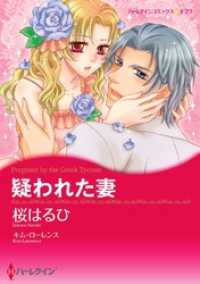
- 電子書籍
- 疑われた妻【分冊】 4巻 ハーレクイン…
-
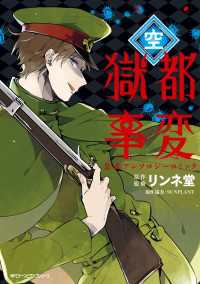
- 電子書籍
- 獄都事変 公式アンソロジーコミック ‐…



