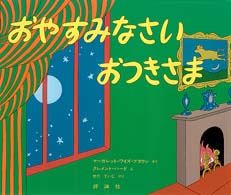出版社内容情報
★「昆虫による物質生産」,「絹タンパク質の高度利用」,「昆虫特有の特異機能や物質の利用」,「農業への応用」,「昆虫にならった製品開発」に大別し,昆虫研究の最新情報を掲載!
★執筆者は,食品・医薬・繊維・農薬・農業・建築など,昆虫研究の産業利用を進めるメーカー・研究機関・大学の第一線で活躍する研究開発担当者!
--------------------------------------------------------------------------------
我が国では古くから養蚕業や養蜂業において昆虫が利用されてきており,特に養蚕業は生糸の輸出によって外貨を稼ぐ主要な産業でした。時代が変わり,国内の繭の生産量は大きく減少していますが,この主要産業であった養蚕業を支えるために日本ではカイコ研究が精力的に進められてきました。この研究の積み上げの結果,カイコで遺伝子組換えが可能となり,カイコの飼育技術に基礎を置くカイコを利用した有用タンパク質の生産技術が発展してきています。また,絹を繊維として利用するだけでなく,タンパク質素材として利用する研究も発展してきており,その生体親和性の良さという優れた性質に加えて「シルク」というイメージもプラスに働いて,広く使われるようになってきています。
また,カイコの属する昆虫は種数が100万以上とも言われており,多種多様な環境に適応し,様々な餌を利用しています。この昆虫の適応能力のメカニズムを解明し利用する研究が行われており,今後もいろいろな機能が発見されて利用されることが期待されます。昆虫の持つ機能以外にも,昆虫の体の動きや体の表面構造,そして昆虫の外部刺激に対する反応様式などを解明することによって,昆虫をモデルにした新素材や構造物の開発も行われています。また,天敵昆虫を増殖して害虫防除素材として利用する技術開発も進んできています。
このように,今まではあまり産業振興に役立つ素材として貴重な資源となってきています。農林水産省では,昆虫機能の利用を目指す「昆虫テクノロジー研究」を現在実施しています。このプロジェクトでは,かつて中国からシルクロードを通って絹製品が各地に広まった歴史を現代の日本に再現し,昆虫機能を利用した製品が日本から世界各地に広まる「日本発シルクロード」のそうしゅつを目標として研究が進められています。
本書が「日本発シルクロード」の実現に寄与できることを希望しています。
2005年5月 川崎建次郎,野田博明,木内信
--------------------------------------------------------------------------------
川崎建次郎 (独)農業生物資源研究所 生体機能研究グループ グループ長
野田博明 (独)農業生物資源研究所 昆虫適応遺伝子研究グループ チーム長
木内信 (独)農業生物資源研究所 企画調整部 研究企画科長
鈴木幸一 岩手大学 農学部 教授
竹田敏 (独)農業生物資源研究所 昆虫新素材開発研究グループ グループ長
三田和英 (独)農業生物資源研究所 ゲノム研究グループ 昆虫ゲノム研究チーム チーム長
山田勝成 東レ(株) 化成品研究所 ケミカル研究室 室長
宇佐美昭宏 片倉工業(株) 生物科学研究所 所長
森肇 京都工芸繊維大学 繊維学部 教授;(株)プロテインクリスタル 代表取締役
中澤裕 (株)プロテインクリスタル 主任研究員
池田敬子 (株)プロテインクリスタル 主任研究員
田村俊樹 (独)農業生物資源研究所 昆虫生産工学研究グループ チーム長
中村匡利 (独)農業生物資源研究所 生体機能研究グループ 代謝調節研究チーム 研究チーム長
伊東昌章 (株)島津製作所 分析計測事業部 ライフサイエンスビジネスユニット ライフサイエンス研究所 主任
朝倉哲郎 東京農工大学 工学部 生命工学科 教授
大郷耕輔 東京農工大学 産官学連携・知的財産センター 非常勤講師
高須陽子 (独)農業生物資源研究所 素材特性研究チーム 主任研究官
辻本和久 セーレン(株) 技術開発部門 主任
佐々木真宏 セーレン(株) 技術開発部門 主任
玉田靖 (独)農業生物資源研究所 昆虫新素材開発研究グループ 生体機能模倣研究チーム チーム長
瓜田章二 福島県農業試験場 梁川支場 支場長;工学博士
長島孝行 東京農業大学 農学部 農学科 助教授
山川稔 (独)農業生物資源研究所 生体防御研究グループ 先天性免疫研究チーム チーム長;
筑波大学 大学院生命環境学科学研究科 客員教授
渡辺裕文 (独)農業生物資源研究所 昆虫適応遺伝研究グループ主任研究官
奥田隆 (独)農業生物資源研究所 生体機能研究グループ 主任研究官
渡邊?虚F (独)農業生物資源研究所 生体機能研究グループ 主任研究官
黄川田隆洋 (独)農業生物資源研究所 生体機能研究グループ 研究員
伊澤晴彦 国立感染症研究所 昆虫医科学部 研究員
岩永史朗 神戸大学 農学部 生物機能化学科 助手
中島信彦 (独)農業生物資源研究所 昆虫共生媒介機構研究チーム 主任研究官
加藤康仁 日本化薬(株) 精密化学品開発研究所
和田哲夫 アリスタライフサイエンス(株) バイオソリューション部 部長
早川徹 新潟大学 大学院自然科学研究科 助手(現:岡山大学 大学院自然科学研究科 助手)
堀秀隆 新潟大学 大学院自然科学研究科 応用バイオサイエンス大講座 教授
日本典秀 (独)農業生物資源研究所 天敵昆虫研究チーム 主任研究官
前田太郎 (独)農業生物資源研究所 昆虫適応遺伝研究グループ 天敵昆虫研究チーム 任期付研究員
畠山正統 (独)農業生物資源研究所 発生分化研究グループ 発生機構研究チーム 主任研究官
小濱継雄 沖縄県ミバエ対策事務所 増殖照射課 課長
山崎努 (株)フィールド 環境事業部 部長
瀧川幸司 (株)フィールド 環境事業部 研究室 室長
安藤規泰 東京大学 大学院情報理工学系研究科 産学官連携研究員
岡田公太郎 東京大学 大学院情報理工学系研究科 産学官連携研究員
神崎亮平 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授
星野春夫 (株)竹中工務店 技術研究所 先端研究開発部 アドバンストコンストラクション部門 主任研究員
青柳隼夫 (株)コンストラクション・イーシー・ドットコム 電子契約事業部 取締役事業部長
能勢健吉 帝人ファイバー(株) ファイバー事業部 モルフォ推進室 室長
--------------------------------------------------------------------------------
目次PDF
総論編
昆虫テクノロジーの総論-研究開発動向- (鈴木幸一)
1. はじめに
2. 人と社会のための昆虫テクノロジー
3. 地域貢献型の昆虫テクノロジー
4. 新しい絹タンパク質資源の探索
5. 特異的機能解析への挑戦
6. 将来展望をもった昆虫テクノロジー
7. ヒトの脳活動にも迫る昆虫テクノロジー
8. ナショナルバイオリソースとしての昆虫
基礎編-昆虫テクノロジーの理解と導入のために-
第1章 昆虫という生物群とは?(竹田敏)
1. 昆虫という生物群の地位
2. 昆虫の起源
3. 昆虫の体の仕組み
4. 昆虫の分類
5. 昆虫の繁栄を支えた適応能力
6. 昆虫の主な生理的特徴
6.1 呼吸
6.2 血液循環と血液
6.3 外骨格という仕組み
6.4 内分泌と脱皮,変態
6.5 休眠
7. 昆虫の殺虫剤と抵抗性
第2章 昆虫の飼育法(川崎建次郎,木内信)
1. はじめに
2. 昆虫の特性
3. 一般的な飼育条件と飼育容器
4. 飼料
5. 病気の予防
6. 近親交配による悪影響
7. 具体的な飼育例
7.1 ハスモンヨトウの飼育
7.2 エリサンの飼育
7.3 ウンカ・ヨコバイ類
7.4 カメムシ類
8. 餌の入手先
8.1 昆虫用人工飼料
8.2 カイコ用飼料
9. 昆虫の入手先
9.1 住化テクノサービス株式会社ホームページで掲載されている入手可能な昆虫のリスト
第3章 昆虫ゲノム情報の利用:昆虫ゲノム解析の現状と昆虫遺伝子探索の方法,利用できるデータ ベース(三田和英)
1. はじめに
2. 昆虫ゲノム研究の現状
2.1 全ゲノム解析
2.1.1 ショウジョウバエDrosophila melanogaster
2.1.2 ハマダラカAnopheles gambiae
2.1.3 オオタバコガの一種Heliothis virescens
2.1.4 ミツバチApis mellifera
2.1.5 トリボリウムTribolium cataneum
2.1.6 カイコBombyx mori
2.2 EST解析
2.3 地図情報
2.4 マイクロアレイ
3. ゲノム情報を利用した遺伝子探索方法
3.1 ホモロジー検索
3.2 遺伝子探索プログラム
3.3 GeneOntology (GO)データベースの利用
4. おわりに
技術各論編
第1章 昆虫を利用した有用物質生産
1. バキュロウイルスを利用した動物インターフェロンの生産(山田勝成)
1.1 はじめに
1.2 カイコ核多核体病ウイルスを用いた組換えタンパク質の生産
1.3 ネコインターフェロンの生産
1.3.1 組換えネコインターフェロンの発現
1.3.2 ネコインターフェロンの単一成分化
1.4 イヌインターフェロン-γの生産
1.4.1 糖鎖結合様式の違いによる多様性
1.4.2 C末端部分の限定分解
1.5 おわりに
2. カイコを利用したタンパク質の受注生産システム-多種中量タンパク生産向けシステムの構築と, その特徴について- (宇佐美昭宏)
2.1 はじめに
2.2 スーパーワームサービスの特徴
2.3 多品種生産への工夫
2.3.1 バキュロウイルスの改良
2.3.2 発現蛋白質の種類による蛹と幼虫の使い分け
2.3.3 迅速な精製条件検討を可能とする蚕
2.4 生産可能な蛋白質(生産した蛋白質の性状)
2.4.1 糖鎖構造の違い
2.4.2 生産量の少ない蛋白質
2.4.3 凝集する蛋白質
2.5 おわり
3. 昆虫ウイルスの多角体を用いたプロテインチップの開発-プロテインチップの考え方と作成法、 利用法- (森肇,中澤裕,池田敬子)
3.1 はじめに
3.2 細胞質多角体病ウイルスが作る多角体とは
3.3 プロテインチップとは
3.4 多角体にタンパク質分子が固定化される仕組み
3.5 多角体へのタンパク質分子固定化の具体例
3.6 プロテインビーズ®に固定化されたタンパク質分子の安定性
3.7 多角体へのリン酸化酵素の固定化とチップ作製
3.8 多角体へのアレルゲンの固定化とチップ作製
3.9 今後の展望
4. 組換え体カイコを利用した有用物質生産系の開発とその展望-カイコ遺伝子組換え手法とその特徴を含む- (田村俊樹)
4.1 はじめに
4.2 トランスポゾンとは
4.3 組換えカイコの作出法
4.4 有用物質の生産に適した組織
4.4.1 絹糸腺
4.4.2 絹糸腺以外の組織
4.5 組換えカイコにおける遺伝子の発現系
4.6 組換えカイコによる有用物質生産の例
4.6.1 コラーゲン
4.6.2 サイトカイン
4.6.3 抗菌性タンパク質
4.7 おわりに
5. カイコの人工飼料育(中村匡利)
5.1 人工飼料の特徴
5.2 人工飼料の組成
5.3 人工飼料の調整
5.4 粉体飼料の調整
5.5 湿体飼料の調整
5.6 人工飼料による飼育
5.7 飼育室の防疫管理
6. 昆虫由来抽出液を用いた無細胞タンパク質合成試薬キットの開発(伊東昌章)
6.1 はじめに
6.2 カイコ幼虫後部絹糸腺抽出液の系
6.3 昆虫培養細胞抽出液の系
6.4 試薬キットの開発
6.5 試薬キットの特徴
6.6 おわりに
第2章 カイコ等の絹タンパク質の利用
1. 絹フィブロインの構造と大腸菌による新しい絹の生産ならびに生体材料への応用(朝倉哲郎,大郷耕輔)
1.1 はじめに
1.2 絹フィブロインの構造と繊維化に伴う構造変化
1.3 新しい絹様タンパク質の分子設計と大腸菌ならびにトランスジェニックカイコによる生産
1.4 再生絹繊維および絹不織布の作成
1.5 絹繊維の生体材料への応用
2. セリシンの構造と機能-セリシン分子の特徴と物理的性質,その機能-(高須陽子)
2.1 セリシンとは
2.2 セリシン分子の特徴
2.2.1 セリシンタンパクの成分
2.2.2 セリシンのアミノ酸組成
2.2.3 各セリシン成分の中部絹糸腺内分布
2.2.4 セリシン遺伝子(連関分析)
2.2.5 セリシン遺伝子(分子生物学)
2.2.6 非セリシン繭層タンパク
2.3 セリシンの物理的性質
2.3.1 セリシンの物性研究に関する注意点
2.3.2 セリシンの結晶性
2.3.3 セリシン類似合成ペプチドの結晶性
2.3.4 セリシンの力学的性質
2.3.5 コロイド化学的性質
2.3.6 セリシン成分による物性の差異
2.4 セリシンの機能
2.4.1 カイコにおけるセリシンの機能
2.4.2 細胞生育促進作用
2.4.3 その他の生理機能
3. セリシンの新規機能性とその利用(辻本和久,佐々木真宏)
3.1 はじめに
3.2 スキンケア素材への利用
3.3 機能性食品への利用
3.4 バイオマテリアルとしての応用
3.4.1 凍結保護作用
3.4.2 細胞増殖促進効果
3.4.3 セリシンペプチド
3.5 今後の展望
4. 絹タンパク質の化学修飾による新機能付加とその利用(玉田靖)
4.1 はじめに
4.2 絹タンパク質の化学反応性
4.3 硫酸化による機能付加
4.4 機能性分子の付加
4.5 グラフト重合反応
4.6 グラフト重合による機能性付与
4.7 今後の展望
5. 蚕糸生産物と野蚕の生活資材への有効利用(瓜田章二)
5.1 はじめに
5.2 蚕糸生産物の有効利用
5.2.1 桑条木質から生体膜類似機能膜の調製
5.2.2 桑条木質から調製した生体機能類似膜によるイオンの濃縮
5.2.3 蚕糸生産物その他の利用
5.3 野蚕の生活資材への有効利用
5.3.1 天蚕絹フィブロイン高分子膜の調製
5.3.2 天蚕絹フィブロイン膜の利用とその配合化粧水の調合
5.3.3 野蚕絹糸の機能利用の検討
6. 絹タンパクのプラスチック等への加工(長島孝行)
6.1 はじめに
6.2 資源としてのシルク
6.3 シルクの構造と機能,そして新しいものづくりへ
6.4 プラスチックを超えたシルクプラスチック
第3章 昆虫の特異機能の解析とその利用
1. 昆虫の抗細菌ペプチドの特性と医薬分野への利用(山川稔)
1.1 はじめに
1.2 抗細菌ペプチドの特性
1.3 細菌の抗生物質に対する抵抗性獲得のメカニズム
1.4 抗細菌ペプチドの改変とその利用
1.5 おわりに
2. 昆虫の外分泌タンパク質の特性とその利用(渡辺裕文)
2.1 はじめに
2.2 注目される社会性昆虫の外分泌機能
2.3 新規遺伝子の探索に有効な栄養関連酵素
2.4 社会性膜翅目の糖質関連酵素
2.5 食材性昆虫類の木質分解酵素
2.6 甲虫類の多様な食性と消化酵素
2.7 昆虫由来酵素の生産
2.8 今後の昆虫外分泌タンパク研究
3. ネムリユスリカの極限的な乾燥耐性のメカニズム解析とその利用(奥田隆,渡邊?虚F,黄川田隆洋)
3.1 はじめに
3.2 ネムリユスリカの極限的な乾燥耐性(クリプトビオシス)
3.3 クリプトビオシスとトレハロース
3.4 ネムリユスリカのクリプトビオシス誘導要因
3.5 ネムリユスリカのトレハロース合成誘導要因
3.6 ネムリユスリカのクリプトビオシス誘導制御機構
3.7 日本産ユスリカはなぜクリプトビオシスができない?
3.8 ネムリユスリカの産業利用について
3.8.1 理科教育の教材
3.8.2 乾燥保存が可能な観賞魚用の生餌
3.8.3 常温乾燥保存が可能な培養細胞
3.8.4 水浄化システムの生物資材
3.8.5 宇宙生物学の実験材料
3.8.6 臓器の常温乾燥保存技術
3.8.7 食肉などの常温乾燥保存技術
3.9 おわりに
4. 吸血昆虫の唾液腺生理活性物質による抗止血機構の解析と利用(伊澤晴彦,岩永史朗)
4.1 はじめに
4.2 動物の血液凝固機序
4.3 多種多様な唾液腺の抗止血活性物質
4.3.1 ダニの抗トロンビン活性物質
4.3.2 サシガメの多機能な抗止血活性物質
4.3.3 カとダニの接触相(カリクレイン-キニン系)阻害活性物質
4.4 有用遺伝資源としての吸血昆虫生理活性分子
4.5 おわりに
5. 昆虫ウイルスRNAによる任意のN末アミノ酸を有するタンパク質の翻訳(中島信彦)
5.1 はじめに
5.2 昆虫ウイルスIRESによる翻訳開始の機構
5.3 IGR-IRESを使用した様々なコドンからの試験管内タンパク質合成
5.4 おわりに
第4章 害虫制御技術等農業現場への応用
1. ゲノム創農薬による殺虫剤開発(加藤康仁)
1.1 はじめに
1.2 農薬市場を取り巻く環境と殺虫剤開発
1.3 現在の殺虫剤開発の問題点
1.4 昆虫ゲノム情報を利用した殺虫剤開発
1.4.1 リード化合物の発見
1.4.2 リード化合物の最適化
1.5 最後に
2. 天敵昆虫・訪花昆虫の農業への応用(和田哲夫)
2.1 はじめに
2.2 天敵昆虫・受粉昆虫利用の現状
2.2.1 海外の現状
2.2.2 日本の現状
2.3 天敵昆虫・受粉昆虫の増殖と普及について
2.3.1 天敵昆虫・受粉昆虫の増殖
2.3.2 天敵昆虫・受粉昆虫の利用技術の普及について
2.4 天敵昆虫・受粉昆虫の開発,利用,普及上の問題点
3. Bacillus thuringiensisの殺虫蛋白質の科学と応用(早川徹,堀秀隆)
3.1 はじめに
3.2 Bacillus thuringiensisの形態,分布,分類
3.2.1 B. thuringiensisの形態と分布
3.2.2 B. thuringiensisの分類
3.3 殺虫蛋白質
3.3.1 クリスタルの構造
3.3.2 殺虫蛋白質の分類
3.3.3 Cryトキシンの構造
3.4 殺虫機構
3.4.1 Cryトキシンの受容体タンパク質
3.4.2 Cryトキシン受容体の糖鎖構造
3.4.3 Cryトキシンの膜貫入
3.5 BT殺虫剤
3.6 B. Thuringiensis殺虫蛋白質と耐虫遺伝子組換え植物
3.6.1 耐虫組換え体植物
3.6.2 耐虫組換え植物作製技術
3.7 B. thuringiensis蛋白質と安全問題
3.7.1 耐虫遺伝子組換え体植物と安全問題
3.7.2 アレルギー問題(スターリンク問題)およびモナーク蝶問題
3.8 Cryトキシンの新展開
4. 天敵昆虫系統の識別技術と,その利用(日本典秀)
4.1 はじめに
4.2 DNAマーカー
4.2.1 RAPD
4.2.2 PCR-RFLP
4.2.3 マルチプレックスPCR
4.2.4 シークエンス
4.2.5 マイクロサテライト
4.3 種の同定
4.4 品質管理
4.5 放飼後のモニタリング
4.6 おわりに
5. 捕食性天敵-植物の情報化学物質を介した相互作用の害虫防御技術への利用(前田太郎)
5.1 はじめに
5.2 HIPVの組成・生産量の変異
5.3 HIPV生産のメカニズム
5.4 HIPVを利用した捕食性カブリダニの採餌行動
5.5 植物-天敵間相互作用を害虫防除にどう活かすか
5.5.1 HIPVの操作
5.5.2 植物の操作(化学的処理)
5.5.3 植物の操作(遺伝的操作)
5.5.4 天敵の操作(行動の可塑性の利用)
5.5.5 天敵の操作(遺伝的変異の利用)
5.6 さいごに
6. 遺伝子組換えによる不妊化技術の開発と利用(畠山正統)
6.1 はじめに
6.2 昆虫の遺伝子組換えの現状
6.3 昆虫の不妊化とその利用
6.3.1 不妊虫放飼法(Sterile insect technique:SIT)
6.3.2 トランスジェニック法による昆虫の不妊化
6.4 トランスジェニック昆虫の利用とそれにともなうリスク
6.5 おわりに
7. 放射線照射による不妊虫を用いた害虫の根絶防除:沖縄県におけるウリミバエの根絶(小濱継雄)
7.1 はじめに
7.2 不妊虫放飼法に必要な技術
7.2.1 大量増殖
7.2.2 放射線照射による不妊化
7.2.3 輸送
7.2.4 放飼
7.2.5 防除効果判定
7.2.6 品質管理
7.2.7 密度抑圧
7.3 ウリミバエの根絶
7.3.1 久米島の実証防除
7.3.2 沖縄県全域からの根絶
7.4 再侵入対策
8. イエバエ幼虫を利用した有機廃棄物再資源化システム(山崎 努,瀧川幸司)
8.1 はじめに
8.2 ズーコンポストシステムの概要
8.3 ズーコンポスト施設の仕組み
8.3.1 前工程
8.3.2 処理工程
8.3.3 後工程
8.4 ズーコンポストシステムの特長
8.4.1 システムで利用するイエバエの特長
8.4.2 処理方法の特長
8.4.3 生産物の特長
8.5 おわりに
第5章 昆虫の体の構造,運動機能,情報処理機能の利用
1. 昆虫の脳による情報処理機能の特性とその利用の展望(安藤規泰,岡田公太郎,神崎亮平)
1.1 はじめに
1.2 昆虫の神経系
1.2.1 感覚器官
1.2.2 中枢神経系
1.2.3 環境受容と適応行動
1.3 昆虫の嗅覚情報処理と適応行動
1.3.1 匂いの受容
1.3.2 触角葉における匂い情報処理
1.3.3 匂い源探索行動とその神経機構
1.4 昆虫の環境適応システムの利用
2. 昆虫の感覚機能を利用したバイオセンサー開発の展望(玉田靖)
2.1 はじめに
2.2 バイオセンサーシステムの設計
2.3 モデル系としてのニクバエ味覚機能の利用
2.4 バイオセンサー構築の試み
2.5 展望
3. 昆虫の運動機能を利用した建築物の形状可変システムの開発(星野春夫,青柳隼夫)
3.1 はじめに
3.2 空気圧利用アクチュエータ
3.3 形状可変出入口システム
3.4 形状可変階段システム
3.5 おわりに
4. 昆虫の翅の構造発色を利用した繊維の開発と製品化(能勢健吉)
4.1 緒言
4.2 構造発色とは
4.3 薄膜干渉
4.4 工業化
4.5 構造発色糸“Morphotex®”の特徴
4.6 商品開発状況
目次
総論編(昆虫テクノロジーの総論―研究開発動向)
基礎編―昆虫テクノロジーの理解と導入のために(昆虫という生物群とは?;昆虫の飼育法;昆虫ゲノム情報の利用:昆虫ゲノム解析の現状と昆虫遺伝子探索の方法、利用できるデータベース)
技術各論編(昆虫を利用した有用物質生産;カイコ等の絹タンパク質の利用;昆虫の特異機能の解析とその利用;害虫制御技術等農業現場への応用;昆虫の体の構造、運動機能、情報処理機能の利用)
著者等紹介
川崎建次郎[カワサキケンジロウ]
(独)農業生物資源研究所生体機能研究グループグループ長
野田博明[ノダヒロアキ]
(独)農業生物資源研究所昆虫適応遺伝子研究グループチーム長
木内信[キウチマコト]
(独)農業生物資源研究所企画調整部研究企画科長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。